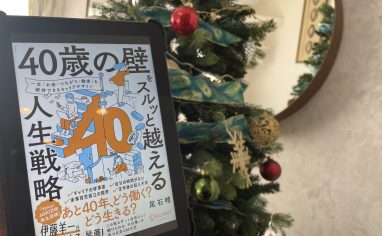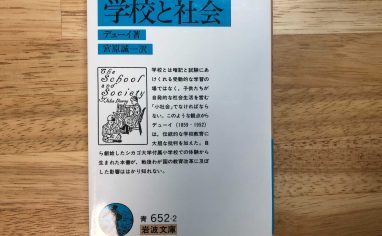世界で最も読まれた論文「リソース・ベースト・ビュー」とは何か?
(本日のお話 2238字/読了時間3分)
■こんにちは。紀藤です。
昨日は朝から立教大学のリーダーシップの授業でした。
大学1年生と2年生のクラス、それぞれの雰囲気は違いますが、
皆、エネルギーが満ちていて、微笑ましく感じた時間でもありました。
学生の皆が、良いつながりを作りながら、
リーダーシップを学べるよう、引き続き尽力したいと思います。
また夜は、大学院の仲間とのお食事会でした。
*
さて、本日のお話です。
先日から始めました『世界標準の経営理論』の読書レビュー、今日も引き続きお届けしてまいります。
30の理論のうちの3つ目です。まだまだ果てしない!ですが、コツコツ読み解きたいと思います。
さて、第3章では、経営学の中でも非常に有名な理論、「リソースベーストビュー(Resource-Based View/RBV)」について取り上げられています。日本では「資源ベース理論」と訳されることもありますね。
ふと思い出すのは、4年前、立教大学大学院の入試問題にもこの理論が出てきたこと。あの時は正直、言葉を調べて書き連ねただけでしたが(汗),大学院での学びを経て、また改めてこの書籍を通じてリソースベーストビューに触れることで、ようやくその意義が腑に落ちてきた気がしています。
ということで早速みてまいりましょう!
■「リソース」に注目した経営理論
「リソースベーストビュー」は、1991年にJ.バーニーによって提唱された理論です。企業の競争力を「リソース(経営資源)」という視点から説明するもので、学術界では6万7千件を超える引用があるという、非常に影響力のある論文となっています。(世界で最も読まれている経営学の論文だそう)
ただ、バーニーは突如この理論を生み出したわけではなく、前史として4つの先行研究を統合する形でこのフレームを築いており、この系譜を理解することが大切だと著者は述べています。
1. ペンローズ(1959年)
企業は経験を通じて、リソース(人材・技術など)を有効活用する術を学び、成長する――そう説いたのがペンローズの理論です。企業を「静的」ではなく、「動的」に捉えた視点は当時としては革新的でした。
2. ワーナーフェルト(1984年)
企業が特定のリソースを独占することは、そのままアウトプットの独占に通じ、超過利潤を生む――これは、SCP理論(Structure-Conduct-Performance)を応用したアプローチです。
3. バーニー(1986年)
こちらもワーナーフェルト同様、「リソースの独占性が競争優位」につながるという視点を補強した研究です。
4. ディルクスクールの理論
リソースの模倣困難性に着目し、以下の3点を強調しました:
――――
(1)蓄積経緯の独自性(歴史に基づく積み重ね)
(2)因果の曖昧性(成果の理由が明確でない)
(3)社会的複雑性(組織文化や関係性が複雑で他社が真似できない)
――――
Appleの「デザイン力」などはその好例で、製品デザインだけでなく、顧客接点全体にわたって模倣困難な強みとなっています。なので、サムスンのギャラクシーがiPhoneを真似ても、そのシンプルなデザインの極みは真似できない、というようなイメージです。
■バーニーの1991年論文の本質
バーニーは、SCP理論が前提とする「完全競争」に対し、現実の企業活動はそこから逸脱していると指摘します。そして、以下の2つの前提に基づき、RBVを構築しました。
――――
(1)企業リソースの異質性:企業ごとに持っているリソースが異なる。
(2)企業リソースの不完全移動性:リソースが簡単には他社に移転・模倣できない。
――――
この前提のもと、競争優位とは「他社にはできない価値創造戦略」であり、それが持続的(10年程度)に続くならば、持続的競争優位と呼べる――という理論枠を提示したのでした。
そして、このRBVの有効性については、55本の論文、549の分析モデルを検証したメタ分析で、約53%がRBVを支持する結果が出たそうです。
とはいえ裏を返せば、半数近くは支持していないということであり、理論の説明力には限界もあるわけです。特に以下の課題が指摘されています:
――――
・トートロジーの問題:「価値があるから価値がある」と循環してしまう危険。
・ブラックボックス性:リソースがどう活用され、成果に至るのかが不透明。
・処方性の弱さ:具体的な「どうすればいいか」が語られていない。
――――
■RBVに関する処方箋「アクティビティ・システム」
本書で著者が紹介している、RBVに関連するフレームワークが「アクティビティ・システム」です。これは、企業活動の相互連関性に着目したもので、特にサウスウエスト航空の事例が有名です。
――――
機体はボーイング737のみ → 購入コスト低い・訓練効率が高い
機内食なし → コスト削減&ターンオーバー短縮
ターンオーバー平均15分 → フライト回数最大化 → パイロット1人当たりの効率アップ
低コスト構造を維持したまま、短中距離特化で競争優位を確立
――――
というように、個々の活動が戦略と整合しながら、相互補完的に組み合わさっている点が、模倣困難性に直結していることを示した好例です。(『ストーリーとしての競争戦略』にも紹介されていましたね)
■まとめと感想
この章を読み終えて改めて感じたのは、「持続的競争優位」とは大企業だけの話ではなく、中小企業や個人事業にも通じる考え方なのだろうな、ということです。
個人のリソースも、それは持続的な競争優位性に繋がります。人的資本(経験、知識、専門性、健康)、社会的資本(人のつながり)、経済資本(金銭的な余裕、投資力)などを作ることが、個人の競争優位性にも繋がることは、個人事業主にも全く同じことが言えます。
私も、メルマガやnoteでの発信、書籍の出版、教育などをもっと複雑に絡み合わせながら競争力に育てられたらな、などと考えながら読み進めた次第です。簡単ではありませんが、だからこそ、学びがある。そんなことを改めて感じさせられる一章でした。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
※本日のメルマガは「note」にも、図表付きでより詳しく掲載しています。よろしければぜひご覧ください。
<noteの記事はこちら>