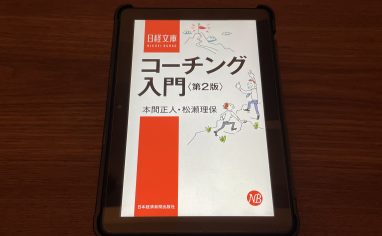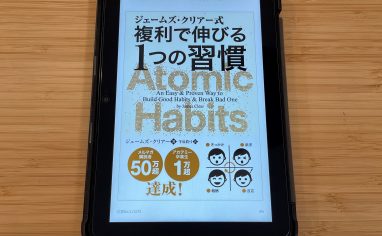「認知バイアスの理論」ー私たちは色メガネで世界を見ているー
(本日のお話 2715字/読了時間3分)
■こんにちは。紀藤です。
昨日は朝から21kmのランニング。
また子どもと地下鉄博物館へのおでかけなどでした。
*
さて、本日のお話です。
本日も、大著『世界標準の経営理論』の全章レビュー、引き続きお届けしてまいります。
本日は第20章「認知バイアスの理論」についてです。
「認知バイアス」という言葉は、ビジネス書などでも有名なので、聞いたことがある方も少なくないかと思います。
例えば「ハロー効果」(=ある一側面が秀でていると、他のこともできそうと思ってしまう)などはとても有名です。
こうした認知バイアスが「人の評価」「意思決定」に影響を与えることがしばしばあるため、経営学という文脈にも大いに関わります。ゆえに、この認知バイアスも「ミクロ心理学ディシプリンの経営理論」という位置づけで、本章で取り上げられています。
ということで、早速内容を見てまいりましょう。
■個人レベルの認知バイアス
まず、個人レベルの認知バイアスについては、以下の4つが紹介されていました。
(1)ハロー効果
ハロー効果とは、後光が差すという意味です。先にも紹介しましたが、ある人が高学歴だったり、スポーツに秀でていると、その人全体の印象が高まりやすくなります。たとえば、「英語が上手にしゃべれる人は、他分野でも頭が良さそう」といった印象が代表例です。
この効果を利用しているのが、人気のある著名人や芸能人を宣伝広告に使う理由ですすね。そのポジティブなイメージが、ハロー効果を通じて商品やサービス全体に波及することを期待して起用するわけです(なので、スキャンダルがあると、即いなくなってしまいます…(汗))
(2)利用可能性バイアス
これは、人が記憶に留めていた情報を引き出す際に、「簡単に想起しやすい情報を優先的に引き出し、それに頼ってしまうバイアス」のことです。
いわゆる「金づちを持つと全部くぎに見える」という現象に近いかもしれません。
より細かく言うと、
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<利用可能性バイアスの特徴>
・想起容易性:大きな事件など、記憶時のインパクトが大きい情報
・検索容易性:記憶から即座に検索しやすい情報(例:「とりあえずいつものやつをやっとけば間違いない」)
・具体性:身近な人から直接聞いた具体的な情報は、優先して信じてしまう
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
よくあるのが、コーチングを生業としている人が、その他の制度的な問題や評価、経営戦略などの問題もすべて「コーチングで解決しようとする」ケースです(自戒を込めて)。
(3)対応可能性バイアス
これは、他者が何かに巻き込まれたときに、本当の理由は周辺環境にあるのに、原因を当事者の人柄などに帰属させてしまうバイアスのことです。
たとえば、何かミスがあったときに「相手のせいだ」と決めつけてしまう。しかし、よくよく見てみると、その人は「最後のボタンを押しただけ」であり、実際は他の複雑な要因が絡み合っていた——そんなことは職場でも非常によくあります。
「特定の人に原因を求める」というのは、確かに職場でたくさん見かける光景だなと感じます。
(4)代表性バイアス
これは、典型例と類似している事項の確率を過大評価しやすいバイアスのことです。
たとえば、「日本人は◯◯である」とか、「中国人は◯◯である」といった、典型イメージに引きずられるものです。
本書では「関西人は冗談が好き」といった例で紹介されていました。
■組織レベルの認知バイアス
組織レベルでは、以下の2つの理論が紹介されていました。
経営学で使われる理論として「社会アイデンティティ理論」と「社会分類理論」が解説されています。
(1)社会アイデンティティ理論
これは、「私は愛知県出身だ」「私はリクルート出身だ」といったように、自分が社会的なグループのどこに所属しているかという認識にまつわる認知バイアスです。
こうしたアイデンティティは、会社や国といった大きな社会グループでも形成されます。
「元リクルート」「元◯◯会社」といった経歴がアイデンティティとなり、認知バイアスに影響を与えることがあるのです。
本書で紹介されていた事例として、国際間のM&Aデータ3806件を調べたところ、中国・ブラジル・インドなど新興国企業は、先進国企業を買収する際に、平均よりも高い買収プレミアムを払う傾向があるそうです。
これは、自分が新興国を代表しているという社会的アイデンティティによって、「どうしても先進国企業を買収したい」という思いが働き、それが高いプレミアムにつながっていると考えられているとのこと。
(2)社会分類理論
これは、組織の中で人が無意識にグループ分けをしてしまうという認知バイアスです。
たとえば、「中途組」「プロパー組」といった括りや、複数の会社が統合してできた際の「元◯◯会社出身」といった分類です。
こうしたグループに対して、「自分と同じグループには好意的になる」というバイアスが存在しており、これをイングループ・バイアスと呼びます。
このバイアスは「こちら」と「あちら」を分ける力として働き、結果として組織内にフォルトライン(亀裂)を引くことにもつながります。
特に、知識・能力・経験・価値観といったタスク型の多様性は組織にプラスの影響を及ぼしますが、性別・国籍・年齢など表面的な多様性は、必ずしもポジティブに働かないこともあると指摘されています。
表面的なダイバーシティではなく、「深層のダイバーシティ(内面の多様性)」こそが、組織には重要なのですね。
■補足:マインドフルネス
本書の最後には、コラムとしてマインドフルネスについても触れられていました。
マインドフルネスは東洋的な考え方であり、一見経済学とは少し離れているようですが、「今この瞬間に意識を向ける」という姿勢を通じて、物事をバイアスなく見る方法として紹介されていたのが興味深かったです。
■まとめと感想
改めて、認知バイアスというのは、自分にも無意識に働いていると感じます。
そういえば大学院1年次の時に、ジェンダーに関する意識について皆でアンケートを取ったことがありました。たしか、リーダーシップの授業だったと思います。
その際、「男性リーダーと女性リーダー、どちらの方が活躍しやすいか」といった質問があり、明らかに性別によって回答傾向が異なっていたのが印象的でした。
そのとき、先生が言った、「色々と勉強して、フラットな思考を持っていると思われる人たちでも、このような差が出るということが、まさにバイアスなのかもしれませんね」というような言葉がとても印象に残っています。
特に、日本では「男らしさの社会」の傾向が強いということが、ホフステードの文化的差異の研究で明らかになっていると聞いたことがあります。
これも、私たちの認知に大きな影響を与えている一例かもしれません。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
※本日のメルマガは「note」にも、図表付きでより詳しく掲載しています。よろしければぜひご覧ください。
<noteの記事はこちら>