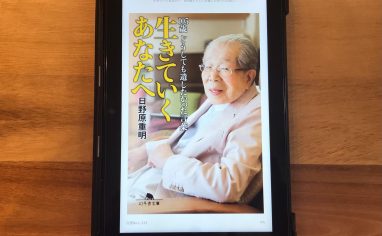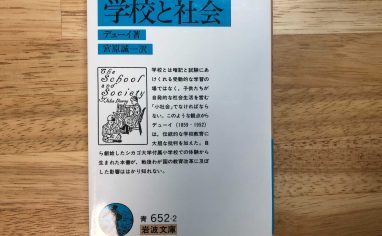教える、というより寄り添う —リーダーシッププログラムを終えて思うこと
(本日のお話 2953字/読了時間3分)
■こんにちは。紀藤です。
昨日は2件のアポイント。
また5kmのランニング。その他書籍の執筆などでした。
毎週土曜日は、個人的な手記ではありますが
「一週間の振り返りと学び」を書いてみたのコーナーでございます。
特に今週は「春学期の全14回にわたって実施された立教大学の『ビジネスリーダーシッププログラム』が終了したことが印象的でした。
そして、教員として携わらせていただく中で、感じる事が多々ある時間でした。
今日はその大学の授業を中心に書いてみたいと思います。
それでは、どうぞ!
■3か月間の大学の授業が終わる
大学のリーダーシッププログラムの最後の授業では、3か月間、プランを磨きながら、ときには深夜までディスカッションを重ねてきた仲間たちと、お互いに感謝やフィードバックを伝え合う、そんな時間が中心でした。
大学1年生、2年生とそれぞれ基本形は同じですが、大学2年生にとっては、2度目のグループワークの経験で慣れています。また、2年生はアルバイトやゼミ、部活など、さまざまな役割を担っている中で、こうした枠組みに投資する時間とエネルギーは100%とはなりません。プロセス自体は比較的さっぱりとしているのが印象的ですが、プランを完成させるステップは、要領を得ながら、短期間で仕上げる力には、流石だなと感じさせられます。
一方で、大学1年生にとっては、初めての大学生活、そして最初の授業です。「友達はできるだろうか」「一人暮らし、大丈夫だろうか」「学校生活に馴染めるだろうか」「自分はコミュニケーションが苦手だけど、大丈夫だろうか」——そんな不安をたくさん抱えながら、カルチャーショックの中で向き合ったグループワークでもありました。
そうした中で、最後の回では、一人ひとりが「リーダーシップ宣言」として、このプログラムで学んだことや、仲間への感謝のメッセージを、涙ながらに語る姿があり、「本当に3ヶ月で成長したんだな」と胸が熱くなるのを感じていました。
最後には、私も教員という立場の役得もあり、皆からメッセージ付きの色紙や花束をいただき、心があたたかくなる時間でした。
※立教大学ビジネスリーダーシップ・プログラム
■教員という立場
この「ビジネスリーダーシッププログラム」における教員の立場は、「支援者」や「コーチ」に近いものだと私は感じています。
というのも、授業の運営や受講生一人ひとりへの関わりは、主に学生メンバーである「運営スタッフ」が担っているからです。
教員は、学生では伝えにくい社会人としての事例を紹介したり、判断に迷ったときのコーチ役として、運営スタッフを支える役割にあります。
運営スタッフ自身も、スタッフという立場を通じて自分のリーダーシップを磨く機会を得ています。むしろ、人前に立って話をしたり、チームのファシリテーションをすることこそが、リーダーシップを育てる時間になります。
そういう意味で、「受講生」という立場から「運営する側」へ、さらにそれをまとめていく立場へと成長できるこのプログラムの構造は、とてもよくできた仕組みだと感じます。
■フィードバックはやっぱり難しい
そんな立場から、教員としては、学生のクライアント向け企画に対する「フィードバック」を行う場面がよくあります。
たとえば、プランの内容に論理的な飛躍がないか、データ収集方法に無理がないか、プレゼンのわかりやすさ、現実性があるか、など。最終プレゼンの評価項目に照らして、「戦えるプラン」になるように伝えていくのが役割です。
そうした中で、色紙のメッセージにも「鋭いフィードバック」「温かくてフレンドリーな雰囲気づくり」などの言葉をいただき、少しは伝わっていたのかなと嬉しく思いました。
具体的なプラン内容のフィードバック、たとえば「引用の仕方が弱い」「スライド3と4の間に論理の飛躍がある」といったことは、比較的伝えやすいです。そこには合理性があるからです。
しかし、難しいのは「チーム内での関わり方」に関するフィードバックです。たとえば、ある人のリアクションが薄く感じられる。何かを話すとき、少し手を仰ぎ見るような様子がある。私は比較的リアクションが大きいタイプなので、反応が返ってこないと不安になることがあります。
けれど、内省的な人にとっては、それが「普通」でもあるわけで——。
そうしたとき、「もっとリアクションを大きくしたほうがいい」と伝えるのは、自分の“好み”に過ぎないかもしれません。むしろ、その人らしさを損ねてしまうかもしれません。
その人が「自分のファシリテーションをどう思う?」というような明確な問いを投げてくれれば伝えやすいのですが、「好みの押しつけ」になってしまっては意味がないとも思う。
どのタイミングで、どのくらいの頻度で、どんなトーンで伝えるのが良いか…そんなことを悩む場面もありました。
時には「もっと気づいたことをフィードバックすべきだったのでは」と反省することもあります。もちろん、気になることが明確であれば、できるだけ伝えるようにはしていますが。
“支援者”として、皆が輝けるように、一瞬一瞬の関わりに気を配る。それが私の教員としてのスタイルであり、好みなのだと思っています。
これが正解かどうかはわかりません。でも、他の先生たちとも語り合ってみたいなと思ったりもしました。
■自分のことばで語るということ
さて、話は変わりますが、ようやく来年刊行予定の「強みに関する本」の執筆を下書きレベルで始めることができました。
基本的に論文から得た「強みの知見」を、できるだけわかりやすく伝える編集作業のようなものなのですが、これがなかなか難しい。
これまでは、論文を要約し、正確で誤解のない言葉で伝えればよかったのです。でも、今回はそれだけではダメ。「読んで面白いか」「温度があるか」「自分の経験が乗っているか」なども求められます。
たとえば、「263kmマラソンの体験記(※)」のように、感情が乗っているものであれば言葉も自然に出てきます。それは手前味噌ですが、自分でも面白いもの書けたな、と感じます。
※人生で大切なことは全部、263kmマラソンで学んだ
https://note.com/courage_sapuri/n/n637bbc8df797
しかし、論理的な文脈の中に“自分の言葉”や“温度”を込めようとすると、それに見合う体験が自分の中にまだ足りていないことを痛感します。
まさに、いま書いているのは「下書き中の下書き」のような状態。これを何度もブラッシュアップして、同時にそれにふさわしい体験も重ねながら、良いものにしていけたらと思うのでした。大変な旅路になりそうですが、まずは歩み出せたことが良かったです。
■まとめ:妥協せずに追い詰める
何かを深めていくためには、「知の深化」が必要です。そのためには、ひとつの領域にぐっと絞って、妥協せずに掘っていく姿勢が大事です。
「これぐらいでいいか」ではなく、「まだまだだ、全然しょぼい」と自分を追い込んでいくほうが、より良いものが生まれると感じています。
ここから半年は、妥協せず、成果として残せるものをしっかり書いていけたらと思います。
同時に、それだけに没頭してしまうと、視野が狭まり、面白みのないものになってしまう可能性もある。だからこそ、外にも目を向けながら、いろんな人と対話しつつ進めていきたい。そんなふうに思っています。
…と、私の頭の中のつぶやきをつらつらと書いてしまいましたが、
最後までお目通しいただきありがとうございました!
※本日のメルマガは「note」にも、図表付きでより詳しく掲載しています。よろしければぜひご覧ください。
<noteの記事はこちら>