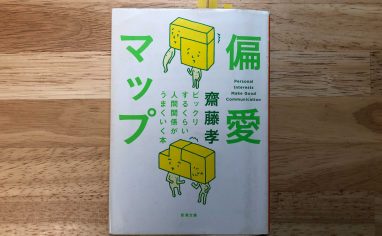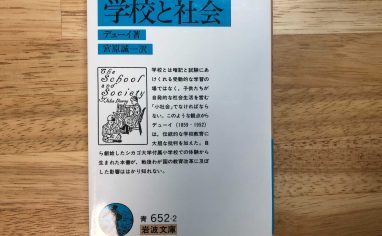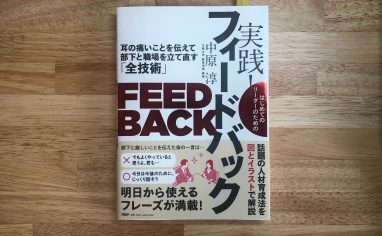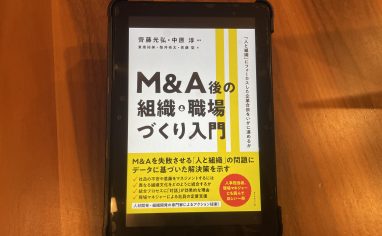「なぜビジネスパーソンは、経営理論を学ぶ必要があるのか?」3つの理由
(本日のお話 2754字/読了時間4分)
■こんにちは。紀藤です。
昨日は、午前から午後まで、大学のリーダーシップの授業でした。
学生の皆が向上心に溢れており、非常に刺激を受けた時間でした。
これからが楽しみです・・・!
*
さて、本日のお話です。
突然ですが、皆さまは「積ん読本」をお持ちでしょうか…。
勉強したくて買ったものの、なかなか手を付けられずにいる本、割と結構生まれてしまうものです。
私にも山のように積ん読本がありますが、その中で「これはボスクラスだろうと思っている積ん読本」がありました。それが、入山章栄先生が書かれた、こちらの『世界標準の経営理論』です。
========================
『世界標準の経営理論』
入山 章栄 (著)
========================
2020年のダイヤモンド社ベスト経済書1位に輝き、そのページ数はなんと820頁。この本が書店に並んだときが「分厚い本ブーム」でした。トマ・ピケティの『21世紀の資本』と同じく購入したものの、そのまま、本棚で眠っている人もいるのでは、、、と想像しています。
今日から、この本(40章もある!)をじっくり読み進めつつ、自分なりの解釈も含め、まとめていきたいと思いました。ということで、本日は開会の挨拶でございます。
――――――――――――――――――――――――――
<目次>
5年ぶりに本棚から目覚める理由
「経営理論」を学ぶべき3つの理由
理由1:「なぜ(Why)の説明」がなければ人は動かない
理由2:「理論ドリブン」の思考は圧倒的に汎用性が高い
理由3:理論は時代を超えて不変である
「経済学・心理学・社会学」を横断する
経営理論は、フレームワークではない
――――――――――――――――――――――――――
■5年ぶりに本棚から目覚める理由
さて、そんな本を「5年ぶり」に本棚から目覚めさせようと思いました。
私自身、大学院の「経営学修士」を取得しましたが、経営学については、正直全然自身がありません(汗)「人や組織マネジメント」に関する知識が中心だったため、経営理論は後回しになっていた、というのが言い訳です。
「読書における最も効率のよい学び方」とは、「読んだ本を、各章ごとにブログにまとめること」です。選書は大事ですが、骨太の本を選び、自らの言葉で、自らの脳内フィルターを通じて言語化すること、それを何日にもわけて継続的に読み進めることで、学んだ内容が深く定着し、脳内のパラダイムが書き換わる感じがするのです。
加えていえば、「生成AIの発達も、ブログでアウトプットすることに役立つ」ようになりました。これまではどうしても、誤字脱字のチェックや句読点の調整、文字の整形などに多くの時間がかかっていました。しかし、今では生成AIの力を借りることで、そうした修正にかける時間がぐっと減りました。
「思ったこと・学んだこと」を口頭で音声入力をしながらアウトプットしながら文章化することで、さしたる手間もなく、勉強にもなり、記録にもなり、発信にもなり、一石三鳥です。
ということで、これから毎日ではありませんが、この『世界標準の経営理論』を少しずつ読み進めて、まとめていきたいと思います。
■「経営理論」を学ぶべき3つの理由
さて、今回は「序章」についてのまとめです。
序章では、まず「経営理論とは何か」ということが語られています。
著者によれば、「理論とは、How、When、Whyに答えるものである」と述べています。
そして、「なぜビジネスパーソンが経営理論を学ぶべきなのか」について、3つの理由を挙げています。
◎理由1:「なぜ(Why)の説明」がなければ人は動かない
経営理論はビジネスにおける「なぜそうなるのか?」という問いに対し、明快な説明を与えます。人は納得して初めて行動する生き物。理論は、複雑な事象をある角度から切り取る鋭利なナイフのようなものであり、人を説得し、納得を促す道具になります。
たとえば、「なぜダイバーシティが必要なのか?」「なぜガバナンスが重視されるのか?」といった問いにも、理論をもとに説明できれば、人の行動を引き出すことが可能になるわけです。
◎理由2:「理論ドリブン」の思考は圧倒的に汎用性が高い
理論ドリブンとは、理論から出発して物事を考えるスタイルのこと。対照的に「現象ドリブン」は、現象から理論を当てはめていく方法です。
たとえば「買収プレミアム(買収額に上乗せされる金額)」という現象を説明するには、情報の経済学、エージェンシー理論、心理学、ソーシャルネットワーク理論など、複数の理論が必要になります。しかし、こうするとどうしても浅くなりがちです。
そのため、本書では「まず理論を深く学ぶ」という姿勢を大切にし、30程度の理論を厳選して紹介しています。理論から現象を捉える思考法の方が、より深く、鋭く物事を捉える“メガネ”を手に入れることができるというわけです。
◎理由3:理論は時代を超えて不変である
本書で紹介される理論の多くは、1930年代、50年代、70年など、今から50年以上前に生まれたものもあります。しかし、理論は古びれることがなく、今も現場で使い続けることができるほど、理論には普遍性があります。
だからこそ、時代を超えて読み解く価値がある、としています。
■「経済学・心理学・社会学」を横断する
また、本書の大きな特徴として、3つの異なる「ディシプリン(学問的枠組み)」を横断的に扱っている点が挙げられます。それを「3つの理論ディシプリン」と呼んでいます。
・経済学ディシプリン:人は合理的に意思決定をするという仮説に基づく考え方。
・心理学ディシプリン:人は経済学が仮定するほどには合理的ではなく、感情的・認知的に限界がある存在だという視点。
・社会学ディシプリン:人と人、組織と組織の“間”にある関係性に注目し、弱いつながりの強さなどを理論化するアプローチ。
このように、経済学・心理学・社会学を横断しながら経営理論を伝えていくという点が、本書の魅力の一つであり、それを可能にしたのが、著者の入山先生の独特の経歴にあることも述べられていました。
■経営理論は、フレームワークではない
その他でも面白かった点は、「経営理論=フレームワークではない」という話(例:SWOT分析は理論ではない)、あるいは経営学・経済学の学術的なトップジャーナルなど、アカデミックな世界におけるコンセンサスなどもコラムで紹介されており、興味深いものでした。
こうした第一人者の先生が解説してくれる「思考の軸」としての理論の重要性はよくよく感じるところなので、これから一つひとつの章を、じっくり読み込むのが楽しみになる一冊です。
ということで、明日以降も、少しずつこの本に登場する理論を紹介していきたいと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
※本日のメルマガは「note」にも、図表付きでより詳しく掲載しています。よろしければぜひご覧ください。
<noteの記事はこちら>