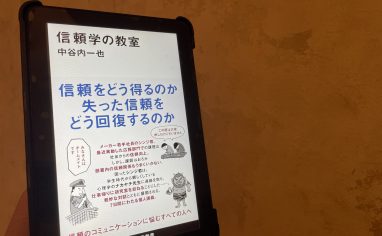意思決定の理論 ー直感と合理性、どちらが役に立つのか?ー
(本日のお話 2968字/読了時間3分)
■こんにちは。紀藤です。
昨日は、新入社員60名の方向けの
「プロアクティブ行動研修」の実施でした。
フィードバック探索などお伝えし、皆さまの配属後に、
自らフィードバックを行う重要性などを、ロープレを含めて行っていただきました。
皆さまご参加いただき、ありがとうございました!
また、午後は1件のアポイント。
ならびに夜は、知人らとトランペットとピアノのリサイタルにいってきました。
現代音楽って、こんなに何でもありなんだと驚きました…!
*
さて、本日のお話です。
本日も、大著『世界標準の経営理論』の全章レビュー、引き続きお届けしてまいります。
本日は「第21章 意思決定の理論」です。
意思決定論というのは大きく2つあるそうです。
1つ目が「規範的意思決定論」(合理性などを基準にバイアスがない状況でのあるべき合理的な意思決定を導く分野)。
2つ目が「行動意思決定論」(現実的には人は時に合理的に決定しないことも含めて意思決定するもの)に分かれ、長らく研究されてきたそうです。
この意思決定に関わる理論について、経営学の視点から整理できて、興味深く、また勉強になった章でした。
それでは早速まいりましょう!
■規範的意思決定論:期待効用理論
まず、1つ目の意思決定理論が、合理性などを基準にバイアスのない状態でのあるべき意思決定を導き出す分野「規範的意思決定論」です。
これは1940年代に数学者のフォン・ノイマンとモルゲンシュテルンによって提示され、経済学を中心に使われるようになった理論だそうです。キーワードは「期待値」です。
「期待値」というのは、特定の事象が起きる確率と、そこから得られる価値の積のことを指します。
例えば、A事業とB事業の「成功する確率」と「失敗する確率」を合理的に考えて、うまくいく確率×得られる利得 − 失敗する確率×失う損失 を計算して、どちらの方が得かを判断するという、非常に合理的な意思決定です。
ただ面白いのが、「人が所有する資産が大きくなるほど、投資などによって追加で得られる利得に対する効用の上昇が小さくなる傾向がある」という点です。
画像
P379 資産が大きいと「リスク回避的」になる図
余談ですが、20代の頃、貯金が100万円だったときに追加の1万円は非常に嬉しかった印象があります。
そして、その金額が嬉しかったので「株に一攫千金狙いでドーンと投下」→「暴落して、なけなしの資産がさらになけなしになる」ということがしばしばありましたが、今は、地道に投資信託みたいになりました。(微々たる資産の増加ですけれど)これも「リスク回避性」が高まったからかもしれません。
ちなみに、基本的に資産が大きい人ほどリスク回避的になる傾向があるようです。一方、資産の大小にかかわらずリスク選好が変わらないリスク中立的な人や、資産が高いほどリスクを好むリスク志向的な人もいるそう。
加えて、自社に全てをかけている経営者と、複数の企業に分散投資している投資家を比較した場合、経営者は一度の大きなミスが自分のキャリア資産に与える影響が大きいためリスク回避的に、投資家は影響が相対的に小さいためリスク志向的になる
——こうしたことから「エージェンシー問題」につながるとも述べられていました。他の経営理論との接続も、興味深いです。
■ 行動意思決定論(意思決定バイアス)
2つ目の軸は、1970年代頃から研究が盛んになった分野です。第一人者ダニエル・カーネマンをはじめとした研究者たちが成果を挙げ、「行動経済学」という分野を確立してきました。
大きく3つの理論があります:
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・プロスペクト理論
・フレーミング効果
・二重過程理論(Dual Process Theory)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◯1. プロスペクト理論
プロスペクト理論とは、「人が投資などから得られるリターンと、それに対する主観的な効用との関係」を示したもので、大きく以下の3命題があります:
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・命題1:人は投資交換に対して主観的なリファレンスポイントを持つ
・命題2:人は損失をより避けたがる(損失回避性)
・命題3:利得が増えるほど効用の追加的な伸びは減少する(利得が増えるほどリスク回避的になる。または損失が続くほど追加損失に鈍感になる)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この理論により、以下のような現象が説明できます。
例えばエスカレーション・コミットメントという意思決定があります。これは、事業の失敗が明らかにもかかわらず撤退できず、さらに資金を投入してしまうというもの。これは命題3の「損失に対する感覚が鈍くなる」ことに該当します。
◯2. フレーミング効果
リファレンスポイントを意図的にずらすことで、人の意思決定は変わる、という理論です。
<利得を強調したフレーミング>
この事業に投資すれば3分の1の確率で300万円を得るが、3分の2の確率で得るものはゼロになる
→「ゼロ」をリファレンスポイントにすることで利得を強調
→ リスク回避的になる
<損失を強調したフレーミング>
この事業に投資すれば3分の1の確率で目標達成、3分の2の確率で目標から300万円下回る
→「300万円」をリファレンスポイントにして損失を強調
→ リスク志向的になる
というようなものです。これもなんとなく聞いた事がある話ですね。
◯3. 二重過程理論(Dual Process Theory)
次に人の脳内での意思決定過程が2種類の思考プロセスによって動いているという理論です。これも非常に有名です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・システム1:とっさの判断。自動的・直感的な処理。思考の負担が少ない。
・システム2:意識的・論理的な思考。時間をかけて段階的に行う。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
衝動買いはシステム1の典型であり、従来の意思決定論ではシステム2に頼ることが推奨されてきました。
■ 近年の研究結果=直感は侮れない
ここで面白いのが、「論理思考よりも直感の方が、正確な未来予測を可能にする」というレビュー論文も出てきている、という点です。
特に、環境の不確実性が高いときには、システム2的な思考で多くの変数を組み込んでも、その変数自体がエラーを含む可能性が高くなります。すると、必ずしも優れた意思決定につながらないというわけです。
つまり、不確実性の高い環境では、「直感的な意思決定の方が優れている」という研究結果が、近年では続々と報告されているそうです。
このような環境下で「直感をどう鍛えるか」が重要となり、著者はSECIモデル(知的コンバット、アブダクション)や、ダイナミックケイパビリティ( センシング(機会を察知する力)、サイジング(機会を捉えて動く力))などのモデルが有用になるだろう、述べていました。
■まとめと感想
「意思決定」というのはマネジメントの文脈でよく聞くキーワードです。
それらを、
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・合理的に考える「規範的意思決定」
・直感的に考える「行動意思決定」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
という2つの視点があり、それぞれに理論が整理されていてスッキリした感じがしました。
また、システム1・2の話はパーソナリティ検査などにも通じるような印象を受けますし、リファレンスポイントの変化も、自分の中で「どれくらいまでお金をかけるか」の感覚が年齢や資産状況によって変わってきているという点で、非常に実感を伴う内容でした。
経営学というと大きな話になりがちですが、こうして身近な行動や感覚と結びつけて考えられると、「あるある!」と思えて面白さが増すなと感じました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
※本日のメルマガは「note」にも、図表付きでより詳しく掲載しています。よろしければぜひご覧ください。
<noteの記事はこちら>