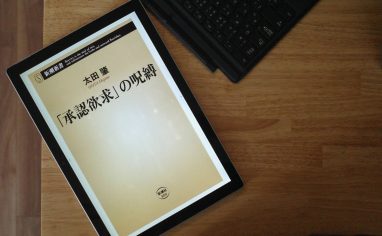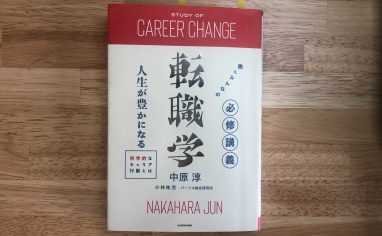3歳児は「ガマンできない」ものである ー自己制御の研究よりー
(本日のお話 2152字/読了時間2分)
■こんにちは。紀藤です。
昨日は福岡の天神へ。
また夜は、18年ぶりの大学時代の仲間との食事会でした。
当時の関係を思い出しながら、
あっというまに20年近くの時を越えて馴染んだ空気になり
「色々あったようだけど、自分は昔も今も自分なんだなあ」と
しみじみ感じる時間でもありました。
本当に、こうした繋がり、大事にしたいなと思った次第。
*
さて、本日のお話です。
性格の強みの一つに「自己制御(Self-Regulation)」と呼ばれる特性があります。
最近、この「自己制御」に関する研究の著書を読みながら、
子育ても含めて「なるほど…!」と勉強になることがありましたので、
今日はそんな自己制御についての学びを、ご紹介できればと思います。
それでは早速まいりましょう!
===================
自己制御の発達と支援 (シリーズ支援のための発達心理学)
amzn.asia
1,650円
(2025年08月13日 16:52時点)
===================
■あらゆることに影響を与える「自己制御」
私たちは「ガマンする」ことを、発達する中で覚えていきます。
自分が思ったことを、そのまま伝えると相手を傷つけるかもしれない。
なので、相手の気持ちを配慮して、伝え方を考える。
あるいは、コーラのがぶ飲みはよくないので、控える。
はたまた、将来のために、受験勉強を頑張る。
こうした、自分の衝動をコントロールしたり、努力のコントロールをするなど、「自分の思考や行動を制御しようとするチカラ」が『自己制御』です。
もうちょっと詳しく言えば、「自己制御」は以下の3つの要素があります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1.衝動性の制御(今の報酬を先延ばしにできるなど)
2.実行機能(目標に向けて努力を積み重ねるなど)
3.気質(生まれ持った特性。自己制御に関わる因子が発見されている)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
そして、この「自己制御」は、年収、健康、仕事の成果など、あらゆる側面に影響を与えていることが知られています。
有名なダニーデンの双子の研究では、1972~73年のニュージーランドで生まれた双子の赤ちゃんを、11歳までの自己制御の力が、32歳になったときの、健康面、経済面、生活面、違法行為などを調査しました。
すると、11歳時点で「自己制御」が高かった子どものほうが、年収も高く、肥満率も低く、仕事が長続きしやすく、学業成績も高かった傾向があることがわかりました。
そうした、「自己制御」がもたらす影響があきらかになってきたことからも、自己制御の研究は盛んに行われてきた、という歴史があります。
■「自己制御」はどうすれば高められるのか?
では、こうした自己制御は、どうすれば高まるのでしょうか?
以下、研究からの示唆を見てみてましょう。
◎(その1)年齢に従って発達する
自己制御が高まるのは、まずは年齢による発達です。
幼児期→児童期と高まり、青年期で一度下がり、成人期になるとまた高まります。(ちなみに、壮年期以降になると、損得のバランスは高まるが、認知面の判断は低下するそうな)
さて、我が息子(4歳)は、衝動の赴くままに行動をしています。
小さい子どもにおもちゃを譲る、などなかなかできません。
しかし、これは脳の発達と関連しているため、「普通の話」なのです。
たとえば、3-7歳児を対象にした研究では、「小さい子のわがままを許すことができる」は、3歳はほとんどできません。4歳は半分くらいができます。5~7歳だと3分の2くらいできるようになります。
SNSのXで、「3歳の子どもがほしかったプレゼントがもらえなくて泣き叫び、ものを壊しまくっている動画」が流れてきて、そのコメント欄には「親の教育が…」「大人になってから心配」みたいなことが書かれていましたが、発達としてみても「めちゃくちゃ普通」なわけです。
(なので、温かく見守りましょう……!)
ちなみに、青年期に入ると、脳の構造が変化し、自己制御の力が一時的に低下します。その結果、衝動が我慢できない、朝起きれなくなる、などの変化が訪れることが、近年の研究で明らかになってきたそうです。
◎(その2)自己制御を高める「5つのアプローチ」を利用する
さて、その他には以下のような自己制御を高める研究があります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1.プランニング(課題を小さくする、手順を示す等)
2.ワーキングメモリ(必要な道具だけ準備させる等)
3.抑制(妨害する刺激を減らす、他者が見守る等)
4.シフティング(課題に選択肢を設けさせる等)
5.感情コントロール(目標を決めて意欲を高める等)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
これは、知的障害の子どもへの支援策として本書では紹介されていますが、他にも多く転用できそうです。
たとえば、『プランニング』は、何かタスクに取り掛かる前に「やることリストを書き出す」などにつなげられるでしょうし、『ワーキングメモリ』は、「机の上に余分な物を置かない(デスクトップもそう)」などの工夫ができそうです。
あるいは、『抑制』は妨害刺激を減らすとして、「スマホの通知をオフにする」「甘いものをそもそも冷蔵庫に入れない・買わない」として使えそうです。
■まとめ
この研究をみて、「4歳児の我が息子の衝動っぷり、大丈夫だろうか…?」と思っていたのですが、こう見ると、いや別に普通なんだ、と思いました。
また、気質もあるので、すべての幼児が100%通過するようなものでもないので、これもまたそんなものだよなと、なんだか安心するような気持ちにもなりました。ということで今日は共有をしてみました。
同時に、短期的なこと、衝動や目先のことだけにとらわれるのではなく、長期的に自分を統制して努力を積み重ねる、あるいは衝動を制御するという支援策もあります。こうしたことはできる範囲で、自分自身にも子育てにも、取り入れていきたいと思った次第です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
※本日のメルマガは「note」にも、図表付きでより詳しく掲載しています。よろしければぜひご覧ください。
<noteの記事はこちら>