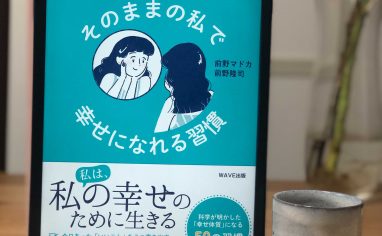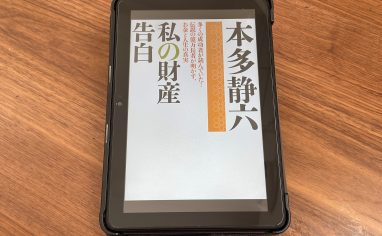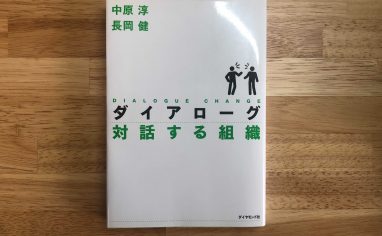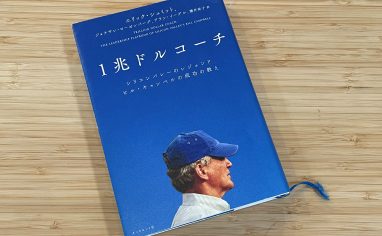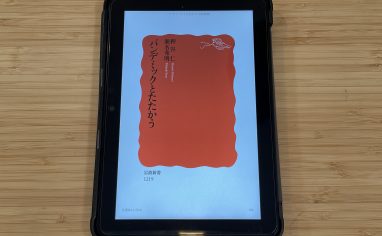今週の一冊『デンマークを知るための70章【第2版】』
(本日のお話 2956字/読了時間4分)
■こんにちは。紀藤です。
引き続き、デンマークに来ております。
昨日は、ランニング8kmをしながらコペンハーゲンの街を散策しておりました。
これからチェコに移動して、また別の国をランニング&散策予定です。
*
さて、本日のお話です。
毎週日曜日はオススメの一冊をご紹介する「今週の1冊」のコーナー。
現在デンマークに滞在しているため、今日はその地にちなんだ少し濃厚な1冊をご紹介します。
=======================
『デンマークを知るための70章【第2版】 エリア・スタディーズ』
村井 誠人 (著, 編集)
=======================
デンマークに関する書籍はいくつか出版されています。
例えば、「デンマークの働き方」とか「デンマークの教育」など、あるテーマの一部分を切り取って分かりやすく説明してくれる本もあります。
しかしながら、あらゆるものは「それ単体」で出来上がっているわけではありません。「国全体のシステムの中で、なぜそれが実現されているのか?」というつながりがあるわけです。
「日本は残業が多い。とにかくデンマークみたいに4時に帰ろう!」と表面的に真似しようとしても難しいのは、それが実現されてきた歴史・経済・政治・制度・文化といった広範囲な背景を見ていないからだ、ともいえます。デンマークを模範とする上でも、その成り立ちを知ることは重要です。
そんな中、この『デンマークを知るための70章』は、デンマークの専門家たちが集まり、旅行ガイドや概説書では触れにくい「国の深層的な構造」について語っている、とても興味深い本です。しかも読みやすくて面白い…!
個人的に激アツな本でした。
ということで、さっそく中身を見ていきましょう!
■本書の概要
この本は、旅行ガイドや概説書では取り扱われにくい「国の深層的な構造」──言語・社会制度・文化・歴史・政治・福祉など──を、多角的な視点から章立てで解説した入門書です。
2009年の初版(70章構成)をベースに、約14年を経て社会・政治・経済の変化を踏まえ、大幅に改訂・拡充されており、編者の言葉を借りれば「旅行ガイドでは分からないデンマークの真の姿」を描いています。
そして、「余裕をもって仕事と生活を楽しむデンマーク人のライフスタイルと、日本との違い」を浮かび上がらせることを目指しているとのことでした。
各分野の専門家が分担執筆することで、専門性と信頼性を両立させながら、「専門書ほど難しくないけれど、旅行ガイドよりも深くて読みやすくて面白い」という本書です。
■目次
では、具体的にどんな内容が書かれているのでしょうか?
本書の守備範囲と、そのテーマについて簡単にまとめました。
(1)デンマークの位置
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・空間・隣接・地理・国際関係 地勢、自治区、隣国との関係、アイデンティティなど
(目次:自治区「フリータウン・クリスチャニア」について、グリーンランド、スウェーデン、フィンランドなどから見たデンマーク、など)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(2)デンマーク語とは
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・言語・語彙・表現 発音、歴史、慣用句、語感、言語文化と社会性
(目次:デンマーク語のhyggeが表すものとは?、など)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(3)デンマークの歴史から
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・歴史の変遷 中世~近現代に至る歴史的流れ、思想・制度変遷
(目次:中世ヴァイキング、キルケゴールの思想、フォルケホイスコーレの過去と現在、など)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(4)デンマークの政治・経済
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・政治制度・経済構造 政治・政策、福祉・税制・雇用関係など
(目次:混迷からイノベーティブ福祉国家へ、デンマークの企業経営ー高い競争力の源泉、デンマークの地方財政ー協調と合意のシステム、など)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(5)デンマークの文学・芸術
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・文化・創造表現 文学、芸術、映画、建築、デザインなど
(目次:アンデルセン、デンマークデザインなど)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(6)デンマークの暮らしと社会
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・社会制度・日常生活 福祉、医療、エネルギー、家族、教育制度など
(目次:デンマーク福祉のウェルフェア・テクノロジー、キャッシュレス社会、デンマーク風力発電の現在など)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(7)デンマークと日本
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・比較・関係性 デンマークと日本の比較、教育・イメージなど
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
■特に面白かったお話
上記の目次をざっと紹介すると、何が書いてあるかよくわからないかもしれませんが、一つ一つの賞には、興味深い話がたくさん書かれています。たとえば、個人的に以下のような話が面白いものでした。(一例です)
◎日本のラジオ体操は、デンマーク由来だった?!
たとえば、「(4)デンマークの政治・経済」では、「フォルケホイスコーレ(成人教育)」が出来上がった背景は、元々は民族意識や市民意識を形成するための農民に対する国民教育の一環でした。そして、当時のデンマークのフォルケホイスコーレが戦前の日本に紹介され「国民高等学校」の成り立ちに影響を与えていたとのこと。
ちなみに当時「デンマーク体操」なるものがありましたが、これが日本の「ラジオ体操第二」に影響を与えたとされています。1932年、デンマーク体操団が日本に来たそうで、アメリカのラジオ体操に加えて、デンマーク体操も影響を与えていると考えられるそうです。(本書では触れられてはいません)
◎高齢社会の介護のための「ウェルフェア・テクノロジー教育」がある
また、「(6)デンマークの暮らしと社会」では、「高齢社会の福祉に対するウェルフェアテクノロジーの活用」については、「介護職の方に、テクノロジーを通じた介護で負担を軽くする国としての教育システムがある」など、見習えるところもたくさんあると感じます。
◎競争のための教育は「死の学校」である
また、若者一人ひとりの自立を支える「エフタスコーレ」という民間の学校が存在しています。その数は242校で、全体の約20%にあたります。
このエフタスコーレについて、以下に本書より引用いたします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
エフタスコーレには、一般の学校とは異なるユニークな特徴がある。まず、生徒は寮で暮らし、他の生徒や教員と生活を共にする。
洗濯、掃除、炊事の手伝いなど、身の回りのことも生徒自身で行う。また、デンマーク語や数学などの必須科目に加えて、スポーツやアートなどの多様な選択科目が開講されており、生徒は自らの興味に応じて学ぶことができる。このようにエフタスコーレでは、教科学習だけでなく、共同生活や多様な学びを通じた人間的な成長にも重きが置かれている。
その背景には、エフタスコーレは19世紀半ばの教育運動にルーツを持つ。牧師N.F.S.グルントヴィ(1783~1872)は、無意味な暗記や試験、立身出世のための競争に基づく当時の学校を「死の学校」と呼んだ。それに対し、学校は一般の市民が自らの生に目覚める場であるべきだと考え、生きた言葉による対話と相互作用に基づく「生のための学校」を構想した。
この思想はやがて、試験を行わず、共同生活の中で自由に学び合う成人教育機関フォルケホイスコーレ(folkehøjskole)へと結実した。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
P418-419
この話は、現在の日本の教育(受験戦争で子どもたちの幸福が下がっている)という問題を考える上で、重要な示唆があるようにも感じました。
■まとめと感想
上記に述べた歴史的背景だけでなく、実際にデンマークを訪れた中で読んでみると、非常に多くの発見がありました。
たとえば、クリスチャニアが生まれたリアルな背景(地域と政治家が間に立って奮闘した経緯)や、「ヒュッゲ」という言葉を文法的にも分析したときに見えてくる、説明しづらいけれど深い意味など。
見て感じた事実に、具体的に史実やデータを知ることで、デンマーク社会の姿を一層立体的に理解でき、大変興味深く、知的興奮を覚えました。「デンマークのことをもっと知りたい人」には、垂涎ものの一冊かと思います。個人的に超ツボの一冊でした。
これからは、旅行に行くときは『地球の歩き方』シリーズで色々巡って、その後に復習として『デンマークを知る70章』シリーズを読もうと思いました(他の国バージョンもあります)。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
※本日のメルマガは「note」にも、図表付きでより詳しく掲載しています。よろしければぜひご覧ください。
<noteの記事はこちら>