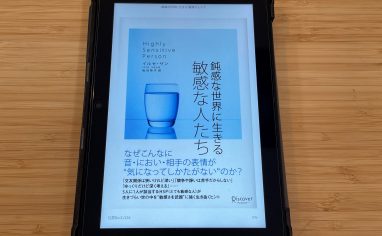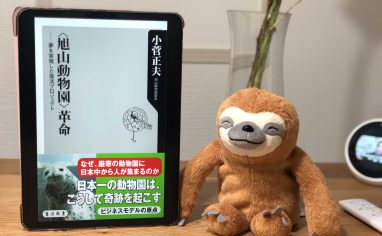「他者にとって自分が重要な存在と感じること」が幸福感にもたらす影響とは? ー18306名のメタ分析の結果ー
(本日のお話 2548字/読了時間3分)
■こんにちは。紀藤です。
昨日も引き続き「強みのワークショップ」の実施でした。
経験学習を回しまくっている今日この頃です。
また夜は13kmのランニングでした。
*
さて、本日のお話です。
先日、ハーバード・ビジネス・レビュー10月号を読んでいた際に、「マタリング」(=自分が職場で”重要”な存在だと感じること)がもたらす力を知りましょう、というテーマの記事がありました。(こちらの記事です↓)
>「自分は必要とされている」と感じられる職場をどうつくるか 従業員の自己肯定感を高めるマタリングの力 | ザック・マーキュリオ | ["2025年10"]月号|DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー
記事の中では、”心理学や社会学の分野で40年以上にわたって研究されてきた重要概念”と説明があり、「へー、そんな概念があるんだ⋯!」と知的好奇心をそそられて、論文を調べてみました。
そうしたところ、以下のような論文が見つかりました。それが「マタリングとウェルビーイングの関連に関するメタ分析研究」なるものです。
30件のマタリングとウェルビーイングに関する研究(N=18406)からどういった関係があるのかというのを見た内容で、規模的にも説得力があるように感じました。
⋯ということで、本日はその論文のご紹介をさせていただきます。それでは、どうぞ。
■今回の論文
タイトル:Feeling Important, Feeling Well. The Association Between Mattering and Well-being: A Meta-analysis Study(重要な存在だと感じること、健やかであること:マタリングとウェルビーイングの関連―メタアナリシス研究)
著者:Monica Paradisi / Amanda Nerini
ジャーナル:Journal of Happiness Studies, 2024
所属:University of Florence(フィレンツェ大学・イタリア)
■30秒でわかる要約
・マタリング(他者にとって自分が重要であるという感覚)がウェルビーイング(幸福感)とどのように関連するのかを、過去30件の研究(合計N=18,406名)を統合して分析したメタアナリシスです。
・結果、両者の間には中程度の有意な正の相関(r=0.41)が確認され、とりわけ「ユーダイモニア的ウェルビーイング(意味や目的のある幸福)」との関連はより強い(r=0.55)ことが示されました。
・この研究は、マタリングが「自己の価値」や「人生の目的意識」を高める心理的資源であることを明らかにしています。
■研究目的/背景
・1970年代以降、幸福やポジティブ機能に関する研究が進む中、従来の幸福論(快楽的・ユーダイモニア的)に対し、「社会的つながり」を含む新しい視点として注目されているのがマタリングです。
・マタリングは「他者にとって重要であり、価値ある存在であると感じる感覚」と定義され、自尊心、社会的適応、心理的健康との関連が報告されてきました。
・本研究では、異なる定義や文化的背景を超えて、マタリングとウェルビーイングの関連が一貫して存在するかを明らかにすることを目的としました。
■方法
・研究デザイン:PRISMAフレームワークに基づくシステマティックレビュー&メタアナリシス
・対象研究:マタリングとウェルビーイングの関係を実証的に調査した30件(39サンプル)
・サンプル総数:18,406名(主に大学生)
・測定尺度:
マタリング:General Mattering Scale, Mattering to Others Questionnaire
ウェルビーイング:Satisfaction with Life Scale, Psychological Well-being Scale, ICOPPEなど
・分析手法:無作為効果モデル(ランダムエフェクト)を用いたピアソン相関の統合分析(Jamovi使用)
■主な結果
◯全体効果量:r=0.41(95% CI:0.33–0.49)
→ マタリングが高い人ほどウェルビーイングも高い傾向。
◯概念別の関連性:
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・快楽的ウェルビーイング:r=0.38
(ポジティブな感情が多く、ネガティブな感情が少なく、人生全体に主観的な満足感や幸福感を得ている状態のこと)
・ユーダイモニア的ウェルビーイング:r=0.55(最も強い)
(自己の価値、人生の目的、真の自己の実現といった、より実存的で深い満足を指す)
・ホリスティック・ウェルビーイング:r=0.37
(対人関係、地域社会、職業、心理的、身体的、経済的といった人生のすべての領域における全体的な満足を指す)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◯モデレーター分析:年齢・性別・地域による有意な差は見られず、文化を超えて一貫した関連を示した。
◯研究の時期:2003年以降に発表された研究を対象に、特に2019〜2023年の研究が全体の3分の2を占めた。
■結論:研究からわかったこと
・マタリングは「自分が他者にとって重要な存在である」という社会的認知に基づく感覚であり、それが個人の幸福感を高める心理的基盤であることが示されました。
・特に「意味」「目的」「自己成長」などを中心としたユーダイモニア的幸福との関連が強く、「誰かの役に立っている」「自分の存在に意味がある」と感じることが、人生の充実感を支えることがわかりました。
■実践に活かすヒント
・職場での応用:
→メンバーが「自分は組織にとって重要だ」と実感できる仕組み(承認・貢献の可視化・感謝の循環)を整えることが、ウェルビーイング向上に直結します。
・教育現場での応用:
→教師が生徒に「あなたがいることでクラスが良くなっている」と伝えるフィードバックを行うことで、学習意欲や自己効力感の向上が期待できます。
■まとめと感想
これらの研究から、マタリングとウェルビーイングが関連していることはよくわかりました。
そしてふと思い出したのが、コーチングの「存在承認」というキーワードです。
承認には、結果を認める結果承認と、行動を認める行動承認、そして存在自体を認める「存在承認」があると。
マタリングはこのキーワードに類似しているようにも感じました。
存在承認は、挨拶をする、名前を呼ぶ、感謝をする、相手にとって大事なことを覚えている、などなどを意味します。
そうした小さなことは、些細なことのようですが「相手が重要な人物である=マタリング」に繋がる行動だと感じるのでした。
そして、冒頭にご紹介をしましたハーバード・ビジネス・レビュー10月号の記事では、
「マタリング・ツールキット」として、マタリングをしているかどうかをチェックするツールがあり、具体的で非常に使い勝手が良さそう⋯!と感じました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
※本日のメルマガは「note」にも、図表付きでより詳しく掲載しています。よろしければぜひご覧ください。
<noteの記事はこちら>