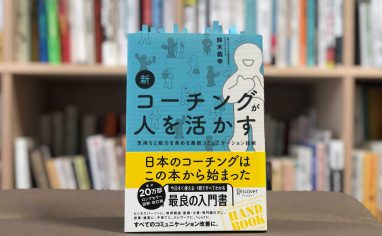チームの力を考える(8)~メンバー選びの法則/最小多様性の原理~
(本日のお話 2032字/読了時間3分)
■おはようございます。紀藤です。
昨日は3件の打ち合わせ。
夜はキックボクシングのジムでした。
*
さて本日も引き続き、
「チームの力を考える」をテーマに
お届けしてまいりたいと思います。
それでは早速参りましょう!
タイトルは、
【チームの力を考える(8)~メンバー選びの法則/最小多様性の原理~】
それでは、どうぞ。
■チームを作るときに
大切なポイントの1つが
「チームメンバーを
どのようにして選ぶのか」
ではないかと思います。
メンバー選びは、
とっても大事です。
■もちろん会社組織だと、
「そもそも会社から
チームが決められてます」
なんてパターンのほうが
多い気もしますが、
いずれにせよチームというのは、
「チームとして成果を挙げる」
ことが目的の中心として
あるかと思います。
ゆえに、繰り返しますが
”メンバー選びは
めちゃ大事”
です。
■では、仮に、
”あるプロジェクトを立ち上げる”
という状況において
メンバーを選ぶ際、
どのような観点で選べばよいのでしょうか?
このことについて
考えてみたいと思うのです。
■結論ですが、
『メンバーの「数」と「多様性」の
影響を考えること』
がポイントになります。
■まず、
「メンバーの数」による影響を
考えてみましょう。
少し単純化するために、
「個人(1人)VS 集団(複数)」
を比べてみたいと思います。
*
例えば「個人」。
(=メンバーの数が最も少ない)
<個人(1人)>
◯メリット
・スピードが早い
・責任が明確になりやすい
・より効率的である
◯デメリット
・創造性、正確性、質が低くなりがち
です。
もし1人だったら、
めちゃくちゃ効率的で
意思決定のスピードも早いでしょう。
でも、正確さや質、
創造性はたしかに低くなりそうです。
■一方、「集団」の場合はどうか。
(=メンバーの数が複数)
<集団(2人以上)>
◯メリット
・決定プロセスに異質性をもたらす
・多くの手法や選択肢の検討が可能になる
・多くの人に決定が受け入れられやすい
・創造的かつ正確で、質が高い
◯デメリット
・より多くの時間と資源を費やす
・同調圧力、社会的手抜き、フリーライダーなど
ネガティブな集団力学が働く可能性がある
(参考:スティーブン・P・ロビンス(2009)
『組織行動のマネジメント』ダイヤモンド社)
となります。
■「メンバーの数」ということで、
個人(1人) 対 集団(複数)
という観点で見てみましたが、
・メンバーが少ないと効率的
・メンバーが多くなると意思決定に時間がかかる
とか、
・メンバーが少ないと決定プロセスに偏りが出る
・メンバーが多いと、多様な人に受け入れられやすくなる
という影響は、
メンバー数が増減するほど
その影響は高まりそうです。
■つまり、
数が少ない or 多い、
どちらもそれぞれ
メリット・デメリットがあるわけです。
そんな中、
「チームの成果」を
生み出すためには、
”「スピード・効率性」と
「創造性・正確さ・質」が
最大化されるメンバー構成”
を「メンバー数と多様性」の観点から
選ぶこと。
このことを、
【最小多様性の原理】
といいます。
多様性は多いほうが望ましい、
しかし効率性も考えたいわけです。
■私も、実際に仕事で
「研修プログラム」を作成しますが、
まさに「メンバーの数と多様性」の
影響を感じます。
この半年で
・1人で研修プログラムを作成するとき
・3人で研修プログラムを作成するとき
・5人で研修プログラムを作成するとき
をそれぞれ体験しました。
やってみたそれぞれの感想は、
以下のイメージです。
ーーーーー
<1人で作る場合>
メリット:早くて効率的
デメリット:アイデアが広がらない、やや偏った内容になりがち
(そして孤独)
<3人で作る場合>
メリット:1人より圧倒的にクオリティが高い。比較的早い
デメリット:5人に比べるとプログラムにやや偏りが出る
<5人で作る場合>
メリット:研修のクオリティが高い。参加者に多く受け入れられた。
デメリット:時間がかかる。(1人の10倍はかかった)
ーーーーー
という印象です。
■仕事の場合、
「締切と工数」を考える必要が
ありますから
今の所のベストな答えは
(私にとっては)「3人」です。
自分と違った思考プロセスを持っている
信頼おける仲間と「3人」で一緒に作成する。
これが、
1)スピード&効率性がよく
2)創造性&正確さ&質
について、最も効率的かつクオリティが高い、
というのが(今のところの)答えです。
ゆえに、3人で作る、としていますが、
内容によって、より高い創造性や正確さを求めるのであれば、
3人より4人
4人より5人
のほうが時間はかかりますが、
望ましい、とも思っております。
■ということで、今日は
「チームメンバーを
どのようにして選ぶのか」
をテーマにお伝えいたしました。
結論、
チームメンバーの多寡によって、
・スピード・効率性
・創造性・正確さ・質
に影響があります。
これらが最大化されるための
【最小多様性の原理】
です。
最も早く、
最も創造性も高い。
そんなメンバー構成を
プロジェクトで実現したい成果を
加味しながら考慮すること。
ぜひ、チームづくりの
参考にしていただければと思います。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
==========================
<本日の名言>
まったく違う知識や考え方を持った人と、
まず対話できることこそ大事だ。
盛田昭夫(SONY創業者/1921-1999)
==========================