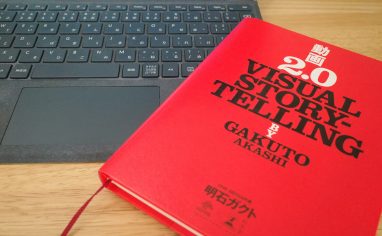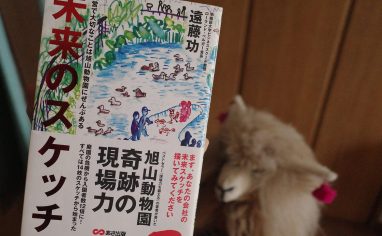「ルーティン」がもたらす3つの効果とは? ー進化理論としてのルーティンー
(本日のお話 2322字/読了時間3分)
■こんにちは、紀藤です。
昨日は、大学院のランニング部への参加。
10kmのランニングでした。
ランニングもペースを上げて、タイムを狙いたいと思う今日この頃。
周りの仲間達に刺激を受けています。
*
さて、本日のお話です。
本日も、大著書『世界標準の経営理論』の全章レビュー、引き続きお届けしてまいります。
本日は第16章「認知心理学ベースの進化理論」についてお伝えしていきます。
進化理論という言葉は、私は正直これまで耳にしたことがありませんでしたが、実は30年以上の歴史を持つもので、「組織はなぜ、どのように変化するのか」「組織を進化させ続けるために注意すべきことは何か」といった問いを解き明かす理論であるとされています。
そして、この理論で決定的な役割を果たすのが「ルーティン」という概念です。このルーティンに焦点を絞って解説が始まるのが、本章です。
新しい視点で「ルーティン」という言葉を咀嚼できた学びになる章でした。
ということで、さっそく中身を見てまいりましょう!
■ルーティンとは何か?
私たちの生活でも「ルーティンワーク」という言葉でよく知られていますが、ここで扱うルーティンの特徴は、以下の2点に集約されます。
――――
<ルーティンとは>
1.繰り返される行動パターン
2.状況の変化によって変わることもある行動パターン
――――
なお、進化理論におけるルーティンとは、個人の習慣ではなく、あくまで“組織集団”が繰り返す行動パターンを指すとのことです。
組織内にルーティン(標準化された手続き)が存在することで、認知負担が下がり、認識キャパシティに余力が生まれます。その結果、新たな学習が継続できるようになるのです。
▽▽▽
本章の中で印象的だったのが、企業の行動規範がルーティン化された事例として紹介されていた、米国の化学メーカー・デュポン社の話です。
同社では、「安全」が行動規範の第一義とされ、これが極めて高いレベルで徹底されています。いわく、まるで宗教のように「安全」が社内文化として根付いているそう。
その徹底ぶりは、たとえば全社員が、「タクシーの後部座席でも無意識にシートベルトを締める」「駅の階段では無意識に壁側の手すりを握る」といった行動として現れているそうです。たしかに、そこまでルーティン化されていたら、さぞかしパワフルだろうな…と思うのでした。
■ルーティンがもたらす3つの効果
このルーティンは、組織にさまざまなポジティブな効果をもたらします。2004年、マーカス・ベッカーが発表したレビュー論文では、次の3つの効果が示されています。
――――
<ルーティンがもたらす3つの効果>
(1)安定化
ルーティン化によって、メンバーの行動パターンが平準化され、将来の予測がしやすくなる。結果、組織に安定性がもたらされる。
(2)記憶
ルーティンは、組織に「知」を埋め込むメカニズムである。トランザクティブ・メモリー・システムやシェアド・メンタルモデルと並ぶ、組織の記憶の仕組みとして機能する。
(3)進化
ルーティンが充実している組織では、認知キャパシティに余裕が生まれ、サーチ行動が活性化される。その結果、新たな知を受け入れやすくなる。
――――
事例として紹介されていたのが、**良品計画の「進化するマニュアル」**という話です。マニュアルをつくるプロセス自体をルーティン化することで、暗黙の行動パターンが形式知として蓄積され、現場が継続的に進化・成長していくという取り組みです。
私も以前この話を聞いたことがありましたが、今回あらためてこの理論の観点から見ると、なるほど…!と腑に落ちました。
また、ルーティンには以下のような特徴があるとも述べられていました。
――――
・漸進的な変化(徐々にしか変わらない)
・経路依存性(進化の方向が過去に制約される)
・硬直化(何もしなければ柔軟性を失っていく)
――――
これも、良くわかりますね。個人でも同じだな、と感じます。
■ルーティンが硬直化するとき
ルーティンは有用である一方で、裏目に出ることもあります。
いわゆる「ルーティンワーク」等というと、ネガティブな意味合いを感じさせることもありますが、以下の3つの条件下では、ルーティンが「硬直化」しやすくなるとされています。
――――
<ルーティンが硬直化するとき>
1.繰り返し行動の頻度が極度に高いこと
2.行動パターンが一定のペースで長期間続くこと
3.時間的プレッシャーや外部ストレスがかかること
――――
変化の局面において、ルーティンがむしろ「足かせ」となってしまうこともあるというのは納得のポイントです。
たとえば、1990年代では、新聞社がデジタル新聞事業に乗り出した際、成功したのは8事業中たった1つのみだったそうです。
なぜかというと、既存の業務に組み込もうとすると、新しいルーティンが生まれにくく、経路依存性や硬直化といったルーティンの特徴がネガティブに働いてしまったそうです。
(ちなみに、その成功した唯一の事業体は「紙媒体とはまったく異なるルーティンをゼロから構築し直したこと」とのこと)
■まとめと感想
「ルーティンワーク」という言葉は、私たちの日常でも頻繁に使われていますが、その背後に「進化理論」という枠組みがあるとは知りませんでした。そして、そのルーティンの特徴をここまで明快に言語化されたことに、なんだかすっきり感を覚えました。
ちなみに、本章では「組織のルーティン」がテーマでしたが、私は個人にも同じことが言えると感じます。
私自身、ルーティンによって認知コストを下げ、より良い思考や探索に時間を使えるという恩恵を感じています(こうした毎日発信もそう)。一方、この日々の配信を4000日以上続けていますが、「変えたほうがいい」と思いながらも、習慣が強固になりすぎて、変化は難しくなっている面もあります。
あらためて、ルーティンとは進化のドライバーであると同時に、ブレーキにもなり得るということを考えさせられた章でした。
※本日のメルマガは「note」にも、図表付きでより詳しく掲載しています。よろしければぜひご覧ください。
<noteの記事はこちら>