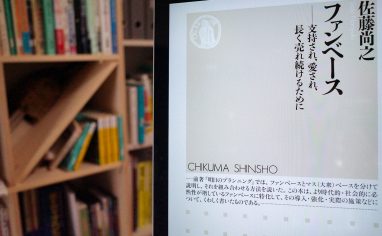AIとスピーチ原稿を一緒に書いたら、割といい感じになった話
(本日のお話 3622字/読了時間5分)
■こんにちは。紀藤です。
さて、最近はAIの活用が著しい今日この頃。
さまざまな分野の方と情報交換をするたびに「AIどんな風につかってます?」なんて日常的になっています。
ふと思えば、3ヶ月前には、大学の授業でも「AIは賢く使いましょう(でもあんまり過ぎてはダメよ)」だったのが、「AIは賢く使いましょう(この流れは止められないからガシガシ使いましょう)」みたいな空気に、なんだか変わったような気もしています。
今日は、そんな「生成AIの使い方」についてのお話です。
特に、個人的に多用している「AIにスピーチ原稿を書いてもらうといい感じになる」というお話を、共有してみたいと思います。
個人的な話も多分に含まれるお話ですが、もしよろしければお付き合いいただければ幸いです。
それでは、どうぞ!
■にょきにょき生まれる「生成AI」サービス
2024年の12月から、2週間に1度、「生成AIの活用講座」に参加をしています。
内容は、その道の第一線で、ありとあらゆる生成AIを使いまくっているプロが、日進月歩のさまざまな生成AIのサービスについて教えてくれて、細かいプロンプトや、その挙動、おすすめの使い方などを教えてくれるという講座です。
値段はなかなかしましたが、それでもAIエージェント元年の今、投資をする価値は十分にあり、また充分に元も取れていると感じます。
結果、「仕事はまずAIとコラボすること」は、半年を経て、すっかり習慣となりました。検索はperplexity、スライド作成はGamma、PPTデータを食べさせてまとめるのはGoogle NotebookLM,マインドマップならMapifyなどなど。
結局はChatGPT(有料版)の利用率が8割位で落ち着いているこの頃ですが、それでも生産性は爆上がりしています。
次にチャレンジするのは、「AIアプリ開発」ということで、自分専用のアプリを開発できる(らしい)ので、チャレンジしたい今日この頃です。
■意外と使える「AIに台本を書いてもらう」
さて、そんな中、「企業研修」という仕事をやる中で、地味に役立つのが「AIにスピーチの台本を書いてもらう」というものです。
私の場合、大学や研修等で話す機会があります。
ただ、私の悩みは「伝えたいことが多すぎて、まとまらない」というのに、いつも悩まされています。
一応メモで台本的なものを書くのですが、そうするとやたら時間がかかってしまったり、あるいは話しすぎて、脈絡なくなってしまうこともあったり、などなど。。。
そんなときに「生成AI(ChatGPT)」が、とても役に立つことに、ある時に気づきました。
方法としては、以下のような「プロジェクト」(自分用のGPTsを作れるような機能)を作っておきます。そして、あとはただ伝えたい目的や流れなどを、思いつくままに喋り倒すだけです。
――――
<研修台本整形プロンプト>
・このスレッドでは、KITOが研修やセミナーの「台本」を作成するための素材整形を行います。
・提示された原稿は、話し言葉ベースで記述されたものや、説明が冗長・重複している場合があります。以下の方針に従って、研修当日の話し言葉として自然に伝わる「台本文」に整形してください。
加えて、整形後の台本の冒頭には、「やや早口で読み上げた場合のおおよその所要時間(○分程度)」を明記してください。
整形の目的
・冗長な表現・重複表現を削除または簡潔にまとめる
・わかりづらい表現や論理の飛躍を補い、理解しやすくする
・聞き手が情報過多にならないように、構成を整理し、要点を絞る
文体の注意点
・KITOの語り口調を大切にし、話しかけるような自然なトーンを保つ
・形式張らず、親しみやすく落ち着いた口調
・一文が長くなりすぎないように調整し、間を意識したリズムを作る
出力形式
・台本としてそのまま読み上げられる文体で整形されたテキスト
・セクションごとに適度に区切りや見出しを入れてもOK
・冒頭に「やや早口で読み上げた場合の所要時間(○分程度)」を明記すること
――――
そうすると、やや違和感はあるものの、スピーチの骨格が重複なく整形されて、準備がぐっと楽になるのでした。
精神的な負担や時間的な効率を考えると、生産性が2倍くらい上がった感覚がするほどです。「プロジェクト機能」は本当にオススメです。
■AIと考えた「大学生に向けた5分の話」
ちなみに、大学生のリーダーシップの授業において、「なんでもよいので5分間、学生に話をする」という機会がありました(日直のように、毎週違う先生が話をしていくという企画です)。
一応多少なりとも役立ちそうで、かつ面白そうな話が良いと思い、AIと考えてみました。これまでの自分の経歴や、比較的ウケそうなネタから案を出してもらいました。
若干手直しをしていますが、こんな感じになりました。
――――
<5分スピーチ原稿案>
こんにちは、紀藤といいます。
大学の授業は2年目で、普段は企業研修などをやっているカレッジという会社の代表をしています。起業して8年目になります。
今日は、5分ですが、皆さんにひとつだけ、伝えたいことがあります。
それは、「コツコツやることの力」についてです。
まず、私の大学時代の話をさせてください。
私は愛知県出身で、北九州市立大学というは福岡の公立大学にいきました。先月久しぶりに大学の先輩に会ったのですが、当時の印象を聞いたら「入学当時、ザコキャラ”だったよね」といわれました(笑)
当時、同期がイケメンパラダイスみたいな人で、すごかったのです。
自分でもその格差を感じて,大学で華々しい生活を送りたくて,大学2年の時、バーテンダーのバイトを始めました。
ただ、当時は小倉はヤクザの街で日本で最も危険な地域だったことを知らず、働いてみると、やたらと暴力的な世界でした。
そこで、バーの店長(上司から)ボコボコになぐられて日、顎が折れるという事件がありました。(ワクワク働くどころじゃありません)
今思えばネタですが、当時は本当にどん底でした。
大学卒業後、新卒で飲食の仕事にも就きました。そこでも失敗ばかり。
アルバイトから社員いじめ的な扱いにあったと感じ、職場で孤立し、会社を逃亡してしまいました。自信はますますなくなって、「自分なんてダメなんだ」と思っていました。
でも、転機が訪れたのが、12年前でした。
悩んでいたある日セミナーにいったら、「変わりたいけど変われないのは、自己省察が足りないからだ」と言われた。つまり2度あることを何度も繰り返すから。改善されないからである、と。
それから、「毎日メルマガを書くこと」を決めました。「毎日学びを振り返りを書いてみよう」と思い立ち、日々の気づきや学びを発信するメルマガを始めてみました。そこから4000日以上、1日も欠かさず続けています。毎日2000-3000文字くらい書いて、今は12年目です。
なぜ書き続けられたのかは「やると上司や周りに宣言したから」。
見てもらうこと外圧をかけてやめづらくした。そうしたら面白いじゃんと、なって続けるパワーになった。
書くことで、毎日振り返るようになります。
ネタを探すようになるし、人の話をメモするようになる。
今日の出来事に意味を見出すようになる。
すると、日々の経験が、ただの“出来事”じゃなくて“教訓”になるんです。
不思議なことに、書き続けていたら、行動も変わっていきました。
そしてそこから、成果も信頼も、何より“自信”もついてきました。
そこから人の縁も広がって、今に至っていると感じます。
改めて、今日、皆さんにお伝えしたいのはこれです。
「書いて、発信して、積み重ねること」
日記でも、X(旧Twitter)でも、noteでもいい。
思ったことを“残す”ことで、経験を穴の空いたバケツにせず、経験を蓄積できます。人生は長距離走。10年後、それは大きな財産になります。
僕の好きな言葉に、こんなものがあります。
「人は1年でできることを過大評価し、10年でできることを過小評価する」
だからこそ、今の自分の行動が、未来の自分へのプレゼントになると思って、ぜひ、自分にできる“小さな習慣”を始めてみてください。
ぜひ皆さんも,書いて振り返る,やってみてください。
そして発信することもぜひやってみてください。
――――
■まとめ:気持ち的にラクになるのが大事
上記はこれまでも話をしてきたことなので、別になくても話せるものです。
ただし、こうしたスクリプトがあることで、気持ち的楽になる、というのがポイントです。
こうして認知コストを減らし、そして新しい部分に、余った認知資源を振り分けていく。そんな使い方をもっともっとできれば、より快適に働けるのだろうな、そんなことを感じた次第です。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました!
※本日のメルマガは「note」にも、図表付きでより詳しく掲載しています。よろしければぜひご覧ください。
<noteの記事はこちら>