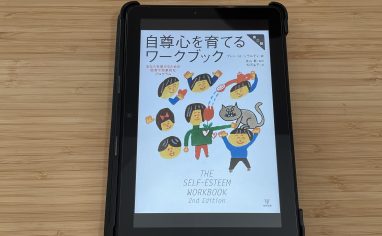発表会の魔物に食べられた日 ー「完全崩壊したカンパネラ」が教えてくれたことー
(本日のお話 4678字/読了時間6分)
■こんにちは。紀藤です。
昨晩、ピアノの発表会がありました。
曲目は、「ラ・カンパネラ」。
自分にとって、超ストレッチな曲です。
決してふんだんにあるわけではない時間を捻出しながら、
毎日1~2時間、練習してきました。
おそらく、人生で最もピアノを練習した1年間でした。
・・・そして迎えた発表会。
結果は、「曲が途中で完全に止まり、崩壊した」のでした。
最も練習をしたピアノの発表会。
そして最も失敗したピアノの発表会。
今しか感じられないであろう、素直な想いを言葉にしてみたいと思います。
長文となり恐縮ですが、よろしければお付き合い頂ければ幸いです。
■「カンパネラを弾く」と決めた日
「ラ・カンパネラ」という曲に、興味を持ったのは、フジコ・ヘミングさんの演奏を聴いたときに、凄まじい迫力に感動したことでした。
2年前、どんな感じだろう?と思って、楽譜を買いました。
そしてちょっと弾いてみました。
すると、最初から”跳躍”の連続で、全く歯がたちませんでした。
そのときは、「ムリだ」と諦めました。
代わりに同じ作曲家の、リストの「愛の夢」を去年チャレンジしました。
そこにも“跳躍”の技術が含まれており、そこで少しだけスキルアップし、昨年の4月、「発表会でラ・カンパネラを弾く」と決めました。
そこから、毎日の練習が始まりました。
たった5分の曲を練習するために費やした時間は、500時間以上。
フルマラソンに出場した日も、フルマラソン後に2時間練習を挟み、
リモートワークのランチタイムに15分だけ、など練習時間を蓄積してきました。
自分で決めたはずなのに「なんでこんなに練習してるんだろう?」
と思うことも、少なくありませんでした。
■255回の録音と、一音一音の思い出
ちなみに私は楽譜を読むのは遅く、基礎技術も弱いです。
大人のピアノだから、仕方ないのかもしれません。
なので移動中に楽譜をスマフォで見てイメトレをする。
ランニングしながら音源を聴いて、曲の流れをイメージするなど、
自分なりに工夫をしてきました。
この2ヶ月では、自分の演奏を録音→聴く→修正するを繰り返し、
録音した数は255回になりました。
たった一小節の、
一音から一音への跳躍を、
何回繰り返したのだろうか。
そんな1年、500時間を、5分に集約させるというのは、
自分にとっては、指がふるえるくらいには、緊張することでした。
■ついにやって来た演奏のとき
発表会の当日。
私の演奏の場面は夜20時。
朝から続く小学生・中学生、高校生とあがっていき、最後が大人の部です。
私の直前には、高1の子が「英雄ポロネーズ」や「黒鍵のエチュード」などの難曲をミスなく素晴らしい演奏を披露していました。
それをみて、心に雲がかかるのを感じました。
比べるものではない、と言い聞かせながらも、
その完成度の違いと自らを比較して、不安が募ります。
朝から大学の授業、その後ピアノスタジオで練習し、オンラインでのミーティングと1日仕事をした上での、ピアノの発表会。
今回は、生まれて初めて、友人が観客としてきてくれました。
大学院や勉強会の仲間でピアノやオーケストラをやっている友人らが3名。
そして妻と息子の合計5名が、観客です。
こんなにも多くの方が聴きに来るというのは、人生で初めての体験です。
気負ったつもりはなくても、意識はしていました。
■最初の鐘を鳴らす
舞台袖で「第9部1番 キトウヤスユキ ラ・カンパネラ」と呼ばれます。
ピアノの前に歩みを進めます。
そこには、イタリアの素晴らしいピアノ「ファツィオリ」がありました。
椅子に座って、何度かポジションを確かめます。
そして、鍵盤に手をおいて、最初の音を慣らしました。
カンパネラ=鐘のように、ポーンとオクターブの連打から始まります。
予想よりも、鍵盤に質量を感じました。
「音を聴いて、丁寧に」と言い聞かせつつ、曲を進めていきます。
最初の”跳躍”は、完璧ではないけれど、少しのミスタッチで進められた。
ちょっとだけ安心しつつ、曲を進めていきました。
■「幽体離脱」が始まる
その中で、どこかで「いま・ここ」のピアノに集中できてない自分を感じ始めました。
弾いている自分と、何かを考えている自分が、幽体離脱をするように、少しずつ乖離していく感覚。
演奏の2分半たったところで、普段では絶対に間違えない場所を、完全に外しました。
その瞬間、弾いている自分の身体から、音を聴き、演奏している自分が、「うしろの百太郎」の霊魂ばりに、スッと離れることを感じました。
なんとか、自分の身体に、離れてしまった自分を戻そうとする。
でも、そうしようとしている自分に気付いても、もうどうしようもない。
弾いている自分、聴いている自分、考えている自分。
3つの自分が分離して、弾いている自分の輪郭がぼやけるように感じる。
そこから一音一音に意志が伝わらなくなり、ミスが目立つ。
ただ、身体が覚えるままにただ指が動いていることを感じていました。
でも、もう止められない。
■完全なる「崩壊」と「沈黙」
そして、最後に起承転結の「結」にあたるパートで、一気に盛り上がるところに差し掛かります。
ダメだ、指が回らない。。。
ミスしかない。
なのに焦ってペースが上がっていく。
まるで脚力が鍛えられていないランナーが、
下り坂の勢いにのまれまま全力疾走して、
足がもつれるような音の羅列が続きました。
そして、完全に、転倒をしました。
いつもは、間違えない場所。
自分が何の音を弾いているか、
全くわからなくなり、曲がとまりました。
直前まで響いていた盛り上がりの真っ最中で、
ホールに「沈黙」が訪れます。
・・・
・・・
・・・
途中から再開しようと、鍵盤を鳴らす。
・・・違う。
別の鍵盤を鳴らす。
・・・これも、違う。
どの音から始めればよいのか、わからない。
5秒か、6秒か。
体感ではもっと長い時間が流れていました。
この時点で「音楽としての演奏は失敗」であることは、
誰の目にも明らかでした。
■舞台の上からは、逃げられない
舞台袖にいる、楽譜をもっている先生を
分離した意識の自分が振り返ろうとするのを、感じました。
でも、ピアノの前からは逃げられない。
自力でゴールテープを目指すしかない。
そう思ったとき、ここからしか始められない、というところまで、
一気に戻すことに決めました。
終わりかけた曲を、約3ページ巻き戻す。
繰り返し練習していた「結」の頭でした。
相撲で言えば、完全に土俵外に突き落とされて、勝負は敗れている。
なのにもう一度、土俵に這い上がって相撲を始めるイメージです。
「リカバリした」とはいえません。
「最後まで諦めなかった」も違う。
心はほとんど、折れていました。
でも、折れた足に支え木をして、ガタガタになっている歩みで、
汗や鼻水を垂らしながら、なんとかゴールテープを目指そうとしました。
そこからは、記憶はありません。
ただ、最後の小節の和音を、鳴らすことはできました。
弾き終わって、お辞儀をするときに、
観客で来てくれていた友人たちの顔を、見ることはできませんでした。
「やっちまいましたー、てへぺろ」みたいに誤魔化しそうな自分を感じ、
同時に「そんなことが浮かぶような心持ちだからこんな演奏になったのだ」という自責の念を覚えました。
舞台袖に退散しながら、袖で見守ってくれている先生たちのいくつもの目がありました。あたたかい受容の中に、あわれみをたたえているようにみえました。それが、自分の心臓のあたりの削り取った気がしました。
■発表会には「魔物」がいる
1年間、レッスンに付き合ってくれた先生にも、申し訳ないと思いました。
先生は、普段は企業で働いている方です。
そして、副業でレッスンをしてくれています。
忙しい仕事終わりや、お休みの日にレッスンに付き合ってくれていました。
そんな成果が、ひどい演奏をしてしまったという無念の思いもありました。先生に、無意識に「すみませんでした」と謝ります。
先生は言います。
「発表会には、魔物がいるんですよね」
「普段、絶対間違えないところで間違えたり。
緊張にのまれてわからなくなったり」
「これまでの発表会が順調だったから、
今回こうした経験が初めてだったと思います。
でも、それがまた成長に繋がりますよ。きっと」
そして、冷静なフィードバックもくれます。
「やっぱり、途中で集中力が切れたところから、
練習で不安要素だったところが、すべてミスとして出ていました」
「練習でできないことが、本番で急にできることはない」
「練習量としては、足りないとは思いません。
でも、細かい部分を丁寧に、確実なものにするというところで、
伸びしろがあったかもしれません」
結局、量はやっているつもりでも、練習の「質」が不足していた。
練習における「瞬間瞬間の集中力と覚悟」が足りていなかった、
漫然と弾いていた、ということなのでしょう。
だから、この崩壊も、失敗も、
すべて実力通りだった、ということです。
残念ですが、認めるしかありません。
自分は未熟で、へたくそな、ピアノを弾く人なのでした。
■「完全なる崩壊」の果てに、何が残ったのか
結論、「音楽の発表会」としては、完全なる崩壊・失敗です。
観に来てくれていた友人らと終わった後に「慰労会」のような食事会をし、豊洲シビックホールの会場を背に、自宅へ向かいました。
友人と別れ、一人になった瞬間に、よそいきの仮面がとれると、
急に足が重くなりました。
トボトボと歩きながら、自らの力の無さを露呈した内容に
やるせなさが色濃くなり、ピアノってなんだろう、と思いました。
はたして、この1年間の500時間超の旅路は、一体何だったのか…。
本業をもっと頑張るとか、あったのでは?
誰かに貢献する、社会に尽くすという時間の使い方もあったのでは?
英語とかプログラミングでも勉強したほうが、よっぽど有用だったのでは?
・・・そんなことが頭をよぎります。
そうしたとき、メッセンジャーの通知がきました。
観客として聴きに来てくれた、同じく管楽器の演奏者である仲間から。
「演奏の場と音楽に、最後まで責任を持ったこと。
その姿を、お子さんが目撃したことがとても重要だと思います」
ピアノ先生は演奏後、こうも言っていました。
「演奏が止まったとき、楽譜を持って行こうかと迷いました。でも、紀藤さんはきっと最後までやるだろうと信じて、いきませんでした」
妻も「よく最後まで逃げなかったね」と、
別の友人は「紀藤さんの生き様に触れた気がしました」と言いました。
もし、この旅路に意味があるとするならば、
自分を見守ってくれた人、妻、理解しているかわからない4歳の息子、
また観に来てくれた仲間に、こんな状態になっても、もがいた姿勢を、
記憶のかけらとして残せたかもしれないこと、なのかもしれません。
心を震わせる「音」を届けることはできませんでした。
ただ、何かを感じてもらう「物語」を届けることは、
言葉を額面通りに素直に受け取るならば、できたのかもしれません。
■「音に感動した」と言ってもらえる日を夢見て
本音では、「音楽として感動した」と言わせたかったです。
しかし、それは全く叶いませんでした。
「逃げない姿勢」ではなく、
磨いてきた音の裏にある、深い何かに感動してもらえるような、
そんなものを届けたいと思っていました。
でも、いつか、練習を積み重ねて、
5年後なのか、10年後なのか、
少しでも「音楽」として感動させられるような弾き手にはなりたい。
そう振り返りの旅路を言葉にすることで、今は思いつつあります。
これからどうするかは、しばらくおいておきます。
1年間、カンパネラしか弾かなかったことから離れて、
ピアノを鳴らして、好きになれるように、触れてみたいと思っています。
そんな意味で、あらゆる楽器に向き合う人に、
心からの尊敬と、敬意を覚えている次第です。
長文、最後までお読みくださり、ありがとうございました!
※本日のメルマガは「note」にも、図表付きでより詳しく掲載しています。よろしければぜひご覧ください。
<noteの記事はこちら>