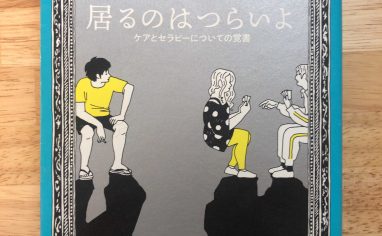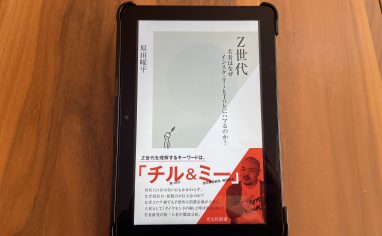世界的に超有名な”知の創造理論「SECIモデル」”を徹底解説します!
(本日のお話 2754字/読了時間4分)
■こんにちは、紀藤です。
昨日は終日、ストレングス・ファインダー研修のDAY2の実施でした。
実際に、「強み」をメンバーとの対話や、チームビルディングにどのように活かすのかを、
様々な理論を紐づけながら実践いただく時間でした。
皆さまのアウトプットを聞きながら、私も大変刺激になるとともに、
ぜひ現場で活用いただきたいと改めて強く思った次第です。
ご参加いただきました皆さま、ありがとうございました!
*
さて、本日のお話です。
本日も、大著『世界標準の経営理論』の全章レビュー、引き続きお届けしてまいります。
本日は第15章「組織の知識創造理論(SECIモデル)」のご紹介です。
このSECIモデルは知の創造プロセスを体系的に描ききった理論として紹介されており、とくに著者はこの章の最後に、この理論と、これを30年前に生み出した野中郁次郎氏に対して「最高の敬意と畏怖と戦慄を覚える」とさえ述べています。
読んでいても、他の章に比べて著者の興奮と熱量が伝わってくるような筆致で、このモデルの経営学における影響力の大きさを感じずにはいられませんでした。
ということで、早速中身を見てまいりましょう!
■SECIモデルとは何か?
SECIモデルは、「組織はどうすれば新しい知を見出せるのか?」そして「そのメカニズムは何か?」という問いに対して、明確なプロセスを提示している唯一の理論であると紹介されています。
そしてそれは今、ビジネスの世界で話題となっているイノベーション、デザイン思考、そしてAIとの付き合い方に大きな影響を与え、むしろAIには決して代替できない、これからの時代にこそ重要な理論として位置づけられています。
このSECIモデルは『知識創造企業』という書籍を通じて世界的ベストセラーとなりました。ただ、学術界においてより重視されるのは1994年の論文「組織の知識創造に関する動的理論」であり、現在Google Scholarの引用数は24,000件超という圧倒的な影響力を誇っています。
この理論で重要なのが「情報」と「知識」の違いについてです。情報とは言語や目に見える記号であり、知識とはより深く、言葉にできないものも含むという理解が、この理論誕生の背景にあるようです。
では、SECIモデルのキーワードや具体的なプロセスをより詳しく見ていきたいと思います。
■形式知と暗黙知
まず本モデルの大事なキーワードが「形式知」と「暗黙知」です。
「形式知」とは「言語化・記号化された知」のことです。我々が話す言葉、書籍や文書、数式、図表、プログラミング言語など、すべて形式知にあたります。
それに対して、「暗黙知」とは「言語・文章・記号で表現が難しい、主観的・身体的な経験知」のことです。そして、SECIモデルの中心的なキーワードの一つがこの暗黙知なのですが、大きく2種類に分けられるとします。
――――
◯暗黙知1「経験の反復により身体に体化された知」
例:ピアノ熟達者が感覚でわかる音の違いや質感など。
◯暗黙知2「個人に体化された認知スキル」
例:M&Aディールで修羅場をくぐった経験者が「これは危険だ」と感じ取る直感。人の信念もこの認知的な暗黙知に含まれることが多いです。
――――
重要なのは、言葉にできない暗黙知の方が実は豊かであり、それをどう形式知に変換していくかが知識創造の核心だという点です。
そのためには、形式知と暗黙知を持つ「人格」が全体でぶつかり合い、ときに融合する必要があります。これが後述する4つのプロセスに組み込まれています。
■SECIモデルの4つのプロセス
個人同士が全人格でぶつかり合い、組織の知識創造プロセスを動的に進めるーーこれを示すのがSECIモデルの4つのプロセスです。それぞれが「SECI」の頭文字のアルファベットを意味します。一つずつ見ていきましょう。
――――
(1)共同化(Socialization): 暗黙知 → 暗黙知
――――
他者との直接的な共感や環境との相互作用を通じて暗黙知を獲得することです。例えば以下のようなものがあります。
◯身体を使った共同体験
例:熟練職人が若手に技術を伝える際、自分の身体の動きを見せる。接客業で先輩の動きを真似る。いわゆる「背中を見て覚える」。
◯共感と対話
それぞれの心情・信念・思考・直感を共有するためには徹底的な1対1の対話が必要。この深い対話を「知的コンバット」と呼びます。理屈だけでは共有できないレベルの共感を超えた交流を指します。
――――
(2)表出化(Externalization):暗黙知 → 形式知
――――
暗黙知を対話・施策・メタファーなどを通じて概念や仮説に変換し、集団の形式知にすることです。例えば以下のようなものがあります。
◯比喩・アナロジー
暗黙知は言語化が難しいため、まずは近い例えでイメージ共有を行います。
(例:経営者の永守氏の「千切り経営」など)
◯アブダクション(仮説化)
「これは〇〇が原因では?」と気づくひらめき・仮説化のプロセス。
◯デザイン思考
暗黙知を図や絵に可視化する取り組みのことも含みます。
――――
(3)連結(Combination):形式知 → 形式知
――――
集団レベルの形式知を組み合わせ、物語や理論に体系化することです。
マニュアル・設計書・計画書など、現場で活用できる体系化された形式知としてまとめ上げる理論もこれに当たります。
他にも、「ナラティブ(物語る)」ことでまだ具現化していない未来の構想(例:会社の方向性)を、物語の形で描くことも、こちらに当たります。
――――
(4)内面化(Internalization) 形式知 → 暗黙知
――――
形式知を実践し、新たな価値を生み出すとともに、暗黙知として個人・組織レベルに体得することです。
形式化された知識を実行→反復→暗黙知化というサイクルで繰り返し、組織は知識を生み出し続けることができます。
■まとめと感想
章の締めくくりでは、「SECIモデルで描かれるプロセスは、ほぼすべてAIには実現できない領域であり、それゆえにこれからの時代こそ重要性が高まる」と強く主張されていました。
――――
・AIは暗黙知を持たない
・AIは身体知や共感を持てない
・AIはナラティブを文脈に応じて柔軟に語れない
・AIは現場に行って事実を知覚できない
――――
このような理由から、人が持つ暗黙知を形式知化するSECIモデルの価値は今後さらに高まるだろうと結ばれていました。
私自身も、たとえばピアノ練習の中で、技術的な細かい違いを感覚的に捉えることがあり、それはなかなか言葉にしづらいものです。
先生はさまざまな方法で言語化して教えてくれますが、それでも理解しきれない領域がたくさんあります…。こうした感覚のぶつかり合い(知的コンバット)を通じて形式知に変換していくプロセスは、まさに人間ならではのようにも感じました。
また、章内では、このSECIモデル(知的コンバット的な考え方)は現象学(フッサール)における「自分と相手主体を同一化する」考え方に近いとも語られており、なるほどー!と思いました。
デカルト的な二元論では相手を観察対象としますが、それとは違う、現象学的な自他一体の関係性は、もしかすると日本人の感覚にもフィットするものなのかな…そんなことを感じた次第です。
■まとめと感想
SECIモデルの本質は、言語化しづらい暗黙知の価値を見直し、それを組織全体の知へと転換していく「知の動的な創造プロセス」にあります。
このプロセスがAI時代においてもなお、人間ならではの強みであり続けるーーそんな視点が非常に印象に残りました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
※本日のメルマガは「note」にも、図表付きでより詳しく掲載しています。よろしければぜひご覧ください。
<noteの記事はこちら>