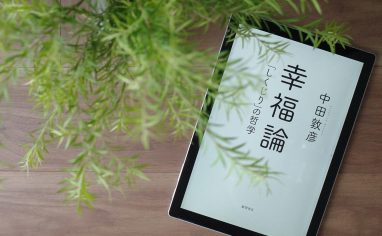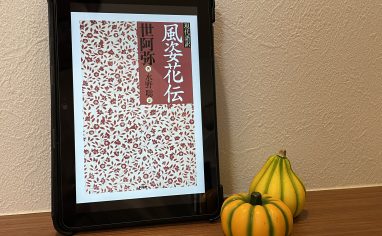今週の一冊『水中の哲学者たち』
(本日のお話 2478字/読了時間4分)
■こんにちは。紀藤です。
毎週日曜日は、最近読んだ本の中から1冊をご紹介する「今週の一冊」のコーナーです。本日はこちらの著書です。
─────────────────────────────
『水中の哲学者たち』
永井玲衣 (著)
─────────────────────────────
本書は、「哲学」という縁遠そうなものを、日常のエッセイのような形で、美しく柔らかい文体で問いかけてくれる著書です。
知人のブログで「描かれている文体がすばらしい」と評価されていたのを見て、なんとなく気になって手に取ってみましたが、とても面白かったです。
そしてこういう表現ができることに、憧れる一冊でもありました。
以下、本の内容と、感じたことについて書いてみたいと思います。
それでは、どうぞ!
■哲学とは「驚異と懐疑と喪失」である
最近では、山口修さんの書籍を通じて哲学に触れたり、以前には日本アスペン研究所で、いくつかの古典原典を部分的にではありますが読んでみたりと、断片的に学んできました。
その中でも、本書はとても優しく、日常的で、哲学をとても身近に感じられるような内容でした。哲学とは「前提を疑うこと」だと言われます。本書の中では、こんなふうに語られていました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
哲学は意外とシンプルである。哲学とは、「なんで? と問うこと」だからだ。だから、学問というよりは、行為や営みと表現したほうがいいかもしれない。
哲学することの根源は「驚異と懐疑と喪失の意識」であると言った。ひとは、びっくりしたりつらいことがあったりすると、「なんで?」と自然に問うてしまう。要するに、「は?(驚異)マジで?(懐疑)つら(喪失)」から哲学は始まるのだ。そうなると、わたしたちは、わりと簡単に哲学できるかもしれない。
(P108)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
当たり前だと思っていることに、ふと疑問を投げかけてみます。
なぜ働くのか。なぜ生きるのか。なぜ学ぶのか。
なぜお年寄りに席を譲るのか。
たとえば、なぜ私たちは満員電車に乗って通勤するのか。
同じ1つの問いでも、それに対して、異なる前提を持った人が対話を重ねる。こうした営みを「哲学対話」と呼び、本書の中では、小学生、社会人さまざまなケースでの哲学対話での場面も紹介されていました。
■対話をすると「がっしゃん」と音がする
また哲学とは「前提を疑うこと」ともいわれますが、本書の冒頭で、象徴的なこんな表現が紹介されていました。以下、引用いたします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
考えごとをしていると、いろいろな音が聞こえてくる。(中略)
とりわけ、がっしゃん、と何かが壊れるような音はよく聞こえてくる。繊細なガラスが割れる音というよりは、重い陶器が砕けるような音だ。
誰かが自分の考えを話している。がっしゃん、と音がする。何の音だろう、とわたしは不思議に思う。別の誰かが考えを話し始める。またがっしゃん、と音がする。
後ろを振り返るが、特に何かが落ちているわけではない。わたしの頭の中だけで鳴っている音なのだ。
目の前のひとが「永井さんは、さっきなんでああ言ったんですか」と不意に問いを投げかけてくる。どきどきしながら、何とか先ほど自分が言った考えについて説明する。目の前のひとは、うなずいてみせたあと「さらに質問したいんですけど」とわたしに言う。がっしゃん、と音がする。
(P29)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この「がっしゃん」というのが、まさに自分自身の前提が壊れる音なのでしょう。
逆に、前提を疑わずに、「これが正しい」「あれは間違っている」と、あるひとつの”合理性”とか”社会通念としての当たり前”を前提として物事を進めるのは、ある意味でとてもシンプルです。
たとえば、何かのプロジェクトで、限られた時間の中で、目的に向かってWBSを作り計画を立て、必要な情報を集め、合理的に組み立てていくとしたときます。
それはそれでとても効率的でわかりやすいです。
けれども、その“最短距離”に進む前に、「そもそもこの議題でよかったんだっけ?」「なぜこの取り組みをしたいんだろう?」と問い直し、それぞれの前提や価値観、なぜそう考えるのかといった背景を語り合おうとすると、一気にめちゃくちゃ時間がかかるようになります。
その人がどんな世界の見方をしているのか、どんな人生を歩んできたのか、何を大切にしているのか——そうしたことを理解し合うには、時間もエネルギーも必要です。
力技で「こうすべきだ」と言い切った方が、ずっとシンプルで楽かもしれません。有無を言わさぬ「論理思考」で突き進むほうが、早いでしょう。でも、本当にそれでいいのか、何か大切なものを横目に見ながら進んでいる感覚もするものです。
その、視界の端に写っている「違っている前提」を丁寧に摺り合わせるのが対話であり、そしてそれはとても難しいことなのでしょう。
■「自分が変わること」を恐れない
本書の中で、著者が印象的だったという一言に、ある哲学の先生が、哲学対話の際に
ーーーーーーーーー
「どうか変わることを忘れないでください」
ーーーーーーーーー
と語ったというエピソードがありました。
そして、この言葉は、私も印象に残ることばでした。
というのも、人は「変わらない」ことで自分を保とうとしているのでは、と思うフシがあるからです。
何かしら「自分とはこういう人間だ」という形を定義し、それに従って生きる方が、実は楽なこともあります。
たとえば、私のことを考えてもそうです。「ウルトラマラソンを走る」「毎日noteを更新している」「強みについて探求している」。
そうした色々な活動を行うのが自身のアイデンティティの一部であり、自信になっている一方、逆から見ればそうした自分像に過度にこだわることで、自分を保っているとも言えるかもしれません。
逆にいえば、「毎日noteを更新する」という行為を手放してしまったら、「自分とは何か」が分からなくなってしまう。そんな不安があることも、否めません。
“強い”のか、“しなやか”なのか、“ありのまま”なのか、うまく言葉にできませんが、自分を持っている人とは、もしかしたら「自分を持っていない人」なのかもしれません。そして、変わることを恐れない人なのでしょう。
そして何より、著者の綴る柔らかい文章。
情景や心の動きがふんわりと立ち上ってくるような文体に、こんなふうに、心を表現できたら素敵だなと感銘を受けた次第です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
※本日のメルマガは「note」にも、図表付きでより詳しく掲載しています。よろしければぜひご覧ください。
<noteの記事はこちら>