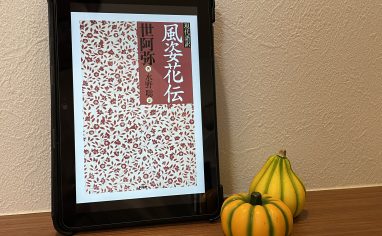今週の一冊『「好き」を言語化する技術』
(本日のお話 3259字/読了時間3分)
■こんにちは。紀藤です。
さて、引き続きドイツのベルリンに来ております。
特に予定を決めているわけでもなかったので
24kmランニングをしながら、ベルリンの壁跡や、博物館を巡っていました。
ほぼすべてカードでなんとかなるので、スマフォと充電器さえあれば、
全然問題ないので、自分にあった楽しみ方だな、としみじみ思った次第。
*
さて、本日のお話です。
毎週日曜日は最近読んだ本からオススメの1冊をご紹介する「今週の1冊」のコーナーです。
今週の1冊はこちらです。
==============================
『「好き」を言語化する技術 推しの素晴らしさを語りたいのに「やばい!」しかでてこない 』
三宅香帆 (著) /ディスカヴァー携書
==============================
2025年最も売れた新書と帯に書かれていますが、今注目を集めている三宅香帆さんの著書です。
『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』という三宅さんの著書がすこぶる面白く、また勉強にもなり、一気にファンになってしまいました。こちらの本も面白いと評判を耳にしており、手にとってみたのでした。
感想として思ったのが、「自分の感覚を大事にすることの大切さ」とその方法を力強く言葉にしてくれているように思いました。
ということで、早速中身を見て参りましょう!
■本書の概要
本書は、自分の好きなことを伝えたいけれど、なかなか言葉にできないーーそのもどかしさをひもとき、伝えることの大切さとその技術について言及している一冊です。
誰もが自分の好きなことをわかってもらいたい、伝えたいと思うものの、うまく言葉にできず飲み込んでしまう。そして心の奥にしまい込んだまま、本当に好きだった理由さえわからなくなってしまう。そんな思いを抱える人は少なくないと思われます。そんな、「好きを上手に表現したい、伝えたい」という思いと悩みを持つ方に届く本となっています。
本書の特徴について、以下のように紹介されています。以下引用いたします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
本書は、アイドルと宝塚をこよなく愛する著者が、書評家として長年培ってきた文章技術を「推し語り」に役立つようにまとめた1冊です。
SNS発信・ブログ・ファンレター・友人とのおしゃべり・音声配信などの発信方法ごとに、自分だけの言葉で感想を伝える技術を教えます。
推し語りには、語彙力や文章力が必要だと思われがちですが、それは間違いです。
必要なのは、自分の感想を言葉にする「ちょっとしたコツ」だけ。
そのコツさえ知れば、あなただけの言葉で好きな作品の素晴らしさを語れるようになります。
ここでは特別に、少しだけそのコツをお教えします!
コツ1 自分の感情を一番大切にする
コツ2 妄想をこねくり回して、感想を生みだす
コツ3 よかったところを細分化するだけで、あなただけの言葉になる
これって一体、どういうことなんでしょう…?
本書を読めば、特別な才能や技術がなくても、あなたの感動を自分の言葉で語れるようになります。
※Amazon本の紹介より
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
■「あなたの感性を大切にしてください」
本書を読みながら、私が一番感じた著者からのメッセージは「あなた自身の中にある感性――好きと思ったり、嫌だと思ったりすることを、他人と比べず大切にしてください」ということでした。
人は誰かが「好き」と言っていると影響されたり、誰かの感想を見ると左右されやすかったりします。人は、社会の中で生き、社会で編み上げられた意味の中で生きる動物なので、他者から影響に抗うのは難しいもの。
特に現代、SNSで他者の意見に触れる機会が多く、自分が何かを感じて言葉にする前に、他人の意見に飲み込まれてしまうことが多い気がします。すると、そもそも自分がピュアにどう感じていたのかわからなくなってしまう。
自分の中に芽生えた感覚を大切にできないこと。それは「自分を大事にできていない」と感じることにつながります。
その中で、誰でもない自分の「好き」を言葉にすることは、自分の中の感性という聖域を守ろうとする行為のように感じました。以下、本書から引用させていただきます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・「好き」は一時的な儚い感情である。そんな前提を内包しているんですね。それは悲しいことでも何でもなくてそういうものなんです。
・「好き」を言葉にして残しておけば、その感情は自分の中に残り続けます。今はもう好きじゃなくても、いつの間にか自分の一部になっていた好きな感情が保存されている。それって意外と大切なことじゃないでしょうか。
・自分の「好き」を言葉で保存しておく。すると、好きな言葉が固まっていく。その気づきは、丸ごと自分の価値観や人生になっているはずです。
自分の力を信頼できる事は、自分の価値観を信頼することにつながります。だって好きなもので自分は出来上がっているのだから。 (P47)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
■個人的に印象に残った話
以下、本書の中から、個人的に印象に残ったお話を、3つほど紹介させていただきます。
◎その(1):「泣ける、やばい、考えさせられる」はNGワード
クリシェ(=フランス語で「ありきたりの言葉」の意味だそう)として「泣ける、やばい、考えさせられる」は使わない方がいいとのこと。
こういう言葉を使った瞬間に、思考停止になってしまいますし、本当は感じたはずの細やかな感性を、超大味な塩か砂糖のみ!みたいな味で集結させてしまうきらいがあります。これはもったいない。ゆえに、こうした単純化したキーワードは、好きを言語化する上でNGとのことでした。納得ですね。
また、好きを言語化するまでは、他者の評価は見ないほうがいい、ともありました。それは上述のように、「他者の評価に影響を受けてしまうから」です。
たしかに私も、映画を見るときレビューを先に見て「評価が高そうだから見る」ということをしがちです。そうすると自分の感覚より他人の評価を先に前提にしてしまい、その評価に影響を受けている自分もいると感じました。もちろん限られた時間をどの作品に投資するかの判断には役立ちますが、それだけに支配されるのはもったいないと感じました。
◎その(2):感情を言語化する王道プロセス
感情を言語化するプロセスも紹介されています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◯ポジティブな感情の場合
・それは共感なのか、驚きなのかを考える
・共感なら自分の体験や好きなものとの共通点を探す
・驚きならどこが新しいと感じたのかを考える
◯ネガティブな感情の場合
・退屈さや不快を感じた理由を、自分の体験との共通点から探す
・ありきたりに思ったときも「どこがそう感じたのか」を言葉にする
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
こうした細分化が、自分の感情を他人ではなく自分自身の言葉でとらえる鍵になると述べられています。
◎その(3):相手に「推し」を語るポイント
また、相手に「推し」を語る際には、情報格差に応じた伝え方を工夫することも提案されています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・相手の知らない情報を補足する
・相手の興味に合わせて話す
・相手が興味を持っていないときにはその前提で語る
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
相手との距離感を意識することが、推しをうまく伝えるポイントなのだと学びました。
■まとめと感想
出版ゼミで「良い本とは、相手の課題やニーズを解決する本」と学びましたが、この本はまさに「自分の好きなものを大切にし、言葉にしたい」という欲求を助けてくれる一冊だと感じました。
誰もが発信でき、同時に他者から影響を受けやすいこの時代にこそ、必要とされている本だと思います。私自身も、自分の感性や感覚をもっと大事にしたいと強く思わされました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
※本日のメルマガは「note」にも、図表付きでより詳しく掲載しています。よろしければぜひご覧ください。
<noteの記事はこちら>