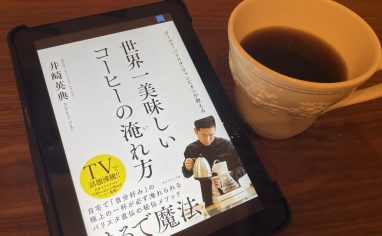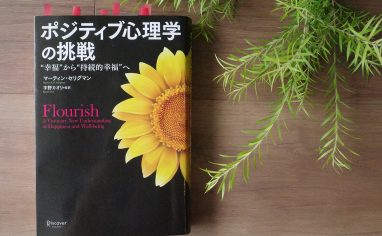ベルリンを3日で50km走り回って思ったこと ーベルリンマラソン応援記ー
(本日のお話 1852字/読了時間2分)
■こんにちは。紀藤です。
引き続きヨーロッパに来ております。
そんな中ですが、15kmのランニングでした。
旅先なのに走ってばかりです。
そして時差により、配信時間がぶれており申し訳ございません。
さて、本日はベルリン3日目の、「ベルリンフルマラソン」について
お話を書いてみたいと思います。
ちょっとマニアックな話ですが、よろしければお付き合いいただければ幸いです。
それではどうぞ!
■世界6大フルマラソンとは?
世界的に最も権威があるマラソン大会として「アボットワールドマラソンメジャーズ」というものがあります。いわく、
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎アボット・ワールドマラソンメジャーズとは
このシリーズは、エリートランナーから一般市民ランナーまで、世界中のランナーにとっての目標となることを目指して、2006年に創設されました。この6つの大会すべてを完走したランナーには「Six Star Finisher」という特別な称号とメダルが贈られます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
とのこと。そして、この中に、あの有名な東京マラソンをはじめ、ボストンマラソン、ニューヨークマラソン、ロンドンマラソン、シカゴマラソン、そしてベルリンマラソンが含まれています。
さて、今回たまたまなのですが、ドイツへの旅行の日程に、このベルリンマラソンが重なっていたのでした。「なんだかやたら宿が高いなぁ。他の日よりも2倍くらいするなぁ」と謎に思っていたのですが、その理由が判明しました。
■ベルリンマラソンについて
ちなみに、ベルリンマラソンは参加者50,000人。東京マラソンのように、当選は簡単ではなく、やはり10万円近くのプレミアム参加費で参加をする枠も用意されているそうです。
とはいえ、コースは歴史的にもマラソン競技的にも素晴らしい。ベルリンの壁で東西に分断されていた時代からの統合を象徴するかのように、コースは東ベルリンから始まり。西ベルリンへ続き、最後は東西の象徴でもあったブランデンブルク門をゴールにするという粋なコース設計です。歴史を感じます。
■マラソンを応援するマラソンをしてみた
そんな中、ある学びの勉強会でご一緒し、またランニングでもつながっているお仲間の1人であるTさんが、偶然このベルリンマラソンに参加していることを知りました。まさかこんな異国の地で、たまたま同じタイミングで出会うことになるとは、まるで奇跡のようでした。
ということで、この日の朝9時15分からスタートするフルマラソンを、応援しながら自分も走る、という計画を立てました。
日々ランニングをしていた成果もあり、ゆっくりペースであれば1日20キロくらいは通常運行で走れるので、6キロ地点・20キロ地点・35キロ地点に走って移動して応援してみたら、練習にもなるし、面白そうだなと思い、実際にやってみることに。
GPSで応援するアプリもあるので、走者がどこにいるかは一目瞭然です。…のはずが、6キロ地点で待ち構えるとあまりの人の多さに見つけられず。そして、20キロ地点でもあまりの多さに結局分からず。Tさん早すぎ、ベルリンマラソン、恐るべし…でした。
さて、実際のコースを走るわけではありませんが、コース沿いを並走してみると、途切れることのない声援とベルリンの街並みが広がっており、まるでベルリンマラソンを走っているかの如き、錯覚を覚えます。
コース脇の道は交通規制で車がほとんど通っておらず、普段なら走りにくそうな道も、人に迷惑をかけない範囲で気持ちよく走ることができます。「裏ベルリンマラソン」的な楽しみ方ができ、とても面白かったです。
途中で一生懸命走っていたら、道端の人に「マラソンのコースはこっちですよ!」と勘違いされたり、国際マラソンのトップ選手の美しいフォームには本当に感動したり、多様な国籍のランナーの中で日本人は少数派でもあり、ひそやかに「自分は日本人だ」というアイデンティティを感じ、良い体験となりました。
■まとめ:走行距離50キロを経て
ベルリンには約三日間滞在しましたが、いくつかの博物館や歴史的スポットを巡りながらも、基本はずっと走っていました。
旅の仕方はいろいろありますが、私にとっては「自分の足で空気を感じながら走ること」が一番楽しい。ブランデンブルク門のような象徴的な場所も、少し外れた川沿いの道も、ドイツの公園の遊具で遊ぶひとときも、日本とは違う住宅地の景色も。走ることで、それらすべてが生き生きと心に刻まれました。
まだ旅の序盤ですが、デンマークでもチェコでも、走りながら、自分の目と足で感じる旅を続けていきたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました!
※本日のメルマガは「note」にも、図表付きでより詳しく掲載しています。よろしければぜひご覧ください。
<noteの記事はこちら>