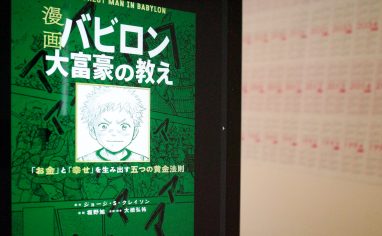デンマークのチェリーワイン醸造所から「持続可能な戦い方」を学んだ話
(本日のお話 2564字/読了時間3分)
■こんにちは。紀藤です。
昨日はチェコにて、12kmのランニング。
プラハの街の歴史的な塔(合計10)を、
走り回りながら登っていた1日でした。
割と寒めの日に、半袖&短パンで、頭にアクションカメラをつけて走っていました。
プラハ城にそんな格好の人はいないので、北欧系の学生団体に「ちょっとアレみてよ!」みたいな空気になっていたのが、ちょっとだけ恥ずかしかったりしたのでした。
まあ、楽しみ方は人それぞれということで!
気にせず、マイペースでいきたいと思います。
*
さて、本日のお話です。
本日もチェコですが、少し前のデンマーク・スタディツアーからの学びをお伝えします。
テーマは「デンマークから学ぶ持続可能な戦い方」についてです。
デンマークの最終日に訪れたのは、ロラン島のチェリーワインの醸造所と、地元のビールの醸造所でした。いずれも規模で戦うのではなく、地域の独自性を打ち出し、自らの「勝ち筋」を見出しているストーリーがとても勉強になりました。そして何より、その成果(ワイン&ビール)がとても美味しかったです…!
ということで、今回の訪問で感じた「持続可能な経営(戦い方)とは何か」そして「強みをどのように尖らせていくのか」について、本日のお話を紹介したいと思います。
それでは、どうぞ!
■世界で唯一?!伝統製法で作る「フレデリクスダルのチェリーワイン」
まず一つ目に紹介するのは、フレデリクスダルというワイン醸造所です。ワインと言っても、チェリーワインが特徴です。
曰く、「世界で唯一、古式ワイン醸造法によるチェリーワインを生産しています」という、非常にニッチな領域で独自の存在感を放っています。
彼らがこだわるのは、以下の3点が特徴的です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・地元と自然に根ざすこと
・Stevns(ステウンス)チェリーという地域資源を最大限活かすこと
・持続可能な農法とクラフトマンシップと革新性の融合
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
もともとオーナーが所有していた広大な土地と、その土地と相性の良い高級品種「ステウンス種」のチェリーを使うことで、まず高品質な原料を確保しているのが土台です。
その上で、決定的な差別化として、彼らは次のような具体的な「尖らせ方」を実践していました。
⑴ 領域の特殊性:「チェリーでワインを作る」
既存のブドウワインとは異なる、「チェリーでワインを作る」という非常に特殊な領域を選択し、そのニッチな分野で世界的な頂点を目指しています。
⑵ 醸造法の独自性:ブドウの原則の「応用」と「実験」
醸造方法にも強いこだわりが見られます。「ブドウワインの原則(発酵・熟成・樽熟成など)」をチェリーワインに応用しています。
特に、熟成や瓶貯蔵、さらには屋外熟成(ガラス瓶での曝露熟成 = Rancio Square)を組み合わせた実験的な手法も取り入れています。
古いフレンチオーク樽、コニャック樽、シェリー樽など、複数種類の樽を用いて風味付けを試みるなど、「クラフトマンシップと革新性の融合」を体現しているわけです。
こうして見ていくと、フレデリクスダルは、
1.「自分たちが持っていた資源(土地の強さ、高品質な品種)を活かし、
2. 自分たちでコントロール可能な領域(荘園)」にフォーカスし、
3. さらに「ブドウワインの原則を応用した醸造法」というオリジナリティを掛け合わせる
ことで、他との明確な差別化を図っていることがわかります。
ニッチな分野も組み合わせると卓越した強みになる良い事例だと感じました。
■地域密着型!地元の「人」と「資源」を活かす「クレンケルップ醸造所」(ビール)
次に訪れたのが、クレンケルップ醸造所というビール会社です。
ここはデンマーク南部・ロラン島にある「クレンケルップ荘園」(Krenkerup Estate)に併設された、600年以上続く家族経営の小規模ブルワリーです。彼らの特徴もまた、「規模で戦わない」姿勢が特徴です。
◎クレンケルップ醸造所の特徴
こちらも、以下の点が特徴だと感じました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・地元の水・農作物など地域資源にこだわり、少量で高品質なビールづくりを徹底
・ローカルコミュニティと密接につながっている点が最大の強み。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
特に興味深かったのが、「ローカルコミュニティとのつながり」です。
ビールの製造過程をオープンにし、地域の人が金曜日の仕事終わりに立ち寄れるような、開かれたビール工房になっているのです。
カールスバーグのような大手には真似できない、「地元の資源(水、麦芽などの原料)」に加えて、「地元民という人のコミュニティ」を最大限活用し、独自の「場」の価値と独自性を創り出している。
この地域との密着こそが、彼らの持続可能な「強み」となっているのだと感じました。
■まとめ: 持続可能性な戦い方とは「ニッチ分野で小さく勝つ」こと
今回、この2つのワイナリーとビール醸造所のお話を聞き、見て、そして体験して(美味しいお酒をいただきました)、改めて強く感じたのは、以下のことです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
持続可能な戦い方とは、自分の強みを活かし、「ニッチ領域で小さく勝ち続けること」である
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
勝負は、必ずしも大きく拡大して勝つことばかりではありません。
今回の例でいえば、それぞれ家族経営という規模を維持しながらも、「〇〇(資源)×〇〇(製法・地域)という領域」を尖らせることで、その独自性を磨いていくことで、長年に亘って、勝つ(持続する)ことができています。そういう意味では、
1,000万人の人に選ばれるブランドではなく10,000人のファンに選ばれ続けるブランドを目指すこと。
そのための挑戦を小さく行なっていくことが、特に中小企業の戦い方の一つなのでは、そんなことを思った次第です。
上記の話は、ランチェスター経営の弱者の戦略としてよく言われることではありますが、実際にデンマークという持続可能性を重視する国で、その成功例を目の当たりにすると、その意味がより深く腹落ちした気がしました。
自分の話で言えば、個人=会社の軸として「強み」ということを一つ柱に掲げていますが、そこに「アカデミックな論文の知見」や「組織行動とのつながり」、「オリジナルの強み探求のコンテンツ」など、小さいけれど様々な要素を掛け合わせたりして、自分ならではのオリジナルの強みをさらに尖らせていきたいと思った次第です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
※本日のメルマガは「note」にも、図表付きでより詳しく掲載しています。よろしければぜひご覧ください。
<noteの記事はこちら>