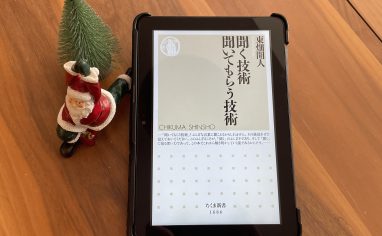やり抜く力を高める「I CANプログラム」とはなにか? ー論文レビュー
(本日のお話 2800字/読了時間4分)
■こんにちは。紀藤です。
昨日は、終日チームビルディング研修の実施でした。
今回も皆さまに、がっつりと事前&事後課題を出して
実際に職場で取り組んでいただく構成になっていましたが
雰囲気から、やっていただけそうな空気を感じました(そう思いたい)。
ぜひ皆様を起点に、職場にはたらきかけていただきたい、
そのように、切に思った次第です。
改めて、ご参加いただきありがとうございました!
また、夕方から12kmのランニングでした。
*
さて本日のお話です。
本日は「グリット(やり抜く力)」を、わずか90分の介入で高めたという興味深い研究をご紹介します。
対象はノルウェーの15歳の学生421名です。本研究では短時間の教育介入(わずか90分)で想定可能な変化が確認されています。
この研究の1年前にパイロット版の論文が発表されており、今回はその再検証にあたる本格的な追試研究です。
「グリットや成長マインドセットを伝える上で、何を押さえればよいか」を考える上で、実用的な内容だと感じました。
ということで、早速みてまいりましょう!
■今回の論文
タイトル:I CAN intervention to increase grit and growth mindset: exploring the intervention for 15-year-olds Norwegian adolescents
(やり抜く力と成長マインドセットを高めるための“I CAN”介入:ノルウェーの15歳青少年を対象とした介入の検証)
著者:Hermundur Sigmundsson / Monika Haga
ジャーナル:Frontiers in Education、2024年11月22日
所属:Department of Psychology, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway(ノルウェー科学技術大学・心理学部)
■30秒でわかる要約
・ノルウェーの421名の15歳の中学生を対象に、やり抜く力(grit)と成長マインドセット(growth mindset)を高める「I CAN」介入の効果を検証した
・実験群(256名)は90分間の「I CAN」プログラム、対照群(165名)は脳に関する一般講義を受講。
・8〜9週間後の再測定の結果、実験群の男子でgritが有意に向上(p=0.046)。
・短時間介入でも信念や態度の変化を引き起こす可能性が示唆されました。
という内容です。
■研究の概要
◎研究目的/背景
・ノルウェーでは生活の質が高い一方で、思春期の若者において孤独、不安、ストレスの増加が報告されています。
・特に15歳前後の学年(10年生)でモチベーション低下が顕著とのことで、教育省は「精神的健康(mental health)」の向上を国家的課題に掲げています。
・本研究では、青少年が「できる(I CAN)」という自己効力感を体験的に学ぶことで、やり抜く力と成長マインドセットの双方を高めることを目的としました。
◎方法
デザイン:準実験的介入研究
参加者:ノルウェー国内38校の中学生421名(15歳)
群分け:
・実験群(256名):「I CAN」介入(90分、2コマ)
・対照群(165名):脳の構造などに関する一般講義(45分)
測定尺度:
・Grit-S Scale(短縮版グリット尺度)
・Growth Mindset Scale(成長マインドセット尺度)
測定時期:介入前と8〜9週間後に実施
分析:分散分析(ANOVA)を用いた群間比較
◎「I CAN」 介入の内容(90分間)
「I CAN」介入は、生徒の信念を「スイッチを入れる」ように変えることを目指した90分間のプログラムです。
MOT(ノルウェーの若者を対象とした社会・感情的学習プログラムを提供する非営利団体)のコーチによって実施されました。
中心となるメッセージ(3つの重要な側面)は以下の通りです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1.努力すれば、自分の限界を超えて多くを達成できる(意図的な練習)
2.困難な状況でも、その気になれば乗り越えられる(成長マインドセット)
3.自信とポジティブな焦点が成功の鍵となる(自己効力感)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
上記を伝える上で、具体的な内容として以下の要素を介入では含めました。
・脳の発達に関する情報:脳細胞の数と発達、および脳の異なる部分に重点を置き、学習のための優れた基盤となることを説明。
・マインドセット関連のテーマ:「脳の可塑性」や「まだ(not yet)」の考え方など、マインドセット介入で一般的な情報に重点を置く。
・意図的な練習の重要性:長期間にわたり一貫して努力を続けることの重要性を示す。例として、数字記憶を7桁から82桁に増やした大学生の事例を紹介。
・神経可塑性の紹介:努力により脳が再編成・変化する能力を説明。タクシー運転手が努力の結果、海馬の体積が増加した例(Maguireら, 2000)を提示。
・感動的な実話:片側脳半球を切除しながら成功したノルウェーのスノーボーダーの物語など、困難を乗り越えるストーリーを紹介。
・比喩の活用:「自分の梯子を登る」などの比喩で、出発点は異なっても誰もが成長できることを強調。
・短い活動:注意と覚醒を高めるために、途中で短いゲームや体を動かす活動を挿入。
・リマインダー・ノートの作成:参加者が最も心に響いた内容を一つ書き留めて持ち帰る「パーソナルノート」を作成。
成長に関して、科学的なデータから、共感を得るエモい話まで、
幅広く伝えることで認知の変容を促そうとしていることが伺えます。
■主な結果
・実験群全体では、「gritのスコア」にわずかに有意な向上(p = 0.06)
・gritスコアの実験群の男子に限ると、有意な向上(p = 0.046)が確認
・成長マインドセットについては、両群ともに有意な変化なし
・対照群ではいずれの変数にも有意な変化は見られず
■結論:研究からわかったこと
1)グリットが向上した(男子のみ)
わずか90分という短期介入で、特に男子生徒においてgrit(やり抜く力)が有意に向上しました。
男子に効果が顕著だった理由として、学業面で改善余地が大きかったこと、また「情熱との結びつき」が強い特性が関与した可能性が考察されています。
2)成長マインドセットは変わらなかった
一方、成長マインドセットへの影響が限定的だったのは、すでにMOTプログラムなど既存の教育で高いベースラインが形成されていたため、
または一度きりの短期介入では十分な変化を生まなかったためとされています。
■まとめと感想
今回の介入は、いわゆる「言語的説得」みたいなものなのかな、と思いました。コーチから様々な情報を伝えたりして、認知を変えていこうとする試みです。
実際、こうしたものの影響がどれくらいあるか介入をよく見てみると、「事前3.07→事後3.13」と高まっていますが、乱暴に言えば「劇的に高まっているわけではない」ともいえます。とはいえ、45分×2回という短時間の授業形式で「やり抜く力=グリット」が高まったというのは興味深く感じました。
研修などでよく話題になるのが「成長マインドセットをどう高めるか」みたいな話でもあるのですが、これらを高める具体的な介入なども、もっと知りたいなと思った次第です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
※本日のメルマガは「note」にも、図表付きでより詳しく掲載しています。よろしければぜひご覧ください。
<noteの記事はこちら>