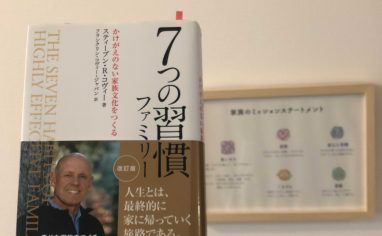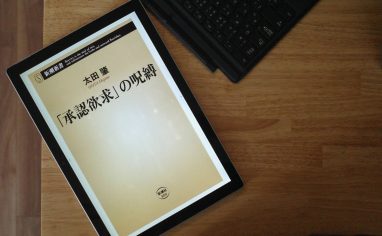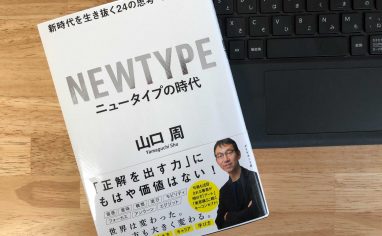今週の一冊『絵本の力』
(本日のお話 2453字/読了時間3分)
■こんにちは。紀藤です。
毎週日曜日は、最近読んだ本の中から一冊をご紹介する「今週の一冊」のコーナーです。
今週の一冊はこちらです。
─────────────────────────────
『絵本の力』
河合隼雄・松居直・柳田邦男
─────────────────────────────
私事ですが、我が家には4歳児がおります。そして寝る前に「絵本読んで」が日課となっています。そんな話をなにげに知人の方にしていたところ、
「『絵本の力』は読んだほうがいいですよ、絵本の読み方・世界の奥深さに震えますよ!」と言われ、読んでみたのでした。
そのタイトル通り、「絵本が持つ力」に向き合う一冊で、いろんな絵本を、もっともっと自分が出会いたいと思いましたし、子どもに聞かせてあげたい、そう思える一冊でした。
ということで、中身を見てまいりましょう。
それでは、どうぞ。
■本書の概要
本書は、“絵本”を単なる子ども向けの読み物としてではなく、絵・文字・音・語りという複合的なメディアとして捉え、「人が生きること」「感性・言葉・想像力」「大人と子ども」の関わりを再考しようと試みている書です。
3名の異なる立場の専門家(臨床心理学・編集/児童文学・ノンフィクション)による、講演や座談の形式で、絵本の力を探求して、「育つ力」「つながる力」「生を支える力」など、絵本が持つ多面的な“力”を掘り下げています。
■本書の内容について
本書は、それぞれの専門家が語る「絵本の力」を3部構成で語ります。そして最後の章で、3名による対談が書かれているという形です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・講演1:河合隼雄「絵本の中の音と歌」
・講演2:松居直「絵本/語り/絵の総合芸術として」
・講演3:柳田邦男「いのちと共鳴する絵本」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
それぞれの立場から、絵本が子どもや大人にとってどんな意味を持つのか、ポイントを整理してお伝えしてみます。
◎「絵本は音と歌でできている」(河合隼雄の視点)
絵本の「音」「歌」「語り」に注目し、絵本を“絵+文字”という静的な存在ではなく、声・リズム・語りといった時間的で聴覚的な体験として捉えています。「絵が言葉を持っている」という表現が印象的でした。
そして、絵本は子どもだけでなく大人の心にも響くものであり、「声の言葉を受け止める」という体験を通して、言葉・絵・イメージの重なりから心の奥に届くものがあると述べています。そういう意味で、やはり「声に出して読むこと」が重要であると述べます。
◎「絵本は大人が子どもに読んでやる本である」(松居直の視点)
編集者・児童文学家の立場から、「絵本は子どもに読ませる本ではない。大人が子どもに読んでやる本である」と強調しています。
そして、絵と語り・言葉の関係を「総合芸術」として捉え、“語りかけ”の力や、絵を「読む」子どもと絵を「見る」大人の違いについても述べており、また、日本語・語り・絵の文化的側面を重視し、絵本を通じて「日本語の強さ、生命力」を次世代に伝えることの重要性を説いています。
バタ臭い(西洋かぶれしている)みたいな表現がいくつか見られており、日本文化の大切さや、また翻訳の絵本を編集する上での苦労(海外の言葉をばらして、再度構成しなおす)ことへのこだわりなど、今の日本の絵本がどうやって今の形になったかという歴史も知ることができました。
◎「人生は3度絵本を読むときがある」(柳田邦男の視点)
ノンフィクション作家として、自身の体験(喪失・死・生の危機)を背景に、絵本の意味を再考しています。
息子さんが、心の病の果てに、自分で命を断ってしまったときの喪失体験の中で、息子さんに読んでいた絵本を思い出す話を、柳田さんは語られています。その中で、ふっと、絵本によって気付かされたことがあったということから、絵本は必ずしも子どものためのものでもない、と述べています。
「人生に三度、絵本を読む時期がある。(1)子どものとき、(2)子どもを育てるとき、(3)人生の後半/振り返るとき」という言葉が印象的で、大人こそ絵本を読むべきだという主張が込められていました。
■個人的に印象に残ったこと
最も印象に残ったのは、「絵本は子どもに読ませる本ではない。大人が子どもに読んでやる本である」という言葉でした。
絵が言葉を持ち、その言葉を大人が声に乗せて読む。
そのリズムと響きが子どもの中に物語の世界を作り出していく。
この声と絵が交わる瞬間”こそが絵本の魅力なのだと感じましたし、それを作り出せる時間が「絵本を読んでやる(敢えてそう書きます)時間」なのだと思いました。
また、良い絵本は大人が読んでも、教養として深いテーマがあることも知りました。たとえば、『もりのなか』では「人と遊びの深い関係性」(ホモ・ルーデンス的な世界)を描き、あるいは『わすれられないおくりもの』では“死と喪失”というテーマを20数ページに凝縮して、子どもが理解できるように伝えています。
それは、大人が文章で学ぶ教訓を、絵と物語という凝縮された芸術として子どもに伝えるということでもある。まさに、絵本が持つ“凝縮の力”を再認識させられました。
そして、三人の著者の対話からは、その教養と洞察の深さに圧倒され、自分自身も「もっと多様なものの見方やツールを知りたい」と思わされました。
■まとめ
繰り返しになりますが、我が家には、ややゆっくりと、しかしすくすく育っている4歳の息子がいます。毎晩「絵本読んで」と言うのが日課です。
主に妻が読んでいますが、妻の絵本の読み方が、かなり理想的であることに気付いて、勝手ながらリスペクトしました(絵と音の世界を楽しませるための抑揚や間を大事にする)
音や“間”、絵とのマリアージュを楽しむように読むこと。
そして絵本の世界から、知識や興味を少し広げてあげること。
そのどちらも大切なのだと改めて気づかされました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
『おじいちゃん』
『アンジュール:ある犬の物語』
『わすれられないおくりもの』
『ちいさなちいさな王様』
『アフリカの音』
『ヴァイオリン』
『もりのなか』
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
これから読むのが楽しみです。最後までお読みいただき、ありがとうございました!
※本日のメルマガは「note」にも、図表付きでより詳しく掲載しています。よろしければぜひご覧ください。
<noteの記事はこちら>