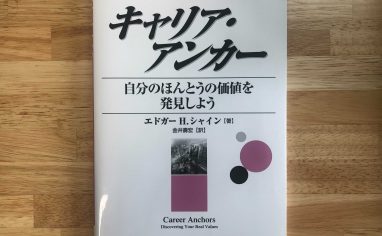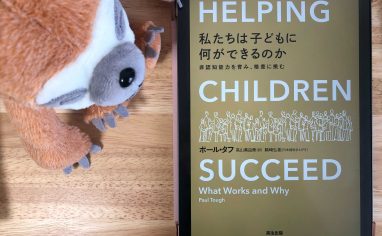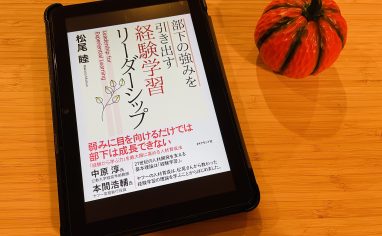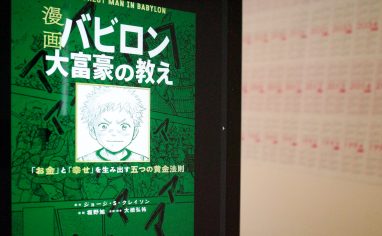チームワークにおける3つの問題点とは 〜「集団圧力/集団浅慮/社会的手抜き」に注意!〜
(本日のお話 2885字/読了時間5分)
■こんにちは。紀藤です。
昨日は終日、会社の経費処理を
ひたすら行っておりました。
よろしくないのですが、
領収書など8ヶ月分溜めており
印刷した領収書の山にもがいておりました。
こういうことがサラリと出来る経理の人、
本当に尊敬します。
やっぱり人は得手不得手があるんだなあ、、、。
(しみじみ)
*
さて、本日のお話です。
昨日、「集合知の力」として、
『グループ・ダイナミクス』
(=人が集まることにより起こる様々な現象)
として、ジェリージーンズの実験のお話を
いたしました。
ジェリービーンズの数を当てる、というような
状況推定問題などの場合、
個人の予測よりも、
様々な視点を持つ複数で予測し
平均をしたほうが「常に」正解に近い数字になる、
そんな興味深い実験です。
※詳しくはバックナンバーをご覧ください↓
本日は、その逆で、
「人が集まることが
ネガティブな結果になりうる」
ケースについて、
”皆で協力することに潜む3つの問題点”
について、
組織行動論の観点から、学びを皆さまに
ご共有させていただければと思います。
タイトルは、
【チームワークにおける3つの問題点とは 〜「集団圧力/集団浅慮/社会的手抜き」に注意!〜】
それではどうぞ。
■上述の「ジェリービーンズの実験」のように
”人が集まる”ことは
望ましい成果を発揮することが
ままあるものです。
まさに「三人寄れば文殊の知恵」ですね。
これは皆の力が合わさって、
いうならば、
”ポジティブなグループ・ダイナミクス”
が発動された状態と言えるかと思います。
■、、、しかし、一方、
「船頭多くして船山に登る」
という諺もあります。
すなわち、
”人が集まる”ことで、
むしろ成果から遠ざかるような
ネガティブな方向に力が働くことがある、
という話。
皆が集まったけど、
・責任の所在が曖昧になったり
・同調圧力で異論を出せなくなったり
・何となく他のメンバーの意見に乗っかったり
、、、となってしまい、
(↑こういうの、ありますよね(汗))
これ、むしろ、個別に責任を与えて
進めたほうがよかったんじゃないか…
なんて思ってしまうような、
組織でよく起こりがちなあるある現象。
いわば、
”ネガティブなグループ・ダイナミクス”
が発動してしまった状態とも言えるかと。
■さて、どうして
”三人寄れば文殊の知恵”になるはずが、
”船頭多くして船山に登る”になってしまうのか?
何が「皆で協力すること」を妨げるのでしょうか?
、、、このことについて
『組織行動論』
(=組織の中の人の行動を研究した理論)
が明らかにしており、
実に興味深く、納得させられるお話があります。
「チームワークにおける3つの問題点」として
以下、まとめます。
(ここから)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【チームワークにおける3つの問題点】
<問題1)集団圧力 >
…個人に対して集団の規範や意見に同調するような
圧力がかかってしまうような現象のこと。
※ 集団のメンバー間で共有されている適切な振る舞いに関する基準を「集団規範」といいます。
人は集団規範に併せた行動をとりがちになります。
そして、集団圧力となり、その場での適切な振る舞いをしようとします。
その理由は”自分が浮いた存在になりたくない”、“集団に受け入れられたい”
”他のメンバーから逸脱したくない“という欲求があるからです。
<問題2)集団浅慮>
…1人1人は優秀であっても、
人が集まって集団で決定することによって、
愚かな決断を下してしまうこと。
※結束力が高く、有能な集団であればあるほど、
メンバーが自信過剰になり、異質な意見が排除されやすくなります。
深く考えないまま決定がなされ、訂正もされづらくなります。
※1986年 NASAのチャレンジャー号で起こった爆発事故は、
実はリスクがあることを知っていた、と言われています。
その中で、他のメンバーが見ているから大丈夫だろう、という
「集団浅慮」が働いていた、と言う視点もあります。
<問題3)社会的手抜き(リンゲルマン効果)>
…個人が本来できるはずの努力をしない、
あるいは能力を発揮していないために、
集団のパフォーマンスが本来あるべき水準を
下回ることがあるというもの。
※研究結果によると、
集団のサイズが大きくなればなるほど、
個人が単独で作業した場合の努力量と、集団で作業した場合の努力量の差が
大きくなることがわかっています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(ここまで)
■、、、さて、いかがでしょうか。
何となく、解説を読んで頂くと
組織で皆さまも思い当たる節が
あるのではないかと思います。
これはいい悪いではなく、
”組織の中にいる人が、
社会心理的に、このような行動を
とりがちである”
という人間の心理を
表しているだけの話。
ただ、放っておくと
上記のような
問題1)集団圧力
問題2)集団浅慮
問題3)社会的手抜き
が起こってしまう可能性が高いため、
そのことを想定した上で、
対策を打っておきたいもの。
■ではどうすれば、
【チームワークにおける3つの問題点】
が起こらないように対策できるのでしょうか?
これもいくつか言われている話があり、
以下の”条件設定”をすることで
集団での協働を機能させることができるといいます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
<皆での協働を機能させるための”条件設定”>
1,「フラットなコミュニケーションを活性化させる」工夫をする
2,多様なタイプのメンバーを揃える
3,メンバーが多数派の意見に流されないように工夫する
4,自信過剰に陥って異質な意見を排除しない
5,他の誰かの努力にただ乗りしない
6,積極的にディスカッションに加わる工夫
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
、、、とのこと。
■ちなみに特に大事なのは、
”フラットなコミュニケーション”
だそうです。
確かにそもそも
「言いたい事も言えないこんな組織じゃ、、、(POISON?)」
みたいな状況が想像できますよね。
ゆえに、今話題の
「心理的安全性」(自分が傷つけられないと感じる)も
上記のチームの協働を機能させるという観点でも
とても大事な要素なのでしょう。
■人が集まる事による可能性は、
素晴らしいものがあります。
ゆえに組織は、チームは
1人では決して出来ない、
目を見張るような成果を出すことができます。
一方、起こってしまいがちな問題点もある。
ゆえに、
・集まることによって起こりうる問題点を知る
(whatとwhy =何が、なぜ起こるのか?を知る)
・集団の協働を機能させるための条件を知る
(how= どうすれば対処できるのか?を知る)
を学ぶことで、
より効果的・効率的に
チームの力を発揮することができますし、
ゆえに「組織行動論」など、
学ぶ価値が非常に多いなあ、と
私自身学びつつ感じております。
ということで、
チームの力、ぜひ
活かしてまいりましょう!
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
本日も皆さまにとって、素晴らしい1日となりますように。
===========================
<本日の名言>
ただ傍観して、不平を言っていてはいけません。
あなたがたは「誰か」が行動を起こすのを待っているのでしょうか。
行動を起こさなければならないのは、あなた方自身なのです。
ワンガリ・マータイ(ケニアの環境保護活動家/1940-2011)
===========================