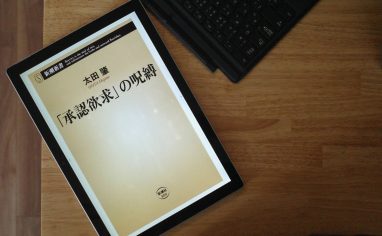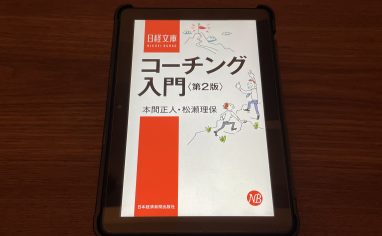「曽我梅林の梅まつり」にて、梅を知る
(本日のお話 1958字/読了時間2分)
■おはようございます。紀藤です。
さて、本日のお話です。
土曜日に小田原市の
「曽我梅林の梅まつり」に、
大学院の仲間と遊びにいかせていただきました。
これまでの人生で「梅」について、
あまり考えたこともなかったのですが、
今回の梅まつりで
梅について学び(?)を深めつつ、
「”解像度を高める”とは
こういうことではなかろうか」
と、一人納得したのでした。
今日はそのお話について
そして梅まつりについて、
ゆるりとご共有させていただければと思います。
それでは早速まいりましょう!
タイトルは
【「曽我梅林の梅まつり」にて、梅を知る】
それでは、どうぞ。
■2-3月は梅が美しく咲く季節です。
その中で、
曽我梅林という600年以上続く
歴史的な名所があります。
曰く、
”神奈川県小田原市では、
600年以上前北条氏の時代に梅の実を
兵糧用にするため、城下に多くの梅の木が植えられました。
(中略)
曽我梅林では、中河原・原・別所の各梅林からなり
約35,000本の白梅が植えられています。”
※引用「曽我の里 別所梅林」
https://soganosato.com/umematuri.html
とのこと。
■そんな中
大学院のお仲間の一人で、
「曽我梅林」
小田原の観光地でもある、
梅まつりの運営に携わっていらっしゃる方がおり、
先日そちらに大学院メンバー数名で
観光にいったのでした。
■見渡す限りの梅の木。
そしてお祭りっぽい出店と
生搾りオレンジ(梅じゃなく)の
気合を込めたセールストークが響き渡る中、
気分が自ずと高揚してきます。
しかし、
このように梅に囲まれていると
様々な疑問が湧いてきます。
そして、
梅まつりにも関われている
大学院の仲間のHさんに
・梅の国内生産量
・梅の種類と育て方
・梅の木の良し悪し
などなど、
梅林を散策しながら
梅にまつわる種々のお話を
聞かせていただいたのでした。
■例えば、
「梅の生産地のあれこれ」
について。
1位:和歌山県→ 南高梅で有名。チョーヤの梅酒。国内シェア約65%。
2位:群馬県→ 群馬の約685分の1が梅園。国内シェア約5%
3位 三重県→ 三重の約2386分の1が梅園
・・・
5位 神奈川県
だそうです。
「チョーヤの梅酒」、
日本どこでもあるのは
和歌山から来ていたのか、、、
と納得します。
■梅の種類も、やっぱりたくさん。
お酒にするもの
梅干しにするもの
、、、
それぞれ特性が違い、
また花の色も味も違うようですね。
(黒糖梅酒とか色々ありますね)
■そして何より、
「梅」の木の生育の話は
なかなか興味深いものでした。
・梅の木は収穫しやすいように
高さは低くなるように剪定している
(だから、低いんですね)
・イイ感じの梅の木は、
3つの主枝が広がり、パラボナアンテナようである
(葉が密集せず、虫がつきにくいそうな)
・そのような形に育てるために、
農家さんが手塩にかけて何年も育てていく
(なので、木のトレードなどは安易にできない)
・梅の花は、違う品種で受粉させたほうが良い実ができる
(そのため隣には違う品種の木を植えることも)
、、、などなど。
■誰からか直接聞ける話には
エネルギーがあります。
なるほど、と頷きつつ
そのお話を聞きながら
ふと思い出した記憶がありました。
それは、東京都文京区にある
「小石川植物園」に数年前行ったときのお話。
そこには、
梅がかなりたくさんあり
色とりどりの梅が咲いていました。
(調べたところによると
園内の梅林は35品種、90本の梅がある)
ただ、当時
よくわからないので、
「いろんな色だねえ」
くらいの安易すぎる感想とともに、
通り過ぎておりました。
■それは、
”「梅」がよくわからなかったから”
に違いありません。
Googleで調べればよいのかもしれませんが、
そこまで梅への愛も深くないのが実際なところだったので、
ある意味当然の帰結です。
■しかし、今回
「梅に詳しい方から直接聞く」
そして、
梅まつりと大学院メンバーという
なにやら楽しげな思い出をスパイスにすることで
梅に対しての興味と
肯定的な思い出が作られました。
そして、脳内メモリに
「梅」フォルダが作成された、
そんな感覚を得たのでした。
■そしてもしかすると
こうしたことがきっと、
机上では学べない
「体験からの学び」
であるのかな、とも思いました。
そしてこのような経験を増やすと
同じものを見たとしても
違う感覚で捉えることもできるのかもしれない、、、
そして、それこそが
『解像度を高めてみる』
ということなのかもしれない
、、、などと思ったというお話。
■一見興味がないと思うことでも、
直接見に行ってみること。
その道に詳しい人に、
熱く語っていただき、
そして体験を刻むこと。
そうして、
世界の解像度は
高まるような気がします。
知らないことはたくさんあるので、
そんな風に、それぞれの道の面白さを
もっと聞いてみたいものだな、
そんなことを思った次第です。
曽我梅林の梅まつり、
今年はもう終わるようですが
また機会があればぜひ行ってみてくださいませ。
お勧めです。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
==========================
<本日の名言>
梅は香りに桜は花
(優れているものを表す)日本のことわざ
==========================