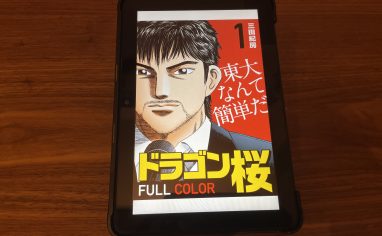経営戦略の基本!SCP理論に基づく「3つのフレームワーク」をご紹介
(本日のお話 2753字/読了時間4分)
■こんにちは。紀藤です。
昨日は2件のアポイント。
また研修プログラムの作成と生成AIの勉強。
夕方からは5kmのランニングでした。
*
さて、先日から始めました『世界標準の経営理論』の読書レビュー、今日も引き続きお届けしてまいります。
本日は「第2章」です。全40章中、あと38章。
まだ山の一合目ですね・・・!
しかし「骨太な理論を、まだ38も学べる」というのは、ある意味楽しみです。これから、どんな世界が見えるのでしょうか。
ということで、本日の章のまとめを、早速みてまいりましょう!
―――――――――――――――――――――
<目次>
「SCP理論」をフレームワークに落とし込む
フレームワーク1:ファイブフォース分析
フレームワーク2:戦略グループ
フレームワーク3:ジェネリック戦略
持続的な競争優位は幻想なのか?
まとめと感想:小さな会社でも、戦略は使える
―――――――――――――――――――――
■「SCP理論」をフレームワークに落とし込む
さて、今回の章は「SCP理論をベースにしたフレームワーク」がテーマです。SCP理論をひと言でいえば、「完全競争から離れ、できる限り完全独占に近づけることが収益性の向上につながる」というものでした。
そしてそのSCP理論を、より実務で使えるように「フレームワーク」として落とし込んだものが、今回の章で紹介されています。本書では「フレームワークはあくまで副産物にすぎない」とし、その根底にある理論の理解を重視しています。
ただし、今回は有名な3つの戦略フレームワークが登場します。そう、MBAでも頻出の「ファイブフォース分析」「戦略グループ」「ジェネリック戦略」の3つです。早速、1つずつみてまいりましょう!
■フレームワーク1:ファイブフォース分析
まずはポーターによる「ファイブフォース分析」から。
このフレームワークでは、産業の収益性は5つの「脅威(フォース)」によって決定されるとされます。そして、これらの脅威が強い産業ほど「完全競争」に近づき、収益性は低くなる。一方で脅威が弱い産業は「独占」に近づき、収益性が高まるのです。
例としてよく挙げられるのが、アメリカの国内航空産業。ここは収益性が低く、ファイブフォースのすべてが強く働いている業界として有名です。
――――
フォース1.潜在的な新規参入企業
参入障壁が低ければ、儲かると見て新規企業が続々と参入し、競争が激化します。アメリカの国内航空業界は1978年の規制緩和により、参入障壁が一気に下がりました。その結果、新規参入が相次ぎ、既存企業の収益性は大きく低下したのです。
フォース2.業界内の競合関係
競合が熾烈なほど、価格競争に陥りやすくなります。特に差別化が難しい業界では、競争は価格に集約され、収益性は下がります。アメリカの航空業界も例外ではなく、現在でも百社を超える航空会社が乱立しています。
フォース3.顧客の交渉力
顧客が簡単に他社に乗り換えられる状況では、顧客の交渉力が強くなります。航空券などはまさにその典型。価格比較もしやすく、ブランドに対するこだわりも相対的に薄いため、企業側は価格で勝負せざるを得なくなります。
フォース4.売り手の交渉力(供給業者)
飛行機本体を製造している企業は数社しか存在しません(ボーイング、エアバス、ボンバルディアなど)。選択肢が少ないことで、サプライヤー側の交渉力が強くなり、コスト増を強いられるのです。
フォース5.代替品の脅威
代替手段が豊富なほど、その産業の魅力は下がります。アメリカでは鉄道よりも高速道路と自動車の方が整備されており、ガソリン代も安価なため、飛行機の代わりに車での移動が選ばれるケースも多くなります。
――――
このように、ファイブフォースによって「産業の収益性」を可視化することができるのです。視覚的にも理解しやすいため、戦略立案時の基本ツールとしてよく使われる理由がわかります。
■フレームワーク2:戦略グループ
次に紹介するのは「戦略グループ」という考え方。
これは、同じ業界の中でも「自社にとっての真のライバルは誰か?」を見極めるために、企業群をグループ化する手法です。
――――
たとえば自動車業界を例に取ると、
高級車メーカー(ジャガー、BMWなど)
パフォーマンスカーメーカー(ポルシェ、マセラティ)
大衆車かつグローバル展開(トヨタ、フォルクスワーゲン、GMなど)
――――
このように製品の価格帯や地理的展開、サービスの内容によって企業は異なる戦略グループに分類されます。
戦略グループを把握することで、「誰と戦うべきか」「どこで差別化できるか」といった戦略上の視点が明確になります。単に業界を一括りにするのではなく、競争の輪郭をより鮮明に捉えることができるのです。
■フレームワーク3:ジェネリック戦略
最後は、ポジショニング戦略の核ともいえる「ジェネリック戦略」です。
ジェネリックとは「包括的な」という意味。ここでは、企業がどのように市場でポジションを取るかを2つの基本的な軸で整理します。
――――
◯コスト主導戦略
徹底的にコストを削減し、低価格で市場シェアを拡大する戦略。安さで勝負し、競争優位を築きます。
◯差別化戦略
独自性ある製品やサービスを提供し、他社にはない価値を打ち出す戦略。価格競争を避け、高付加価値で収益性を高めていきます。
――――
そして、SCP理論の観点からいえば、「完全競争から離れ、完全独占に近づく」ことが望ましいとされるため、この2つのうち、目指すべきは明らかに「差別化戦略」になります。
実際にファイブフォース分析でも、差別化によって各フォース(脅威)を弱めることができる、という示唆がなされています。
■持続的な競争優位は幻想なのか?
一方で、SCP理論には批判もあります。
それは、「安定」と「予見性」を前提にしている点です。
現代のように市場の変化が激しい時代では、ひとたび得た競争優位がいつまでも続くとは限りません。
実際にアメリカ企業6,772社を対象にした分析によると、「持続的な競争優位」を維持できている企業はわずか2〜5%程度だったそうです。
今は、状況の変化に応じて「一時的な競争優位」をいかに連鎖させていけるかが重要だといいます。
さらに、SCP理論では「人間は合理的で、認知バイアスに左右されない」という前提があります。しかし実際には、意思決定において非合理な要素や感情が大きく作用します。そういった“人間らしさ”を無視している点も、限界として指摘されているのです。
■まとめと感想:小さな会社でも、戦略は使える
今回の章を読みながら改めて感じたのは、「差別化戦略」は、実は自分のような小規模な会社にこそ重要なのだろうな、、、ということです。
私は企業の人づくり・組織づくりの支援をしている小規模の会社を経営していますが、たとえば大手のリクルートやパーソルと競うのではなく、「小回りが利く」「現場のニーズに柔軟に応えられる」といった点が、差別化の源泉になります。
そのうえで、今のところの自社ならではの強み(立教大学大学院で専門性を学んでいる=理論を応用できる、信頼のおける情報を提供できる、統計ができる(仲間がいる))といった知見は、ファイブフォースのような「外部の脅威」を緩和できるよな、と思ったりするのでした。
戦略フレームワークを、大企業だけでなく、小さな組織にも活用していく。そんな視点を持てたことが今回の収穫でした。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
※本日のメルマガは「note」にも、図表付きでより詳しく掲載しています。よろしければぜひご覧ください。
<noteの記事はこちら>