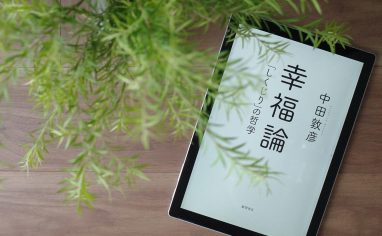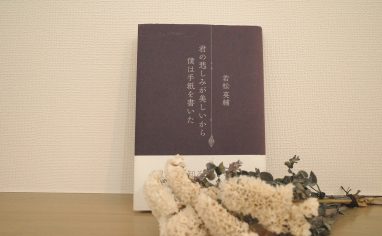おすすめの一冊『読書について』
(本日のお話 2775字/読了時間4分)
■こんにちは。紀藤です。
引き続き、沖縄に来ております。
先日、博識な知人が「商業出版に物申す」的な流れで、多くの出版物がいかによろしくないのか…という話を熱く(?)語ってもらいました。
要は、本当に中身があり価値のある本ほど読まれず、大衆にとって読まれやすい本ほど(人類の知を残すという意味においては)実は価値がないということ。
そして「ショーペンハウアーの『読書について』は読んだほうがよい」とのことで、早速手にとってみたのでした。
なかなかの毒舌っぷりなのですが、納得できることも多く、感想として「本格的に書き始める前に、読めてよかった」と思える一冊でした。
ということで、早速中身を見てみたいと思います。
====================
『読書について』 (光文社古典新訳文庫)
ショーペンハウアー (著), 鈴木 芳子 (翻訳
=====================
■ショーペンハウアーとは
本書は、哲学者ショーペンハウアーによる1851年刊の『余論と補遺』の一章として「読書について」が収められています。
巻末にショーペンハウアーの生涯が書かれていますが、幼少期から父親の教育により、哲学者に師事をするなど、学問の世界を志す意志を見せるものの、同じく父親から商人になるように強く言われ、商人の道を歩んだ青年期を持ちます。
その後医学科へ進学、哲学科へうつって、カントとプラトンを研究し、彼の哲学体系の軸となった、とのこと。
このあたりは私も詳しくはないのですが、本文を読むと「出版の商業主義への辛辣な言葉」「無知な金持ちに対する痛烈な批判」などが、何度も何度も登場してくることから、
彼の生い立ちにおける、知性なき拝金主義への”怒り”のようなものを私は感じました。
例えば、こんな感じです。
―――――――――
ドイツ国内でも国外でも、今日の文学は悲惨をきわめるが、その元凶は本を書くことでお金が稼げるようになったことだ。お金が要る者は、猫も杓子も、机に向かって本を書き、読者はおめだたくもそれを買う。その付随現象として、言葉が堕落する。
へぼ作家の大部分は、その日に印刷されたもの以外読もうとしないおめでたい読者のおかげで生計を立てている。
P24
――――――――――
”へぼ作家”、”おめでたい読者”、”言葉の堕落”など、原文はわかりませんが、日本語訳では痛快な言葉で書き表されます。しかし、150年前も今も、ある立場にたてば、とても納得いく話にも思えます。
私レベルの読者でも、研究者が生涯をかけた濃厚で、学び深き専門書はあまり手に取られず、”おかゆ”ように希釈して食べやすくした本が何万部も売れるというのは、「人類の知を書を通じて残していく」という観点では、なんだか切ない感覚もある、という見方もできます。
この点は、本書の批判として「良書/悪書の線引きが”エリート主義的”であり、大衆の娯楽や共感などを認めていない」というお話もあるようですが、その立場を明確にして主張するところに、「たしかに・・・!」と唸らされるのでした。
■「読書について」のポイント
さて、では本書で述べているショーペンハウアーの主張はどのようなものなのか? 以下いくつかポイントを絞って、まとめてみます。
まず、「多読はよろしくない」という主張です。
基本的に「読書とは自分の頭ではなく、他人の頭で考えることである」と述べ、すなわち本を読んでいる間は”他者の考えを受けるだけで、自分の思考を止めている”ことになる、というわけです。
本を読むことによって、それが刺激となり、また自分の思索が広がることはある。しかし、「あくまでも自分の頭で考える」ことが常に主役であるべきで、そのための材料として読書はしたほうがいいというわけです。
多読をしていると、常に他者の考えが頭の中を歩き回っているので、そうするよりも、良書をじっくりと読み、立ち止まって考えるのが大事、と述べます。
次に、「良書を読むために、悪書は読まないこと」です。
私たちは限られた時間しかない、なので、良書を読むためには悪書を読まないようにするべきだ、と述べます。もし悪書に出会ったと気づいたら、「ただちにその本を投げ捨てなさい」とすら言います。
基本的に、良い本は元々それを書いた創始者のような古典を読むべきで、それを模倣したり二番煎じのような著書は、”剽窃したものである”、”自分の価値を示したいだけ”のような表現をし、斬って落とします。
特に「稼ぐためだけの書き手」は、世の中に悪書を量産するので、ただちにいなくなるべき、くらいのテンションで語ります。
■「著者」として参考にしたいこと
というように、ショーペンハウアーは基本的に凡庸・平凡な著者について、かなり厳しいスタンスを取っています。特に、「背伸びをして良く見せようとした凡人」については、よりいっそう、厳しい。
しかし、たとえ凡庸な人でも、読むに値するものを書くことができる、と述べているシーンもあります。それが、私なりの解釈でいえば「等身大の言葉で表現する」ということです。
たとえば、このように述べます。
――――――――――――
文体は書き手の顔だ。精神の相貌が刻まれている。それは肉体の顔よりも、もっと見まちがいようがない。他人の文体をまねるとは、仮面をつけることだ。仮面はどんなに美しくても、生気がないためにまもなく悪趣味で耐えがたいものになる。醜くても生きた顔のほうがいい。(P42)
――――――――――――
なるほど、「醜くても生きた顔のほうがいい」のですね。
言葉に仮面をつけて着飾っても、精神は透けて見えてしまうようです。
――――――――――――
凡庸な脳みその持ち主は、考えたことをそのまま書く決心がつかない。そんなことをしたら、パッとしない代物になるだろうと、うすうす感づいているからだ。
それでも、ちょっとしたものになることもある。ひたすら真摯に仕事に向かい、わずかばかりのありふれたことでも、かれらが実際に考えたことを、考えたとおりに、とにかくそのまま伝えようとするなら、読むに耐える本、分相応の世界で、それなりにためになる本が書き上がるだろう。(P43)
――――――――――――
「凡庸な脳みその持ち主」が「ちょっとしたものになる」ためには、
「わずかばかりのありふれたことでも、そのまま伝えようとする」ことで「読むに耐える本、それなりにためになる本」ができるそうです。
(でも、これ、とってもよくわかります。
まさに、私の日々の発信がこれだなあ…と思います。
すごいものを書けるとは思えないなら、素直に書くしかないのですよね)
■まとめと感想
改めて、読んでみた感想として、哲学者ショーペンハウアーの毒舌に、ちょっとした抵抗感を覚えつつも、納得させられる本でした。
そして、自分が本を書くのであれば、「誰かの言葉を模倣するのではなく、飾らない言葉で、自分が感じ、体験したことを伝えていく」ことが必須なのだろうな、と感じました。
「凡庸な人物」の代表である自信がありますが(汗)、これは著書を書くうえで大切にしたいというメッセージが詰まっており、背筋が伸びる良書でございました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
※本日のメルマガは「note」にも、図表付きでより詳しく掲載しています。よろしければぜひご覧ください。
<noteの記事はこちら>