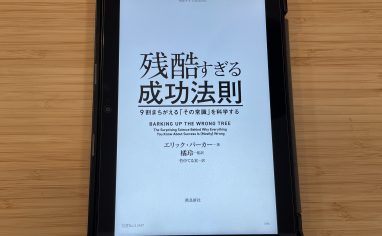リーダーシップ理論の100年の歴史を「5つの分類」で紐解く
(本日のお話 2753字/読了時間3分)
■こんにちは、紀藤です。
昨日は4件のアポイント。
また研修企画の作成、夕方は10kmのランニングでした。
*
さて、本日のお話です。
本日も引き続き大著書『世界標準の経営理論』の全章レビュー、引き続きお届けしてまいります。
いよいよ「第三部 ミクロ心理学ディシプリンの経営理論」に入っていきます。800ページの著書も折り返し地点です。
この部ではビジネスパーソンにとって日常的に直面する課題に直結する内容――リーダーシップ、モチベーション、意思決定といったテーマが中心となります。非常に実用的な内容で、読んでいてワクワクする章でした。
さて、本日のテーマは「第18章 リーダーシップの理論」についてご紹介していきたいと思います。
リーダーシップ理論の約100年の歴史を振り返る、濃厚な章でした。
それでは、早速参りましょう!
■そもそも、リーダーシップとは何か?
まず、「リーダーシップとは何か?」という定義から見ていきましょう。本書では、バスによる以下の定義が紹介されています。
――――
リーダーシップとは、状況あるいはメンバーの認識、期待の構成・再構成がしばしば行われるグループにおける、メンバー間の相互作用のことである。この場合、リーダーとは変化を与える人、すなわち他者に対して影響を与える人のことを指す。
グループ内のある人が、他メンバーのモチベーションや能力を修正する際、それがリーダーシップである。(筆者抄訳)
――――
私が関わらせていただいている大学では「リーダーシップ=チームの目標に向けて他者に与える影響力」と定義していますが、あくまでもこれもひとつの定義です。
実は、リーダーシップの定義は今なお、完全には定まっていません。
本章では、リーダーシップ理論の歴史をひもとくことで、その多様な側面をシンプルかつ網羅的に理解できる構成になっています。
以下、5つの理論群(リーダーシップ理論の変遷)として整理されていますので、1つずつポイントを見ていきましょう。
■理論1:リーダーシップの個性理論(1940年代~)
最も古い理論は、リーダーの「個性」に焦点を当てたものです。「見た目からしてリーダーっぽい人」が持つ特性――即戦力、自信、支配力、独立心などが研究されてきました。
しかしながら、こうした特性に対して明確なコンセンサスは得られていません(ただし、心理学の「ビッグファイブ」の観点からは、外交性の高い人が変革型リーダーになりやすい、という相関が見られています)。
■理論2:リーダーの行動理論(1960年代)
次に登場したのが「リーダーの行動」に注目した理論です。ここでは、リーダーによって部下への接し方や働きかけのスタイルが異なり、それが組織やチームに与える影響を分析しています。
たとえば、
――――
ミシガン大学:業務重視型 vs. 従業員重視型
オハイオ州立大学:役割設計重視 vs. 人間関係重視
――――
といった分類がありました。
130本の実証研究をまとめたメタアナリシスによれば、「関係重視型」は部下の満足やモチベーションに好影響を与え、「業務設計重視型」はリーダーのパフォーマンスに寄与することが明らかになっています。
■理論3:コンティンジェンシー理論(1960~70年代)
「コンティンジェンシー」とは「条件付き」の意味です。
この理論では、リーダーのスタイルや特性の有効性は、状況次第で変わるとされています。つまり、特定のリーダーシップスタイルが常に効果的とは限らず、状況に応じて適応が必要だという考えです。
この流れから、1970~80年代に登場する次のような新しい理論へとつながっていきます:
――――
リーダー・メンバー・エクスチェンジ理論(LMX)
トランザクショナル/トランスフォーメーショナル・リーダーシップ
――――
■理論4:リーダー・メンバー・エクスチェンジ理論(LMX)(1970~80年代)
LMX理論では、リーダーと部下一人ひとりの「心理的交換関係(エクスチェンジ)」に注目します。
従来は「リーダーの行動は部下全体に均一に影響する」という前提でしたが、現実はそうではありません。リーダーと部下の関係性によって、成果や満足度に違いが生まれるとされています。
興味深いのが、グラーン(1984年)が提唱した「LMXを高めるための3つのコミュニケーション」:
――――
・部下の悩みや課題を傾聴する(アクティブリスニング)
・課題に対して、自分の意見を押し付けず尊重する
・お互いの期待を共有する
――――
特に、もともとLMXが低かったリーダーと部下のペアでは、これを実践することで部下の自己評価やパフォーマンスが向上したそうです。
■理論5:トランザクショナル&トランスフォーメーショナル・リーダーシップ(1980〜90年代)
トランザクショナル・リーダーシップ:いわば「交換型」「管理型」。業績に対して報酬を与えたり、問題がなければ干渉しないといった手法を取ります。
トランスフォーメーショナル・リーダーシップ:ビジョン提示や啓蒙によってメンバーを成長に導くスタイル。以下の3要素から構成されます:
――――
カリスマ性
知的刺激
個人への配慮
――――
■シェアド・リーダーシップ(2000年代〜)
最後に、近年注目されているのが、「誰か1人」ではなく「メンバー全員がリーダーシップを発揮する」というシェアド・リーダーシップです。
ウォン(2014年)による42件の研究をまとめたメタアナリシスでは、「数値的リーダーシップ(上司による管理)」よりも、「シェアド・リーダーシップ」の方がチーム成果に良い影響を与える傾向があることが示されました。特に複雑なタスクを扱うチームではその傾向が顕著だそうです。
ちなみに、ウォンは、現代のリーダシップで最も強力なのは
――――
「全員がビジョンを持ち、互いに啓発し合い、知識を交換する姿」
――――
だと説かれています。
これはつまり、トランスフォーメーショナル・リーダーシップとシェアド・リーダーシップを両立させるような在り方です。そしてその根本にあるのが
――――
「自分は何者で、何を成し遂げたいのか?」という個人のビジョンの明確化
――――
だと言える、と述べており、一人ひとりが「ビジョンを持つこと」が重要だと述べていました。
■まとめと感想
個人的には、最後に紹介されていた「全員がビジョンを持ち、互いに啓蒙し合うこと」が特に印象に残りました。
自分自身も「何をしたいのか」「何を目指すのか」といったビジョンを持たずして、行動に意味を持たせることは難しいと感じています。リーダーシップとは結局のところ「影響力」ですが、志がないところに、道は生まれない、とも思います。
近年のビジネススクールでも「志」や「パーパス」が重視されていますが、こうした青臭いものではなく、不確定な時代だからこそ、多くの人に求められているものだと、私には思えます。
そして改めて、このリーダーシップというテーマを「ミクロ心理学ディシプリン」という視点で整理したことで、より深く理解できたように感じました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
※本日のメルマガは「note」にも、図表付きでより詳しく掲載しています。よろしければぜひご覧ください。
<noteの記事はこちら>