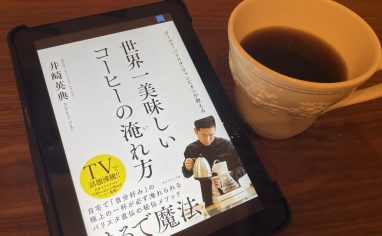『人脈のできる人 -人は誰のために「人肌ぬぐ」のか?』 読書レビュー#1
(本日のお話 1996字/読了時間2分)
■こんにちは。紀藤です。
昨日は大学院のランニング部。
25kmのランニングでした。
今月は300km目標に対して、まだ156kmなので、
なんとかこれから走行距離を増やしたいところ。
仕事が多く、果たしてできるかどうか不明ですが、
できる限りがんばりたいと思います。
*
さて、本日のお話です。
「人脈」なる言葉があります。このあたりのキーワードが含まれる書籍は、2010年前後の本が多く、ちょっと前に流行った言葉、のような印象でしょうか。
さて、この「人脈」について、法政大学ビジネススクールの高田氏が実際にビジネスパーソンに向けて研究をし、また人脈とはどういう言葉なのかということを定義した読みやすい専門書があります。
===================
『人脈のできる人―人は誰のために「一肌ぬぐ」のか?』
高田 朝子 (著)
===================
本日はその本に書かれている内容を紹介してみたいと思います。
2010年の本で、SNSなどのつながりは考慮されていないものあり、人と人のつながりがどのように生まれるのかを考える上で面白い本でした。
それでは、どうぞ!
■無形資産としての人脈
「人脈」は、あったほうが良い、そんな印象はなんとなくあるように思われます。
また、100年時代の資産に「社会的資本」という人とのつながりが表現されることもありますが、確かに人とのつながりによって仕事が生まれたり、あるいは助けられたりということはありますね。これは体験的にも感じることではないでしょうか。
・・・とは言いつつ、ではこの「人脈」というのは一体何なのか。
何回か飲み会に行けば、それは人脈と呼べるのか?
お互いに修羅場経験を共にして、深い信頼関係で結ばれた時間を過ごしたから、人脈と呼べるのか。
少なくとも、相手のことを知っているだけでは「人脈」とはなかなか呼べない印象です。では人脈というのは、どうなったら人脈と呼べて、どうしたらそのような人脈を作ることができるのだろうか。
そんな問いに関して、人脈という言葉の定義と、また「できるビジネスパーソン」や「医師」「女性」などと対象者を変えて、定性的なインタビュー調査などを行いつつ、学術的な観点からも人脈というものを明らかにしたのが本書になります。
■本書の概要
まず、本書の概要について簡単にお伝えします。
まず、本書では、「人脈」とはただ知り合いが多いということではなく、
“自分または自分たちのために一肌脱いでくれる可能性がある人”という定義に立ち、どのような人間関係が“使える(本質的な)人脈”になるのかを、理論・構造・実例をもとに論じます。
著者は、単なる「名刺を交換する」「フォローアップをマメにする」という表面的な人脈づくりではなく、「修羅場を共にした経験・信頼・期待感」があるかどうかが鍵になると主張しています。
◎本書の目次(章立て)
以下は本書の大まかな章構成です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第1章 人脈とは何か?
第2章 人脈を科学する―いつから人脈か、どこまで人脈か?
第3章 デキる人の人脈―考えたこともありません?
第4章 医師の人脈―専門職者たちの緊密な世界?
第5章 女の人脈―女と男はメンテが違う?
第6章 人脈の構造を読み解く―なぜ、どうやってできるのか?
第7章 悩めるあなたへのアドバイス―「最強の人脈」を作るには?
第8章 マネジャーへのアドバイス―つながりやすい組織とは?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
■本書のメッセージのポイント
本書の中心的なメッセージはこのようなものです。
◎「一肌脱ぐ人」が人脈の核心
著者は、人脈とは「自分が本当に困ったときに、一肌脱いでくれる人」の集合体だと述べています。
たとえば、助けを必要としたときに動いてくれる人がいるという期待感・信頼感が、その人との関係を“人脈”と呼べるものにするという考えです。
◎“修羅場”を共にした経験が信頼を育てる
特に「一緒に修羅場をくぐった経験」があると、人とのつながり・信頼関係が強くなると述べています。修羅場とは、「時間制約」「アウトプット要求」「未知の手順」という三つの条件がそろった、試行錯誤や高ストレスの状況です。
◎人脈は「ギブ&テイク」だけではない
また、帯や紹介では「人脈づくりに必要なものは、マメなフォローでも、ギブ&テイクでもなかった…」と記されています。
つまり、ただ「与える/受け取る」関係を繰り返すだけでは、深い人脈にはなり得ないというメッセージです。長期的に、自分も相手も何かを差し出すであろうという信念が育つことが大事とのこと。
◎職種や性別で「人脈の構造」が違う?!
本書ではさらに、「いつから人脈か、どこまで人脈か」「人脈の構造」を分析しています。たとえば、専門職(第4章)や女性の人脈(第5章)など、属性や文脈によって人脈の構造や動き方に差があることも取り上げられています。
■まとめと感想
「人脈」と言われた時にぼんやりしたものを、構造的に考える面白い本でした。たとえば、「家柄での人脈」みたいなもの、「大企業の上役ゆえの人脈」はどのようにできてるか、などなど。
また、「第6章 人脈の構造を読み解く―なぜ、どうやってできるのか?」では、どのように生まれるのかというメカニズムも語られており、ライフハック的にも面白いものでした。これはまた後日、追って紹介したいと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
※本日のメルマガは「note」にも、図表付きでより詳しく掲載しています。よろしければぜひご覧ください。
<noteの記事はこちら>