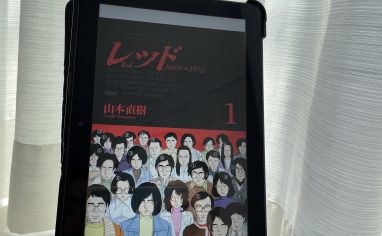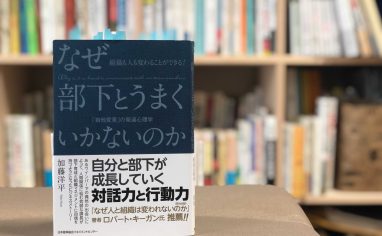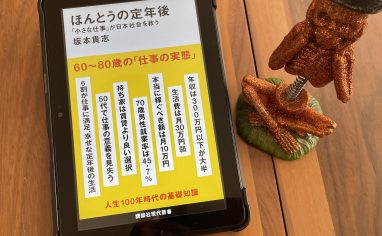室内楽コンサートで「ピアニストが新聞をビリビリに破いていた話」からの学び
(本日のお話 2504字/読了時間3分)
■こんにちは。紀藤です。
今週は、新入社員向けの研修が3日間あり、
また大学でのリーダーシップ・プログラムの最終発表会があったり、
コーチング✕AIのパーソルさんのイベントに参加したりと、
お仕事としてもなかなか濃密な1週間でした。
また、月曜日は「トランペット✕ピアノの室内楽リサイタル」へ行き、
また金曜日は「サントリーホールで都響のオーケストラ」の鑑賞へ行きました。
なぜか、気づいたら縁遠かった「クラシックのオーケストラ」にちょくちょくいくようになっているのが不思議です。
今日は、この「オーケストラに行った話」をテーマとして書いてみたいと思います。結論、クラシックの面白さをより知った気がしたと思いました。
それでは、どうぞ!
■オーケストラにいく「謎の会」
人のつながりは、新しい世界を連れてきてくれます。
私が最近オーケストラに参加するようになったのも、ある友人とも先輩とも先生とも言える方々とのつながり(通称:謎の会)でした。
謎の会のメンバーは3名。
1人は、私。もう1人は、元大企業で役員をされており、その後独立された60代半ばの経営者Mさん。そして最後が、30代半ばの哲学者Hさんです。
それぞれ、私が憧れを抱かずにはいれない経験や、人柄・能力などを持ち合わせている、尊敬する人たちです。
そんな彼ら(一応私も含む)は、「クラシック音楽」が共通点です。
チェロがお好きでオーケストラに定期的に訪問する方、トランペット奏者で絵画も嗜む方、ピアノを趣味でやっている人(私)などなど。
友人という感じでもない「謎の会」として、いつぞやか、半年に一度くらい、よさげなオーケストラに一緒に行ったり、あるいは私のぶっ壊れたのカンパネラのピアノ発表会まで来てくれたりしました。
そして、今週はたまたま2回のコンサートが開催され、月曜日と金曜日に、一緒に鑑賞しにいったのでした。
■「地上最高のトランペット奏者」がやってきた
さて月曜日に、Hさん(トランペット奏者)が、日本で来るのは最後になるかもしれないというトランペットの世界的奏者がやってくるとのことで、ヤマハホール銀座にて、ピアノ✕トランペットのコンサートがありました。
ちなみに、トランペットは古典派→ロマン派→近代→現代など色々とクラシックでも時代ごとの特色があるようですが、トランペットは古典音楽ではそんなに頻繁に登場することが少ない傾向がありました。
しかし、ロマン派後期以降はトランペットもソロで登場するようになったり、だいぶ活躍の場が広がっているそうです。
そして、ホーカン・ハーデンベルガー氏は「地上で最高のトランペット奏者」という方の演奏だそうで、それならばということで、そもそもトランペットとピアノというコラボレーション自体がみたこともありません。
なので、「とにかく食わず嫌いせずにいってみよう!」となりました。
■ピアニストは、新聞をビリビリに破いていた
そして、コンサートが始まります。そこには、トランペット奏者のホーカン氏と、韓国のピアニストの2人。
私は、前から2列目の席でしたが、音圧がすごくて、振動がビリビリ伝わってきて、ドキドキしました。
1曲目は、おそらく王道っぽい曲(細かくわからなくてすみません)で、トランペットって、こんなに自由に演奏できるんだ・・・と驚きました。
非常に小型のピッコロ・トランペットや、やや大きめのバストランペットなど。トランペット✕ピアノの室内楽というのが、新鮮な体験です。
ただ、びっくりしたのが2曲目以降です。ピアニストのとなりに、台のようなものが置かれており、またヘッドセットのようなマイクもつけています。
なんだろう…と思いつつ、曲を聞いていると、ある曲が盛り上がってきたタイミングで、ピアニストが曲の途中で、急にイスから立ち上がりました。
そして、台の上に歩き、そこに置いてある「新聞紙をビリビリに破りはじめた」のでした。
「!!」
そう思ったのも束の間、その後、トランペットが不思議な音の連続でおしゃべりするように音を返します。
すると、その直後、ピアニストが韓国なまりの日本語で「ナニヤッテンダヨー!!!」とツッコミ(?)のような言葉で叫びました。それに、トランペットの音で答える。
私は、どうリアクションしたらよいかわからなかったのですが、会場の聴衆は皆、真剣に聞いています。「これが、現代音楽なのか・・・」と度肝を抜かれた気持ちになりました。
■まとめ:音楽を楽しむということ
その後も、ピアニストがソロでいくつかの曲も弾いていました。
「亜麻色の髪の乙女 ー怒りー」という曲では、有名な「亜麻色の髪の乙女」のメロディから展開する形で、曲がヒートアップしていき、最後は拳でガンガン鍵盤を叩くみたいな演奏だったりして、これまた驚きました。
と思えば、白い手袋を急にはめて、あとはひたすらグリッサンドを繰り返してさざなみのような音を出し続けるとか、なんだか音楽ってこんなに幅があるんだなあ…と驚かされたのでした。
私も、ピアノを趣味として楽しんでいたものの、ショパンやリストなどが好きで、そればかり弾いていましたが、モーツァルトやバッハなどの古典も勉強した方が良い、とピアノの先生に提案されている今日このごろです。
そして、そうした曲を知ると、「ピアノの音をただ鳴らすのではいけない」という感覚が、ちょっとずつですが育ってきたような気もします(あくまでもそんな気がするくらい。まだまだ超勉強不足です)。
自分は耳も良くないですし、ピアノも上手ではないですが、そんな自分なりに楽しめるようにもっと勉強したいな、と思っている次第です。
次は、ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団の演奏会(チケットが高い!!)です。オペラ、古典、他にも色々楽しんでみたいな、と思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
※本日のメルマガは「note」にも、図表付きでより詳しく掲載しています。よろしければぜひご覧ください。
<noteの記事はこちら>