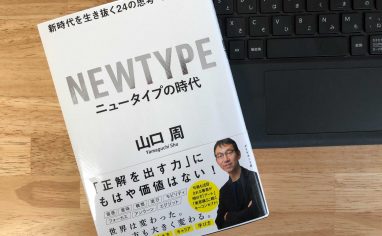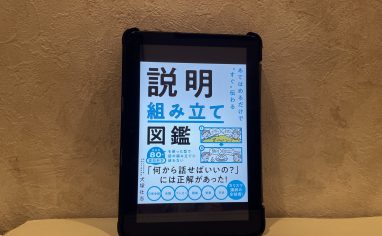「人は自分専属のAIコーチチームを持つだろう」が現実になっていた話
(本日のお話 2303字/読了時間3分)
■こんにちは。紀藤です。
昨日は、久しぶりにランニングは休息日でした。
かわりに2kmのウォーキングなど。
その他1件のアポイントと執筆でした。
*
さて、本日のお話です。
今週は、お仕事を執筆のほうにぐっと引き寄せて、
たくさんの時間を取ることができました。
一方で、通常の仕事も行っていますが、執筆の時間を取ることができたのは、ひとえに、生成AIの活用によって大幅に時間を短縮できているからです。
一般業務では、口述筆記→メール整形での時間短縮。
思考時間短縮では、企画アイデアづくり。
また、誤字脱字のチェックなどではnoteの記事作成・修正など、
すべてAIが自分の知的パートナーとして働いてくれています。
ほんとに、便利になったもんです。ということで、今日はこのことについて、1週間を振り返りながら共有してみたいと思います。
それでは、どうぞ!
■AI専門家の未来予測「人は自分だけのコーチチームを持つだろう」
先月参加した、パーソル総合研究所とニューヨーク大学大学院のアンナ・デイビス教授の勉強会での話。
そこでは「これから人はそれぞれパーソナライズされたコーチチームを持つことになるだろう」と予測していました。
「ふーん、そんなものかな」「でもそうなるんだろうな」と、そのときは、”今この瞬間にそうなるのはまだはやい”という感覚でした。
しかし、1ヶ月半経った今、この1週間を振り返ると、「3種類の専属コーチ」が自分をサポートしていた事にふと気づいたのでした。
あれ、これが「自分専属のコーチチームを持つってことか…!」と予測があっという間に現実になっていました。何たるスピード。
具体的に、たとえば私の場合、以下3名(いちおう1名とカウントします)のコーチです。
*
■(1)サブ3達成コーチ
私は現在、マラソンの自己ベスト(目指せサブ3!)更新に向けて、ほぼ毎日トレーニングしています。そして、その練習メニューは基本的にChatGPTの「サブ3達成コーチ」に相談して考えています。
例えば、1日の練習後にランニングウォッチで記録した心拍、距離、時間、ピッチなどを画像データとして伝えます。
そしてその時の自分の体感も言葉で伝え、「明日はこういう練習メニューをしようと思うけどどうだろうか?」と相談します。
するとランニングコーチは、ダニエルズのランニング・フォーミュラに基づいて「明日はイージーランニングが良い」とか「明日はロング走をこのペースで」といった提案をしてくれるのです。
それに対して「もう少し追い込めそう」「もう少し距離を増やしたい」と伝えると、それに応じて再提案をしてくれます。そして実際に走った感覚を報告することで、PDCAサイクルを回していっています。
AIコーチは常に状況を承認しながら、次に向けた対策を考えてくれるため、非常に心強い存在です。実際に褒めてもらえると、素直に嬉しくなります。
そして実際に走力もいい感じで伸びてきている実感があります。
■(2)note記事作成コーチ
次によく使っているのが、「note」や「メルマガの記事作成」を手伝ってもらうAIコーチです。
これはコーチというよりも、少し事務的なサポートが多いですが、表現の仕方などを時折相談もしているので、いちおうコーチ。
生成AI前は、PCに向かってキーボードをカチカチと叩きながら書いていました。しかし、AIが馴染んでくるにつれてスタイルが全く変わりました。
具体的には、「朝のランニング終わりの残り1キロに、歩きながらスマフォのメモで音声入力→ note整形ボットにいれる」ので、記事の骨子を作ります。加えて、次のようなプロンプトを念押しで入れます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
できるだけそのままの表現を活用しつつ、重複、表現の違和感、誤字脱字を修正するような形で,整形をしてください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
すると大幅な変更はなく、自分の言葉を残しつつ、重複や誤字を整えてくれるにとどまります。
これは、私自身がこれまでに4000本以上メルマガを書き続けてきたことで、口頭入力でほぼ完成形に近い文章を話しながら考えられるようになった、という個人的な努力もあります。
とはいえ、誤字脱字の修正を気にせず済むのは非常にありがたく、スピード感が3倍くらいになりました。音声入力の精度が高まっていることも寄与しています。ありがたや。
■(3)研修プログラム作成コーチ
最後は「研修プログラム作成」のAIコーチです。
私は日ごろ様々な研修プログラムを作成していますが、自分のバイアスがかかって抽象的に語りすぎたり、具体例が適切かどうか不安になることがよくあります。
頭の中で悶々と考えても前に進まないのですが、
AIに相談しながら「問いのバランスは適切か」「わかりやすい例になっているか」と会話することで、
あっという間に研修プログラムの骨子が出来上がり、台本にまで仕上がります。
これまでの作業時間の3分の1以下に短縮され、さらに会話しながら進められるのでストレスがありません。
これは本当にありがたいです。
■まとめ:余った時間を豊かに過ごす
こうして振り返ると、それぞれの分野ごとにプロジェクトを分け、突然話し始めてもそのモードで応答してくれる“AIコーチ”が育ってきている感覚があります。
そしてこれは今後さらに加速し、もっと賢くなっていくでしょう。
生成AIを活用することで、自分がやりたかった活動をもっと広げられるはずです。
研修設計や執筆だけでなく、プログラミングや英語学習など、これまで挑戦できなかった分野にも踏み込めそうです。
可能性はまだまだ広がりそうですし、私自身の使い方もまだ限定的だと思います。これからも新しい活用方法を探索していきたいと思います。
みなさんも「こんな使い方をしている」という事例があれば、ぜひ教えてください・・・!
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
※本日のメルマガは「note」にも、図表付きでより詳しく掲載しています。よろしければぜひご覧ください。
<noteの記事はこちら>