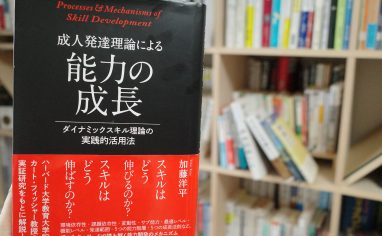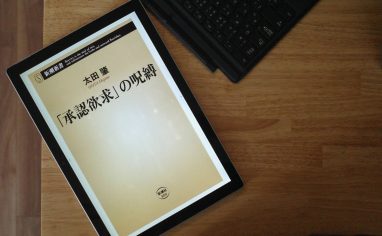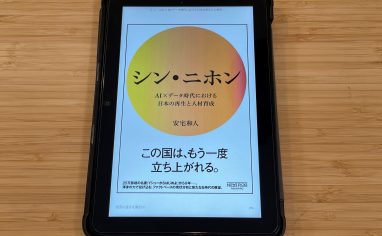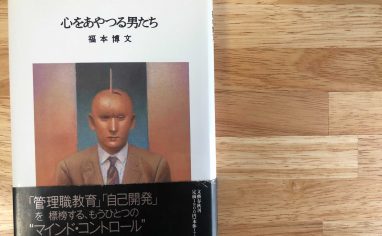「ホーセン工場実験」から考える、”職場の人間関係”が大切な理由
(本日のお話 1992字/読了時間3分)
■こんにちは。紀藤です。
昨日は3件のアポイント。
ならびに研修の準備などでした。
本日26日から年末のお休みに
入られた方もいらっしゃるのでしょうか。
良い年末年始をお過ごしくださいね。
*
さて、本日のお話です。
先日より読み進めております、
『組織行動 ー組織の中の人間行動を探るー』
(著:鈴木竜太、服部泰宏)
という書籍がありますが、
その内容が大変学びになっております。
今日はその中の学びから、
「なぜ職場において人間関係が大事なのか?」
について、ある興味深いお話が
紹介されていました。
そのお話について皆さまに
ご共有させていただければと思います。
それでは早速まいりましょう!
タイトルは、
【「ホーセン工場実験」から考える、”職場の人間関係”が大切な理由】
それでは、どうぞ。
■企業人事の方と
お仕事でお話させていただいていると、
よく耳にする話があります。
それは、人事の方の
こんな悩みです。
・コミュニケーションが苦手なマネージャーは
結構多い。
・ゆえに、「コーチング研修」など
提供しようと試みたりはする。
・ただ当のマネージャー本人の本音は
「何でコーチングとかやらなきゃいけないの?
成果を出せばいいんじゃないの」
「タスクも目標も明確にしているし、
給与や待遇も悪くない。
仕事だからやればいいでしょ」
「人間関係が大事とか
ただ甘えているだけじゃないの」
と感じているようす。
・”コーチング等を学んだりして、
部下の話を聞く必然性がわからない”と言われてしまう。
・というか、そもそも職場で
人間関係って本当に大事なのか?
、、、というような内容です。
上記の話は少し極端ですが、
仕事は仕事と割り切れる人。
目標は達成するためにあり、
タスク重視型のマネージャーに
多い考えのように思います。
■確かに、
・「仕事」で会社に来ている
「組織からの期待・成果」を出すために、
ここに集まって給与もらっている
・だから決められたタスクなど
各々やればいいんじゃない?
というのは、
一見シンプルな理屈なようです。
しかし、一方、
「そういった無機質な対応じゃ、
あまり上手くいかなそう」
という感覚も、
同時に覚えるのもあるのではないかと。
その大切さは、昨今の
「心理的安全性」や
「エンゲージメント」などの
キーワードに繋がっており、
あえて今声を大にして言う必要も
ないのかもしれません。
■、、、しかし、”そもそも”ですが、
「職場で人間関係が重要」という考えは、
いつから生まれたのか?
そんな中で、一つ、
興味深い実験があります。
最新の研究ではなく
もう90年以上前のハーバード大学の研究で、
『ホーソン工場実験』
と言われるものです。
これは、1927年から1932年、
アメリカのシカゴ、ウェスタン・エレクトリック社の
ホーソン工場で実施されました。
この実験は、途中からハーバード大学の
エルトン・メイヨー、フリッツ・レスリスバーガーらが
研究に加わりました。
その実験は、
「様々な状況下で、
生産性がどう変化するのか?」
という、「生産性を高める要素」を
見つけるための実験でした。
■そして、その
「ホーソン工場実験」の結果、
当初の予測と全く異なる
興味深い結果がでたのです。
まずわかったこと。
それは、
・作業所を暗くしたり、
・労働条件を変えてみたり、
さまざまな作業条件を
設定したにも関わらず、
実験対象に選ばれた女性たちのグループは
「高い生産性を保ち続けた」
ということ。
(つまり、作業条件では、
生産性は変わらなかった)
そして、作業条件を元に戻したところ、
過去最高の生産性を示しました。
■、、、はて、これは何だ?
作業条件を変えても
”生産性”は下がらない。
では、一体何が彼女たちの
「生産性」を高めているだろうのか?
結果、ハーバード大学の
メイヨーはじめ、結論付けたことは
「彼女たちの生産性を支えているのは、
作業条件の良好さではなく、
『職場の人間関係である』」
ということでした。
実験では、監督が高圧的に監視はせず、
女性工員は自由な雰囲気で仕事ができている、
作業条件の変更の際は女性工員に事前に相談がなされ、
工員たちが反対した変更が強行されることはなかった、
など、
実験対象の彼女たちへの配慮が
「働きやすい関係性」を構築し、
喜んで仕事をすることで生産性が上がったのでした。
■これが「ホーソン工場実験」の結果であり、
この実験の前までは
「疲労・報奨と罰のあり方」などの
作業条件で生産性が変わると考えられていましたが、
【「職場の人間関係」「監督者の態度」といった社会的条件が
”モチベーションを高め生産性に影響を与える”ことが示された】
と生産性に対する考え方が変わったのです。
そしてこれは、
「メイヨーの人間関係論」として
今につながっています。
■この実験を見ると、
90年前の過去から振り返ってみても、
仕事や産業が変わっても、
”人間関係が良好であることは、
生産性につながる”
ということが言える、
そもそもの実験結果かと思います。
そうすると、マネージャーが
「何で私が部下の話を
聞かなきゃいけないんだ?」
という疑問に対しての回答は
『それは生産的な職場を実現するために、
”人間関係を良好にすることが不可欠”だから』
と言えるのでしょう。
■人は機械と違います。
ゆえに、関係性の善し悪しは
良い生産性を保つ上でも
とても大事なことになるのでしょう。
ということで、
「職場の人間関係はやはり大事」
であるし、
「リーダー/マネージャーは、
職場の関係性を良好に保つことが
成果にも繋がる」
のだな、ということを
改めて学んだ次第です。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
===========================
<本日の名言>
私は声をあげて称賛し、
声を和らげてとがめる。
エカチェリーナ二世(ロシアの女帝/1729-1796)
===========================