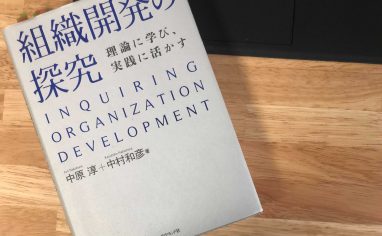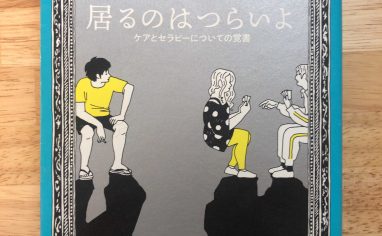プレイフル・ラーニング体験記 ー学びの場をつくる「3つのS」ー
(本日のお話 4654字/読了時間4分)
■こんにちは。紀藤です。
この土日に、大阪万博会場の夢洲の隣「舞洲」にて、
上田先生の「プレイフル・ラーニング」のワークショップ『Party of Future』に参加してきました。
このイベントは、著書『プレイフル・ラーニング』にある「本気で遊び、その遊びを通じて学ぶ」というコンセプトをもとに、定期的に開催されているものです。
…とはいえ、伝説のワークショッパーとも称される上田先生自身によるイベント、あとどれくらい開催されるかも不明です。そんな中、今回たまたま参加できたことは僥倖でした。
そして、参加してみて「本気のプレイフルな場作り」とは、ここまでやるのか…!と、固定観念を壊された感覚です。
楽しいワークショップというものを、部分的にしかわかっていなかったんだな、と思わされました。
ということで、今日はその体験の一部を、できるだけ言葉にして共有させていただければと思います(超難しいですが)。
それでは、どうぞ!
■24時間のワークショップ
本ワークショップですが、当日まで何をやるか、全くわかりません。
また当日は「自分の好きな本を持ってくる」「スイーツを持ってくる」「問いを持ってくる」などの準備が案内されました。
(本当は事前のオンラインの集まりに参加することで、イベントの準備から参加する機会があったのですが、私はタイミングが合わずできませんでした)
8月9日(土)の正午12:00がワークショップの開始。
そして、8月10日(日)翌日昼まで約24時間です。
到着早々、会場は受付から仕掛けだらけ。
今回のテーマである『Unlock』にかけて、文字が書かれた(Lockとかだった気が)A4用紙をパンチで破ったり、「自己紹介カード」や「ジャンプ動画撮影」、「持参した本へのオリジナルカバー作成」など、その場作りに参加をしていきます。「参加者100人分のスイーツ持ち寄り(&早速食べまくる)」など、自然と交流が生まれるアクティビティが並びました。
そして、開始時間。「イエーイ!!」と、突然の爆音でのバンド演奏。何が起きたかわからないまま、Adoの「私は最強」が大音量で流れ、超絶な歌唱力持ち主の参加者が歌い出す圧巻の幕開け。
会場は手拍子と歓声に包まれ、強制的ともいえるほどの巻き込み力に圧倒されました。空気に馴染むとかじゃなく、ねじ込まれる感じです。
私の個人的感想で言えば、お盆の初日、新幹線チケットが取れず、朝6時から立ちっぱなしで東京→新大阪→万博会場から4km歩き、
ひとしきり体力を使い果たして会場に到着した私は「ワークショップお疲れ様でした!!」と、フィナーレ気分になりました(他の仲間も同じ感想を持っていた)。
息着く間もなく、屋外におもむろ置かれていた白いTシャツの山。
そこに、全員でスポイトで色水を垂らしてデザインするアート作り。
音楽に合わせて、身体を動かしながらやってみてください、という情報量が多すぎる展開ですが、不思議とその場に併せて、皆が溶け合っていく感覚があります。
その後は、「皆で歌と踊りをやったりします。なんだかわからないけど、できちゃったというのを目指します」というような案内だけあると、よくわからず、気づいたら踊りの練習が始まっていました。
そのまま、小中学校の頃にやったような「合唱コンクール」ばりの歌のレッスン。ソプラノ・アルト・テナー・バスと、パート練習が始まります。ちなみに、このイベントのためだけに作られたプロの作曲家の曲のもと、プロのボイストレーナーと、プロのダンスの先生のもと、合唱とダンスを完成させていきます。ほんとうに、ガチです。
12時から17時までほぼノンストップ。何度もやり直しをしながら、一曲を完成させ、気づいたら夕方。そして、夜は分科会として教育、アート、組織開発などのテーマで語り合い、深夜まで続いていきました。
■「場が人を巻き込む」の仕組み
プレイフルなワークショップの特徴は「誰もが参加してしまう場の設計」にあります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・全員で同じTシャツを着る
・持ち寄ること、一緒に歌を歌うこと、身体を使ったりハイタッチやアイコンタクト
・グループ間でフォルトライン(境界)ができないような工夫
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
全員が、参加者であり、運営チームになっています。
ダンスや歌も、身体性を伴うアクションにも意味があります。「自分の体が開く」感覚は、「自分の心を開かせる」という心身の連動につながります。
一方、こうしたダンスや歌が苦手な人もいます。そういう人は、実は撮影や編集、グラフィックレコーディングなどとして参加し、輪に入れない状況が生まれないようにされていました。
これは、参加者で運営として関わっている人から、そのタネのような話を聞かせてもらったのですが、こんなお話でした。
「『自分は変われない』『人の能力は生まれつき決まっている』と考える『固定思考』の人は一定数存在します。その中で、設計された場の力によって、固定思考から一歩を踏み出すことができるのが、プレイフル・ワークショップの一つの効果です」
とのこと。「場が人を巻き込む」ことを可能にする、学びの場作りの真髄を見たように思いました。
■完璧に準備し、思い切り手放す
さて、これらのワークショップは、その場で「柔軟にゼロから作っている」ように見せて、実は「入念に設計されているもの」でした。
正しく言えば「完璧に準備し、思い切り手放す」という表現が正しいようです。主催者の一人がいわく「どんな事が起きても大丈夫なように、あらゆる準備をしてきた」とのこと。
実際は大きな流れはあるけれど、集まった人がアドリブで作り上げていく。そのアドリブに対応できるツール(環境やステージ)を、使わないとしても用意していたのだそう。
進行の多くは即興に見えますが、実際には1年をかけた周到な準備が背景にあります。プロのミュージシャンやダンサーを揃え、本気度を示すことで「遊び」ではなく「真剣な体験」に変わる設計。また、プロの演者も参加者として場に入り込むことで、あちら側とこちら側という上下関係を感じさせない関係性が生まれていました。
しばしば「入念な準備が必要」といいますが、深さの違いを感じます。
■学びと遊びを融合させる「3つのS」
2日目の振り返りでは、ある木で作られた「TVボックス」のようなステージが作られました。
分科会の内容を、”30秒で発表、時間が経ったらシャッターが降りて強制終了する”というステージでは、笑いと熱気が生まれました。全員がイキイキとプレゼンをしており、「リフレクション」という静かな感じとはちがうものでした。
また、その後、床いっぱいに広げた模造紙(ロッケンロール=六間のロール紙)に皆が床に落書きのように「ワークショップの振り返り」を書き、それを練り歩きながら、皆でこの1日間何が起こったのかを観察しました。
上田先生曰く、リフレクションとは静かに反省みたいなものではなく、「アプリシエーション」(価値を認めることで、我が物にする)ことだと思う、といっていたのが印象的でした。
そして、その後、初めてとも思われるような、少し理論的な上田先生のお話がありました。「今回の場のデザイン(学び✕遊びの場作り)には『3つのS』が必要だと考えてます」と。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1.STUDIO(=スタジオワークでアトリエ活動を行う)
2.SHELL(=1人空間”シェル”で自分と対話する)
3.STAGE(=ステージに上がってパフォーマンスを行う)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
たとえば従来の学びでは、「先生の話をしっかり聞く」「テキストで学ぶ」という発想が強く、遊びと学びは別物とされがちです。
「適切なスタジオ、シェル、ステージが用意されれば、皆がもっと自分事として体験したことを学びに変えられる。しかし、適切なステージなしに急に発表してください、と言われてもなかなか難しいんです」
「そして、この話を、何も体験していない時に言われても、わからない。今のタイミングだから、この話が『わかる』んですよね」
そのような、こうした話を、実際にそのことを「体験したあと」に言われるからこそ、本当に理解できる。”腹落ちする”のは、体験に言葉が乗ってこそ生み出される。そう感じました。
■まとめ:わたしの学びのポイント
今回の参加者は、学校関係者の方が多く、高校や大学の先生もいらっしゃいました。また海外の大学院で学ばれた方や、ダンサー、建築、音楽関係の方などバックグラウンドが多彩で、「教育」という大カテゴリは同じでも、”隣の領域”というような、やや違うところが興味深いものでした。
なので、立脚している理論など、知らない単語もたくさんあり、それが「自分は知らないことばかりなのだ」と越境学習のアハ体験を多くすることができました。
それらも含めて、今回の体験から得た学びは大きく3つです。
(1)周到な準備の重要性
「場をつくる」ためには、事前の巻き込みや一つひとつの活動の意図を明確にした設計が欠かせないこと。あらゆることを想定するからこそ、手放して、参加者による場のデザインが可能になります。
事前準備、音楽、ツールなど、準備はいくらしても良いと思いました。
(2)身体性を伴う学び
身体と声を全力で使うことの重要性も学びました。声を出す、身体を動かすこと。不思議なもので、身体を開くことは、個人の中でエネルギーを循環させるような印象があります。
それを、集団で行うと、抽象的なようなのですが、参加者間でもエネルギーが循環し、それが関係性が深めるような感覚も覚えました。
そして、それが日常の自分の枠(思考や関係性)を越える補助線となることを強く感じます。身体を使った学びは、学びの質を大きく変えます。
(3)ファシリテーターが本気で楽しむこと
誰かに納得感がある伝え方をするには「物語とデータ」が必要といいます。
しかし、学びを記憶と身体に刻むためには、そこに加えて『体験』が必要だと今回思いました。
未だに、この場でたくさん歌った歌の歌詞とメロディが頭の中に流れ続けています。これから、この学びを、私も実際の場づくりに活かしていきたいと思った次第です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
※本日のメルマガは「note」にも、図表付きでより詳しく掲載しています。よろしければぜひご覧ください。
<noteの記事はこちら>